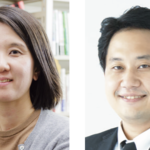『公研』2020年10月号
東京大学先端科学技術研究センター教授 池内 恵
1 戻る人波、消えた姿
とある美術館の展示に添えられた、主催者の言葉が目を惹いた。「新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの眼を、いつも以上に、日常のくらしとそれを取り巻く自然の変化、そして芸術や文化の存在へと向けさせることになりました。本展会場を一巡することで、くらしと自然そして芸術の豊かな関わりを体感し、激変する社会における現在の、そしてこれからの生活を改めて考えるきっかけとなれば幸いです」とある(京都国立近代美術館「京のくらし──二十四節気を愉しむ」展、7月23日─9月22日)。
コロナ禍は着実に経済を侵食し、人心を蝕んでいっている。芸術・文化をめぐる産業は最も打撃を受け、また「不要不急」として切り捨てられ、置き去りにされかねない分野である。何年もかけて準備・調整してきたであろう、こういった展覧会も、開催そのものが危ぶまれ、展示方法や規模を変更してどうにか実現の運びとなったのだろう。その間の苦労が忍ばれる。不安と不透明を抱えながら辛うじて開催にこぎつけた時の、主催者としての喜びや、改めてとらえ直した企画の意義をめぐる思い、そして決意が、こういったちょっとした文言から感じ取られる。日々にとらえ直し、決意をし直す、コロナの時代の生活である。
それにしても「日常のくらしとそれを取り巻く自然の変化」には敏感になった。展覧会は通りいっぺんに言えば「関西の都市の上流階級の生活史」などというくくりに入るものであり、以前であれば関心も抱かず、展覧会の存在にすら気づかなかったであろう。そんな私にしても、会期終了間近にこうして時間を見つけて訪れている。時期は、「シルバーウィーク」といつの間にか呼び習わされるようになった、9月の秋分の日に至る4連休であった。
秋分の日が巡ってきたということは、「あれ」から半年がたったということである。「あれ」というのは、3月の春分の日とそれに続く週末の三連休のことである。思い出してみることができるだろうか。2月下旬から数回にわたって要請され、小刻みに延長された外出自粛の果てに、緩んだ陽気、開いた桜花に誘われて、多くが「禁」を破り一斉に行楽地に出た半年前の雰囲気を。その後の急激な感染拡大を、連日のテレビ報道によって、グラフで目に焼き付けられ、国民的な「悔恨」を迫られ、一段と厳しい「自粛」の日々に踏み込んだことを。あれから半年の月日が流れたのである。
天体の正確な動きと共に訪れた秋分の日に連なる4連休に、人々は(私を含む)、再びそれぞれの行楽地に足を伸ばした。このたび政府は「GoTo」等の経済振興策で、人々に外出を促していた。感染第二波が先行したことであたかも「譴責」を受けるかのように観光振興策から除外されていた東京についても、この連休に先立って、翌月からの「解禁」が告げられていた。
それによって「機が熟した」あるいは「自粛の禁制が緩んだ」と多くが内心に受け止めたのだろう。都市によっては、繁華街で局地的にコロナ前をも凌ぐ人出となったという。もちろん、旧に復したわけではない。人混みの中に、コロナ禍が訪れる瞬間までは多くを占めていた外国人観光客の姿はない。いわゆる「インバウンド」の姿は消滅しており、いつ戻るかは全く未定である。そもそも戻るか否かも分からない。どのような形で戻していくか、見通しは示されていない。さらに言えば、「自粛警察」とも形容される社会の反応により、県境を超えた移動、地域を越えた移動への忌避感情が定着し、容易に払拭されていない。特に「東京から来た人」への、差別や敵意とすら見られる感情が地方社会で噴出したことは、それを実際に体験した者からは、忘れようとしても忘れ去ることは不可能な、違和感として残り続けるだろう。その代わりに、地域圏の中での人の流れが活発化し、緩やかな地域分権や人口の分散化につながっていくのか。まだ先は見えていない。
世の中には「インフルエンサー」と呼ばれる、ちょっと身軽な、活発な人たちがいる。こういった人たちは、秋分の日前後の自粛緩和の兆しを敏感に察知し、新幹線に飛び乗り、それぞれの思う行楽の地に足を伸ばし、InstagramやFacebookといったSNSに、カミングアウトしたかのように画像を上げていった。こういった層の動きは、感染拡大の初期の局面においてはマイナス要因になっているのだろうが、リスクを犯してでも経済を回復させなければならない局面においては、変化の先ぶれ、前向きの動きとなるのだろう。
これらの新たに出てきた人の流れが、本格的・恒常的な社会活動の正常化への第一歩なのか、あるいは期間限定の「お試し」であり、自粛疲れを凌ぐ一時的な気晴らしとして許容されたものに過ぎないのかは、これから訪れる冬季にどの程度の感染者と致死率になるかにかかっている。誰も安心していない。束の間の観光で、訪れる先の光景が、どこか以前とは異なったものとなっていることへの違和感や、将来への不安感を押し隠しながら、人々は黙々と義務のように、SNSで「近況」報告を行う。その間にも刻一刻と時は経過し、不可逆的な変化が目に見えないところで進んでいく。それらはもちろん、悪いことばかりではない。
2 再生の芽吹き
この連載も、6回を数える。6カ月という月日は、コロナ禍という事象において、長いのか短いのか。過去のこういった疫病では、数年の月日を経て、感染の拡大と小康状態を繰り返した上で、やがて人類がウイルスに十分慣れるか、ウイルスが弱毒化・無害化するなどして社会に溶け込み、事態が収まっていったようである。そのような時間軸の中では、半年はまだ、「とば口」に過ぎないかもしれない。
とは言え、個々の人間の生活実態としては、社会的な活動が大幅に制約された中での半年間は、かなり長い時間である。その間に止まって待っていてくれないのは、人間社会の否応ない新陳代謝、死と再生のプロセスである。先月号のこの欄では山崎正和さんの死去をめぐる随想を綴ったが、それだけではなく、私が3月の連休にふらふらと迷い込んだとある名所の付近に居を構えていた、私にとって恩のあるとある分野の大家の先生は、その頃すでに、不慮の事故に起因して死の床に就いておられたことを、後になって知った。
もちろん待たないのは死だけではない。少子化でずいぶんと先細りになっているとは言え、次世代の再生の芽吹きも感じられる。新たに社会に参入していく若者たちの動きは、制約の下でも止まらない。また止まってはならない。大学という場で「学事歴を止めない」ことを一念に一丸となって春の学期を凌いだ我々教員も、このプロセスを裏から支える立場である。
私が予防的な「自主隔離」のリモート勤務の拠点と定めたこの土地で、定点観測・生存確認のように訪れていた古びた喫茶店の常連客の一人が、ある日、手に手を取って結婚を報告に来た、そんなところにも居合わせた。この方は西欧のある国からこの地を訪れ、定住した外国人であり、コロナ禍で故郷の家族との往来が途絶える中、当地にて知り合った相手と、大きな式を挙げることもなく、近しい友人のみでお披露目・祝宴の会合を開いたところだという。こんな時には、「東京からの客」に厳しく目を光らせるようになっていた喫茶店のマスターや常連客たちの警戒心も和らぐようで、数名の「東京からの友人の集合と祝福」を暖かく見守っている。また、そういった口実でもあって人が動いてくれなければ、経済がもたない、という感覚が、「インバウンド」には直接裨益せず「観光公害」に冷ややかな目を向けていた層にまでも、広がった時期でもあった。
私のほうでは、突然にこういった若い人の門出に出くわし、もごもごと祝いの言葉を口にし、場を壊さないように早期に辞去する仕草も、板にはつかないが、いつしかそれなりに身につけていることに気づく。コロナ禍の中でも着実に進んでいく、自分自身の、社会の中での高齢層への押し上げ、あるいは押し出しであり、自分がプレイヤーとして一線に立つだけでなく、若者をサポートしなければならない立場に、否応なく立っている。戸惑いつつも、気持ちを新たに持つしかない。
3 リモートでの事業拡大
この未曾有の事態の中で進んだ2020年という年度の前半は、私にとっては仕事の上で、単独行動を好む個人プレーヤーから、プロジェクトを提案し予算を獲得し運営し実施する、組織者としての「生まれ変わり」の時期に当たった。地球的な規模での社会環境の激変の時期に、偶然にも、個人的には仕事の環境や形態の激変を経験していたことになる。環境が一定の中で自分の側だけが変化を迫られるよりも、コロナ禍の下での移行のほうが、より摩擦が少なかったと言えるのかもしれない。職場の環境、国内で仕事をする上での関係先の環境、そして私の仕事上で関係が深い中東という地域や、私が自らの運営する部署やプロジェクトにおいて掲げる「グローバルセキュリティ・宗教」という問題に関わる環境が、いずれも激変し流動的になる中で、前例の少ない規模と手法を導入した研究室運営の組織の設定と移行が、いわば非常時のどさくさに紛れて、さほど知られることなく、つまりさほどの摩擦を生むことなく、進んでいった。
ここで取り組んでいたのは、研究室の予算面と人員面での急拡大であり、大規模な研究プロジェクトとその実施運営のための組織の発足である。これは私自身にとって、仕事の環境の大きな変化と、そしてその前提となる生活の変化を不可欠とするものだった。
私自身は、これまでの研究者としてのキャリアにおいて、異例とも言える自由さを享受してきた。これまで三つの職場を移動したが(これは研究者としては標準的な数である)、それらはいずれも「研究所」である。最初に勤めたのが経産省系の地域研究の機関(独立行政法人)で、次は「大学共同利用機関法人」という、一般には耳慣れないが、全国の大学間の共同研究を促進することを目的とした研究所の一つに職を得た。現在所属する東京大学先端科学技術研究センターは、国立大学の附置研究所という、これまた一般にはそれほど理解が容易ではない存在で、大学の学部のようなものだが、第一義的には教育よりも研究を目的としている。まとめると、私はこれまで、「大学(准)教授」を名乗っている時期が長いにもかかわらず、一度もいわゆる「学部」に所属して、自分の学部学科の学生を教えていた時期がない。非常勤で、大学の中の、あるいは他の大学の学部に教えに行くことはある。しかし「自分の学科の学生」を育てるという経験をついぞしたことがない。しかも私の場合は准教授(以前の制度の職名では助教授)の時期から、自分の分野についての小さな部署を単独で運営させてもらっており、その上に教授が「学科の上司」として存在していた時期がない。良くも悪くも一人で自由に研究だけをさせてもらってきた。
このように、私の職業は、世間一般にはわかりにくいタイプの「教授」なのである。一生の間に、複数の機関に所属したにもかかわらず、研究所にしか勤めたことがない教員というのは、特に人文系であれば、かなり珍しいだろう。そして、私の年齢やこの先の職場の可能な選択肢を考えれば、おそらく私はこのまま「学部で教えたことのない教授」のまま、職業人生を終えることになりそうであることが、ほぼ確実な未来として見えてきた。
これは幸運なことに見えるかもしれない。私自身が、かつて若い頃に描いた、根拠のさほどない勝手な将来のキャリアへの見通しも、今となっては思い出せないが、おそらくこのような、自由に、自分のめざす研究を進める、というものだったに違いない。その場所を確保するための過程で経験した障害や摩擦や、それを乗り越えるための闘争を、ここで記すことはしないが、いずれにせよかつて思い描いていたであろう理想的な研究環境に近いものを、現状では、期間を限定して、確保できている。何よりも、上司も部下もいない自由さを、十分に満喫してきた。私にとってそれは、孤独と拠り所のなさと不安定さをはるかに超える価値を持っていた。
4 水面下での足掻き
しかしこの半年に進めてきたことは、この自由をかなりの部分捨てる結果をもたらす組織構築である。組織と言っても、官庁や上場企業の大組織ではもちろんない。研究室で直接雇用する人員としては10名ほどの、小所帯の組織を立ち上げる。しかし通常は人文系の研究室は極小である。教授・准教授・助教といった職名のいずれかを持つ数名で構成され、その予算規模は、研究のために機動的に用いられるのは年間に数十万円から、せいぜいが200万円程度である。これでは雇用は不可能である。研究者が膨大な庶務を抱え込んでその勤務時間の大半を費やすと共に、次世代の研究者の安定雇用による育成が進まない。
この制約を乗り越え、若手・中堅の人員の常勤雇用を一定数確保し、たとえ3年間といった限定された期間であっても、生活の安定と、整備された研究環境を提供して、その先につなげていく機会をもたらす。そのための予算の獲得を、企業や官庁への個別の拠出依頼、あるいは競争的研究費の公募への応募という形で前年度に準備してきたが、これらがまとめて、大きめのものでは三つ、そのほか小さなものも含めれば五つほど、次々と新年度開始の前後に舞い込んできた。コロナ禍による非常時、という状況が、前例のあまりない提案の受け入れ・採択を間接的に後押ししたのかもしれない。あるいは単に私が、自分一人のことだけではなく他人を、そして次世代の育成に責任を負わなければならないとみなされる段階に達した、つまり歳を取ったというだけのことかもしれないが。
細々と単独で運営していた研究室に、突如として多くの予算が舞い込むのと同時期に、コロナ禍は刻一刻と深刻化していった。私としてはこの間にどう過ごしたのかの記憶が曖昧である。コロナ問題の世界的な深刻化を不安に満ちながら見守る記憶と、年度末にかけて相次いで舞い込む大型予算の採択通知を身震いしながら受け取って準備に駆け出した記憶との間の、整合的な接合がない。それらは全く同じ時期に生じていたはずであるが。
所属大学が全学組織で対応を迫られ、新学期の新たなかたちでの運営の試行錯誤が高速で進められていくのを、「友軍」的な附置研究所教員として見守り、受動的に参加しながら、同時に、あたかも「中小企業のオヤジ」になったかのような、人文系の研究室としてはおそらく前例がほとんどない破格の規模の予算の受け入れと、人員の雇用、組織立ち上げを進めていった。それらの作業は、コロナ禍によって強いられた、教育と研究の全面リモート化と、偶然、時期的に重なることとなった。研究室は、人員の数でも、部屋数と使用面積で、急激に拡大しつつあるが、それを多くはリモートで推進するという奇妙な状況が、半年間続いた。ようやく、組織形成の面では「踊り場」というべき時期に達したところである。
研究費が増えて嬉しい、という感覚は、実際に入ってくると、それほどない。そもそも研究費はある程度以上の額になると、自分のために使える資産というよりは、それを人様のためにより有効に使うために日々に頭を絞ることを求められる課題であり、負債のようにすら感じられる時もある。申請時から、これらの予算の使い道は明確で、それは若手・中堅の雇用を増やす、というものであった。コロナ禍によって、この目的への傾斜はいっそう強まった。元来が人件費を重視していた新規の大型予算だけでなく、私自身が従来から確保していた予算についても、その多くの本来の用途であった海外学会・国際会議への渡航は、早々に実施が困難と見て、費目の切り替え手続きを急ぎ、可能な限り、若手・中堅の雇用の人件費に付け替えた。近頃の大学の雇用条件はそれほど良くない。つまり、雇う側から言えば、少額の予算でも、寄せ集めれば、かなりの数の研究者を雇用できてしまう。「質の悪い雇用」はそれ自体は良いことではないが、そもそもポストがなく大学の研究環境へのアクセスを阻害されている研究者たちに、ささやかな規模でも常勤のポストを生み出し、地位と環境を一時的にも整備すれば、その先に進んでいけるかもしれない。何よりも、コロナによって悪化していく経済環境の中で困窮することを避けるための、一時の避難場所は確保できるかもしれない。
5 いつの日か立ち現れる繋がり
このような「大義」を実現するためには、いくら拡大したとは言え、研究室の中の人的資源だけでは到底足りない。大規模に研究会を組織し、総計50名ほどの、他大学・研究機関に所属する第一線の研究者に参加を依頼し、適宜関与してもらう。これはほとんど一方的なお願いである。それらの研究者から言えば、私の研究室で若手・中堅に場を与えるために協力する義務も義理もない。私の研究室で組織するプロジェクトが、それらの研究者にとって関心を持てるもの、利益のあるもの、期待の持てるものであり続けなければ、継続的な協力は得られないだろう。日々にプロジェクトのコンセプトと実施体制を考え続け、策を練り、手を動かし続ける日々が続く。
これらの研究事業を組織し運営・実施する過程で、いくつかの海外の大学・研究機関とは密接なやりとりを行っていった。コロナ禍という世界共通の非常事態に、大学と研究機関という同様の立場で直面したことによる、ある種の「同志」としての意識は、直接対面することのできない環境下でも、共有できていたと思う。感染状況は国によって異なるが、私が重点を置く中東地域では、イランやトルコ、UAE、そしてイスラエルのように、かなり深刻な影響が、長期にわたって出ており、収束の見通しは立っていない。これは私にとって現地調査や国際会議といった事業展開を著しく困難にするものであると共に、特殊な状況下での事業の継続を協力しながら行っていくパートナーシップを醸成する機会ともなったように思われる。
コロナ禍が明けた時に、あるいはコロナによる制約が本当に常態化し恒久化した世界において、国内で水面下で進めてきた組織形成と、国際的に結んできた紐帯がどのように現れてくるか。おそらく見えないところで熾烈な競争が繰り広げられている。ここで中国の大学・研究機関とどう関係を取り結ぶか、これはいっそう見えないところで、複雑に「組み手」が争われている。これらについて、次回にも少し記してみよう。