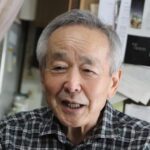歴史的に一番うまい佛師の集団をめざす
──技術に価値があると。
松本 大佛をつくるにしても、截きり金かねなど彩色もうちの職人は歴史上で一番上手い技術をめざしています。職人の意地ですね。文字にすると生意気と取られるかもしれませんが、僕は先人たちに何も負けてはならないと思っているんです。
運慶と快慶は僕らの業界にとってもスーパースターで尊敬していますが、いつまでも彼らに現代の佛師が負けている、とかあってはならないし、彼らを超えないと失礼やし恥やと思うんです。僕らは彼らの作品を見て学んで、それを超える作品をつくれる機会と、いい道具がいくらでもある立場にあります。慶派の流れを汲んだ工房ですが、そういう意味では彼らはライバルです。だから、僕らがめざすのは歴史的に一番うまい佛師の集団であることなんです。
それは現代だけじゃなくて、過去、未来の中でも一番いいものをつくりたい。我々の命がなくなっても「平成、令和にめちゃめちゃすごいやつがおったんやな。こんなん人間の手では誰もつくれへんぞ」と、未来人たちも一目おくようなものをつくりたい。
やっぱり物づくりって、自分に自信を持って物をつくってないと世に出せないと思うんですよ。もし、自分が他よりも下手と思っているんだったら、何か注文してきはった人がいても「自分よりあっちの人にお願いしちゃったらどうですか」って思うので、胸張れないじゃないですか。それって物をつくる人にとってはプライドが許さないんですよね。そういう物づくりの高い信念が、やっぱり僕は強くて、なめられてたまるかと思ってる。
だから、うちよりいい作品をつくれる人がいはるんやったらお願いしたいですけど、うちがやったほうが絶対いい佛像を納められる自信がありますから、どんなに小さい仕事でもやりたいんです。それを、商売人とか言われたら本当に腹が立ちます。お金を求めてるんじゃなくて、未来永劫そこにお祀りされて人の祈りを受け止める佛像は、いいもんが納められていないとあかん。その思いに尽きます。そこについては貪欲なのかもわかんないです。
我々の作品を好みで嫌いと言われるのは仕方ないです。だってどんなに美人な俳優さんでも好みでない、とかありますよね。だけど「下手やな」と言われるのだけは絶対に認められない。これだけは絶対に言わせません。

──いい技術を持つには?
松本 例えば、一人の職人の50年分の仕事量は、50人の職人がいるうちの工房では1年分です。素晴らしい技術を持った工房でつくっていくことで、一人では経験できない数の佛像彫刻ができます。それと、やっぱり最初に言った、受け継ぎ方の原理が松本工房の進化に繋がっているんです。松本明慶が産みの苦しみで築き上げてきた技術を僕が一生懸命に受け継いで、そこから3代目はすごい進化の度合いで仕事をしてきている。父親が25歳だった時より僕が25歳の時のほうがすごい技術を持っていたし、最近は3代目であるうちの息子が一番すごいんじゃないかと気づいたんです。25歳の史上最年少で大佛師を大本山から認許されましたんで。
僕は、死ぬまで現役をしていようとは思っていないんです。上がいると伸び切らない技術や、やりにくい部分は最終的に出てきます。自分よりも心技体で超えた、と思う人がいる場合は、その人が先頭に立ったほうがいい。引き際を見て僕は3代目に譲ろうと思っています。そこは父親とは違うところですね。
約400年ぶりに納めた新たな佛像
──表現に関してお伺いします。古くからある佛像から現在デザインが変化している部分はあるのでしょうか?
松本 不動明王さまや観音さま、みなそれぞれ佛像の形には決まりがあります。例えば不動明王さまやったら、こんな髪型でこれとあれを持ってこれを着ていないといけないとか。決まりごとの範囲内で作家は自分の理想的な顔はこれですとか、プロポーションのバランスはこれがいいとか、自由にはできます。でも決まりごとから外れてしまうと、もうお不動さまとか観音さまと呼べなくなってくるんですよ。
滋賀県に西国三十三箇所第十三番札所の大本山石山寺さまの依頼でつくった弥勒菩薩さまは、蓮華の下に特別に石をあしらったデザインにしています。石山寺さまは石の上に国宝のお堂が建っているので特別につくったデザインです。
弥勒菩薩さまは未来佛さまといって、お釈迦さまが入滅されてから56億7千万年後に世に現れて世界を救ってくれはる佛像なんですね。この56億7千万っていう数字にかけて、光背に567体の化け佛ぶつ(佛像の頭上や光背に置かれている小さな仏像、または佛が衆生を救うために別の姿で現れること)を取り付けたのも特別なもんです。
ここの国宝の本堂の中に新しい佛像が入られたのは400何年ぶりだそうで。そういう歴史の巡り合わせの中に僕らが生きていて、彫らせてもらいました。そのおかげで、石山寺さまからも大佛師の御門をもらってます。石山寺さまがこれまでに大佛師を誰かに認許したっていう記述はないそうなので、僕ら親子3代が初めてになります。
──佛像は今も変化をし続けているんですね。
松本 うちの場合は依頼を受けてつくる他に、自由な発想でつくることもあります。
「ほっぺた撫でてみたい、触ってみたい」っていう「触欲」が人間にはあると思います。そんな触りたくなるような佛像として、オリジナルでつくったのがわらべ地蔵さんです。そもそもは新潟中越地震のときに山古志村で倒木してしまった杉の木で「何か市民の心のよりどころになるものを──」って言われて寄贈したものです。避難所でたくさんの被災者の方々に撫でてもらっていました。こういったものは今までの佛像では存在しなかった作品ですが、その後、佛像のジャンルのように定着してきました。