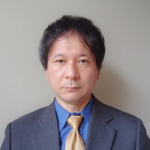2025年7月号「対話」
社会に出るタイミングで就職難に見舞われた「就職氷河期世代」。
氷河期世代の不遇は様々なかたちで語られてきたが、苦境にいるのはこの世代だけなのか? また、苦境にいる人たちに社会はどのような手当てをすべきなのだろうか。
東京大学社会科学研究所教授 立命館大学産業社会学部教授
近藤絢子 筒井淳也
こんどうあやこ:1979年生まれ。東京大学経済学部卒、コロンビア大学大学院博士課程(経済学)修了。Ph.D. 大阪大学講師、法政大学准教授、横浜国立大学准教授。東京大学社会科学研究所准教授などを経て2020年より現職。専門は労働経済学。著書に『就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差』、共著に『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』『日本の労働市場』、編著に『世の中を知る、考える、変えていく』など。
つついじゅんや:1970年生まれ。一橋大学社会学部卒業、同大学院社会学研究科修士課程修了、同博士課程中退。博士(社会学)。光陵女子短期大学国際教養学科専任講師、名古屋商科大学総合経営学部助教授などを経て2014年から現職。専門は社会学。著書に『人はなぜ結婚するのか 性愛・親子の変遷からパートナーシップまで』『仕事と家族 - 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』『未婚と少子化 この国で子どもを産みにくい理由』など。
記述統計と因果推論
近藤 本日は就職氷河期世代をテーマに議論していきたいと思います。議論を始める前に、就職氷河期世代とはどの時代を指すのか具体的にしておきます。私は2019年の「就職氷河期世代支援プログラム」関連の公文書の定義に倣って、1993年から2004年に高校や大学などを卒業した世代を就職氷河期世代と呼んでいます。これをさらに、前期(1993年卒~1998年卒)と後期(1999年卒~2004年卒)に分けています。今回の「対話」でもこの定義を用いていきたいと思います。
最初に簡単な自己紹介をさせていただくと、私は労働経済学を専門にしています。昨年10月に『就職氷河期世代──データで読み解く所得・家族形成・格差』を発表しました。この本は記述統計、つまり時系列グラフやクロス表集計など、シンプルな方法でデータの概要や特徴を記述・要約したうえで論じる構成になっていますが、普段はより複雑な計量モデルを組んで、因果推論の手法を使うことで個々の政策の効果を研究しています。
筒井 私の専門は家族社会学で、人口の変遷や出生率などのデータを使いながら、日本の家庭や社会の変化について研究しています。6月に『人はなぜ結婚するのか──性愛・親子の変遷からパートナーシップまで』という結婚のあり方をテーマにした著作が刊行されたところですが、未婚化や晩婚化、少子化、パートナーシップの多様化などの現象などについても研究しています。
いま記述統計と因果推論という専門的な言葉が出ましたが、この二つは研究のスタイルがだいぶ違いますよね。因果推論は、政策の影響をつぶさに見ていきます。例えば、子どもを増やすことを目的に打たれた政策が出生率にどのような影響があったのか、その効果を具体的に検討する研究です。「どうして少子化したのか?」という疑問に答える研究ではないので、社会の変化を説明するのには向いていないところがある。そのため世間一般では記述統計的な研究のほうが話題になったりしますが、私は因果推論にもっと陽が当たるべきだと感じています。近藤先生は記述統計と因果推論の両方を使い分けている印象があって、労働経済学の研究者としてはめずらしいタイプだと感じています。
近藤 私の研究のメインは因果推論で、普段は政策介入の効果をミクロに見ています。記述統計的なアプローチは、個人的な興味から一般向けにコラムなどを書くときにやっている感じですね。所属している東京大学社会科学研究所の同僚には社会学者たちもいますが、彼らのほうが視野が広いと感じています。最近の労働経済学の世界は、どうも蛸壺化してしまっているところがあります。私もその一人になっているのかもしれませんが、分析できる対象しか分析しない傾向があります。
筒井 社会学の分野では因果推論を積み重ねても社会を説明できないのではないか、という立場が根強くあったと思います。ただ最近では社会学でも因果推論をやるべきだという雰囲気になってきています。一般の方には専門的に感じられるでしょうが、この「対話」を読み進めていかれる際にも、このスタイルの違いを頭の片隅に置いていただければと思います。
苦しんでいる層は氷河期世代に限ったことではない
筒井 冒頭から少し脱線しましたが、本題に入りたいと思います。近藤先生の『就職氷河期世代』をあらためて読みましたが、この本にはいくつかの大きなメッセージがありますよね。その一つは、学校を終えて就職する段階で望むような仕事に就けず、その後十分なキャリア形成ができずに低賃金に苦しんでいる層は就職氷河期世代に限ったことではないというご指摘です。氷河期世代以降もリーマンショックや東日本大震災などによる不況の影響で、若年者雇用の苦境は続き、決して改善したわけではないと。
近藤 図表1から3の統計データからわかるように、今の30代も決して恵まれた雇用状況にあったとは言えません。図表4は、初職が正規雇用だった割合と非正規だった割合を示したものですが、むしろ氷河期世代以降で悪化しています。
筒井 氷河期世代は社会的にもインパクトが強かったので、私もこの世代が最も厳しい状況にあるのだろうと漠然と思い込んでいたところがありました。こうしてデータをあらためて見ると、とても「改善した」と言える状況ではありませんね。
就職氷河期世代という言葉が広く使われたことで、就職難はこの世代の特徴であると、認識が固定してしまったのかもしれません。実際はこの世代に限った景気循環による影響ではなく、構造的な変化が起きていた可能性がある。
近藤 おっしゃる通りです。2016年に、連合総研が行った氷河期世代の実態を把握するためのプロジェクトに参加したことがありました。その際に、確かに氷河期世代はそれより上の世代と比較すると著しく状況が悪化していますが、下の世代とはあまり差がないという事実が浮かび上がってきました。
その少し後の2019年に政府は氷河期世代対策を打ち出しましたが、対象が「2004年までに卒業した人たち」に限られていました。氷河期世代以降も苦境が続いていることは明らかですから、そこで区切る必要はないはずです。『就職氷河期世代』を書こうと考えたきっかけも、その事実を知って欲しいという思いがありました。
どういうわけか、世代で輪切りにしたがる人が多い傾向があります。しかし支援するのであれば特定の年齢層に限定するのではなくて、窮地に陥っている人たちに狙いを定めて対策するほうが望ましいはずです。氷河期世代には困っている人たちが多いのですが、それ以降の世代にも支援が必要な人たちはいるわけです。
筒井 氷河期世代でも成功している人たちは当然いるし、それ以降の世代でも厳しい人たちもいますよね。
近藤 そこには濃淡があるので、支援対象を世代で区切るのはおかしいはずです。
本を出して取材を受けるようになってから気が付いたのですが、世間が思っている氷河期世代と一番景気が悪かった時代とは少しズレがあると感じています。世間が考えている就職氷河期は前期にあたる、内定率などが下がっていく途中にいた年代の人たちです。就職氷河期という言葉が流行ったのは、その世代が就活していたときでしたから、社会に強いインパクトを残したのだと思います。けれども、最も厳しい状況にあったのは氷河期後期の人たちです。
筒井 学校を卒業して就職するタイミングで、雇用環境が悪かった人たちのことを就職氷河期世代と呼んでいるのでしょうが、高卒と大卒とでは4年間ズレますよね。おそらく氷河期前期というときは高卒基準では75年から80年くらいに生まれた人たちで、大卒になるとそれよりも前になる。我々は就職氷河期と聞くと70年代前半生まれを思い浮かべるんですよね。
近藤 けれども、それは大卒の人だけです。
筒井 ショックが大きかったのは、むしろ非大卒のほうだったのかなという気がします。日本社会を研究しているハーバード大学のメアリー・C・ブリントン教授(社会学)が書いた『失われた場を探して──ロストジェネレーションの社会学』では、高卒、特に普通科の非進学校を卒業した人たちのほうがより厳しい状況だったと紹介されています。
近藤 高校卒──統計上では専門学校卒も含めています──は、今でも非正規雇用の割合が高いままで、もうずっと改善していません。
筒井 このあたりはメディアの認識がズレていたり、解像度が粗かったりする印象があります。ズレたまま今に至っているところがあるのかもしれない。
近藤 よく氷河期世代のあとに一瞬、雇用が回復したと言われています。確かに大卒市場は求人倍率が少し上がっていますが、それは大卒に限った話です。あたかも全体的に良くなって、氷河期は終わったかのような雰囲気になっていました。実際はその後もリーマンショックの影響などで雇用環境は悪化していましたが、そこは忘れ去られている印象があります。
筒井 20代の非正規雇用の比率が明らかに悪化したのは氷河期世代からであることは間違いないのだけど、後ろの世代でもそれが継続していた。
近藤 氷河期世代が始まりだったことは確かですね。