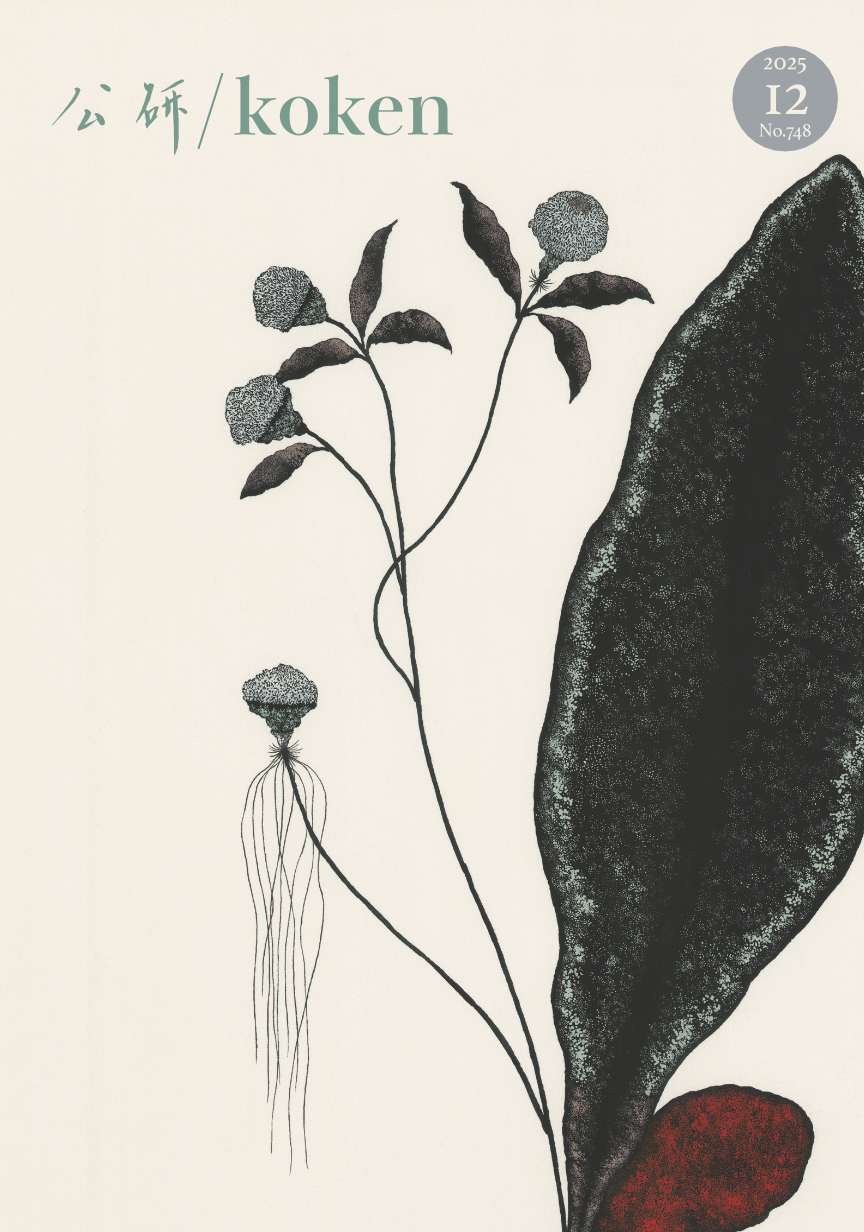注目されるインフレ抑制法の見直し
杉山 2022年にバイデン政権下で成立したインフレ抑制法(IRA)が今後どうなるのかも注目されています。名前からは想像しにくいですが、インフレ抑制法とは、大まかには脱炭素への投資を減税することで経済成長と気候変動対策を推進することを目的とする法律です。かつてないほど大胆かつ大規模なクリーンエネルギーへの減税措置を含んでおり、アメリカの気候変動対策の方向性を明確にしたものです。こここそトランプの攻撃になりそうですが、現状はどうでしょうか。
上野 トランプ大統領は選挙中からインフレ抑制法の減税を「新たなグリーン詐欺」と呼んで強く批判し、廃止を公約として掲げていたほどです。
本日は5月27日ですが、実は先週、インフレ抑制法の見直しに向けた動きがありました。その背景には、トランプ大統領が実現を熱望する所得税などの大規模減税があります。もともと、1期目の2017年に「トランプ減税」と呼ばれる、所得税や法人税の減税法を成立させていて、そのうち所得税の減税措置は今年末で期限切れを迎えます。トランプ大統領はこれを延長することに加え、チップへの非課税措置なども打ち出しています。
では、その減税分の財源をどうするのか。目をつけているのが、インフレ抑制法による脱炭素支援の撤回なのです。
杉山 なるほど。脱炭素支援を削って、減税財源に充てようとしているわけですね。
上野 はい。実際5月22日に、連邦議会下院では減税パッケージ法案の「One Big Beautiful Bill Act」が可決されました。ここには、インフレ抑制法の減税措置の「一部」撤回が盛り込まれています。法案は現在、上院で審議されています。
再エネと電気自動車がとにかく嫌いな共和党
杉山 すべての減税が撤廃されるのではなく、一部なのですね。
上野 そうなのです。興味深いことに、一律廃止ではなく、「延長するもの」「維持されるもの」「即時撤回に近いもの」というようにまちまちです。これは共和党の技術の好みによって決められています。
まず、延長するものがバイオ燃料の生産に関する減税です。2027年末までの減税を、31年末まで4年延ばしています。次に維持されるものは、CCS(炭素回収・貯留)に関する減税(45Q)です。32年までに着工したCCS施設が減税の対象になります。また、既存の原子力発電所に対する税制優遇措置は、適用期限を32年末から31年末へと1年前倒しをしていますが、小幅な短縮に留まっているので、維持と言っていいでしょう。
杉山 バイオ燃料もCCSも脱炭素・低炭素技術ですが、なぜこれらはあまり強く批判されないのでしょうか?
上野 この背景には、地域的な事情と政治的な力関係があります。バイオ燃料の一種であるバイオエタノールは、共和党が強いネブラスカ州やアイオワ州で盛んに生産されています。これらの州は、面積の大半が農地で、トウモロコシの栽培が盛んです。そのトウモロコシが、燃料用のバイオエタノールの原料として使われているのです。そうした事情から、地元の共和党議員たちはバイオ燃料産業を守るために、減税などの政策支援を強く求めています。
実はここにCCSが絡んできます。一般的なCCSでは、発電所などから出てくる空気と混ざったCO2を分離・回収するのにコストがかかります。しかし、バイオエタノールの製造過程で出るCO2はタンク内での発酵によって発生するため、濃度がもともと高く、簡単に、しかも低コストで回収できるのです。
にもかかわらず、「CCSは高コスト」という前提で減税制度が設計されています。その結果、バイオエタノールに由来するCO2を回収して地中に隔離すれば、事業者には大きな儲けが出る仕組みになっているのです。
もともとCCSは、化石燃料を使いながらも脱炭素を実現するために石油・ガス業界が推進してきた技術でしたが、そこに農業ロビーが加わったことで、共和党内では非常に強い政治的支持を得るようになりました。つまり、共和党内の政治力学が、バイオ燃料とCCSの減税政策を支えているというわけです。
杉山 なるほど。まさに共和党の「好み」なのですね。
上野 そうですね。他方で即時撤回に近いのが、電気自動車1台あたりへの最大7500ドルの減税です。名目上は26年末での廃止ですが、実質的には25年末が期限となりそうです。というのも、26年は累計販売台数20万台を超えるメーカーは減税の対象外となるためです。大手メーカーはすでに累積20万台以上の電気自動車を売っていますので、結果として25年末でほぼ使えなくなります。
また、再生可能エネルギーへの減税政策である、ITC (Investment Tax Credit:投資税額控除) とPTC(Production Tax Credit:生産税額控除)も事実上の即時撤回です。法案成立から60日後までに着工した再エネ設備は対象になりますが、あまりの期間の短さに即時撤回と言ってよいでしょう。ただ、上院での法案審議で、もう少し期限が延びるかもしれません。
杉山 同じ脱炭素でも原子力と再エネではここまで扱いが違うのですね。
上野 共和党はとにかく再エネと電気自動車が嫌いなようです。他方、原子力は超党派的に支持されています。ただ、民主党は原子力の脱炭素の側面を支持していますが、共和党は必ずしもそうではありません。様々な支持理由がありますが、たとえばトランプ大統領が5月23日に署名した大統領令では、AIデータセンターや軍事施設を支える安定電源としての価値が強調されています。
杉山 これらの政策の転換は、日本への影響はどうですか?
上野 アメリカの気候政策は、政権が変わるたびに右へ左へと揺れ動きます。そのたびに世界の気候変動対策が振り回されるのは正直なところ迷惑でもあるのですが、今回のインフレ抑制法の見直しに関して言えば、日本にとっては、案外悪くない話も含まれています。
というのも、日本は今、アンモニア混焼の火力発電を行うことで、少しでもCO2の排出を減らそうとしています。このアンモニアの一部はアメリカから輸入する計画で、天然ガスからアンモニアの原料となる水素を取り出して、出てきたCO2は地下に閉じ込めるというCCS技術を使います。ここでポイントになるのが、アメリカのCCSに対する減税措置。これが続けば、日本がアメリカからアンモニアを安定して輸入するための追い風になります。
同じく、日本の都市ガス業界が進めている合成メタンも、CO2を回収して水素とくっつけてつくられるので、これにもCCS減税が使える可能性があります。バイオ燃料をつくる過程で出る濃いCO2をうまく利用できるので、日本としてはこれも助かるわけです。
さらに自動車分野でも、日本では電気自動車一本で行くのではなく、バイオ燃料の導入も進めようという動きがあります。これもアメリカからの輸入を一部見込んでいるため、もしバイオ燃料生産に対する減税が下院法案通りに2027年から31年まで延長されれば、日本にもメリットがあります。
つまり、トランプが気候政策を見直すことでアメリカの排出削減にはブレーキがかかるかもしれませんが、日本にとって重要なクリーン燃料輸入には、意外と追い風が続くかもしれない。そういう意味では、少し皮肉ですが、日本の脱炭素にとってはプラスになる部分も残されているのです。
中国からのデカップリングとデリスキング
上野 インフレ抑制法の見直しで注目すべき点が、多くの減税に「禁止外国組織等」に関する制約を付けようとしている点です。下院を通過した法案では、懸念のある国や組織が一定の関与をする場合、減税を適用できないとされています。たとえば、再エネ発電では、中国企業が生産工程に関与する太陽光パネルを使う場合、減税を適用できないように見えます。
アメリカ産のパネルは価格が安いわけでもありませんし、物によっては中国産より10倍近く値段がすると言われています。中国産のパネルを使う場合には減税不可となると、アメリカの太陽光普及は一旦減速もあり得るのかと思います。それとも技術進化によって、さらなるコストダウンがなされるのか。中国製が完全に排除される場合、アメリカで太陽光発電事業は成り立つのか。ここはいかがでしょうか?
杉山 成り立たないと思いますね。よく聞く話ですが太陽光パネルの世界シェアで中国は断トツです。日本はかつて50%を誇っていましたが、今は1%未満です。
前から中国製の太陽光パネルや太陽電池モジュールには関税が掛かっていました。しかし、中国企業は関税を避けるため東南アジアで少し加工して「東南アジア産」としてアメリカに出していたのですが、アメリカはそれを迂回輸出と問題視。バイデン政権時代から検討を重ね、最近、関税を最大3500%超まで引き上げることになりました。ここに加えて、インフレ抑制法の減税の対象外になると、相当な減速になります。
上野 そうですね。禁止外国組織等に関する制約が、経済安全保障上の理由なのか、アメリカ国内で化石燃料を高めるためなのか、単なる保護主義なのか、ここの動機は様々だと思います。
最近でも、中国製の太陽光発電設備に通信機器が付けられていて、遠隔操作で大規模停電を引き起こす可能性があるのではないかとの危険が指摘されました。そうなると、再エネの進展は、ただコストを安くすればいいわけにはいかなくなります。
杉山 そこは考えなくてはいけない点です。太陽光パネルもただのパネルではなく、スマートインバーターなどが付属してあり、外部と繋がることができる。つまり、電力インフラの一部として、セキュリティ上の懸念があるのです。これは単なるモノの貿易とは違うので、経済安全保障の観点から慎重になるのも当然かなと。
ただ、パネルはパネルなので、それだけなら何も悪さはしませんよね。そうなると、国際分業が理想的なやり方だと思うのです。しかし、今の地政学的状況では、それが一番難しいのも確かです。
上野 デカップリングとデリスキングの概念の違いですね。中国との経済関係を完全に切り離すのがデカップリング。完全な切り離しではなく、中国が経済的な依存関係を武器として使うことができない程度に依存度を下げようというのがデリスキングですね。その下げた分を埋めるには、自国生産だけでなく、友好国間でサプライチェーンを築く「フレンドショアリング」というやり方があります。
先ほど言ったように停電を起こすなど甚大な被害が出るものはデカップリングするしかありませんが、それ以外はデリスキングとするのがアメリカを含む多くの国々の基本路線だと思っていました。しかし、第二次トランプ政権は、サプライチェーン強靭化のための横の連携を壊しかねない関税政策を友好国に対しても展開しています。これでは、フレンドショアリングどころではありません。
さらに、このトランプ関税によって中国が「不公正なのはアメリカだ」と強く主張し始めたことで、脱中国依存そのものの正当性に疑問を持つ声も出てきて、動きが少し鈍くなっている印象です。今後、中国の安い製品への依存が再び強まるのか、それとも別のかたちで国際分業を進めるのか、方向性が見えにくくなっています。デリスキングを進めるには、中国に代わる選択肢の確保に向けた国際協調が欠かせませんが、トランプ政権以降、アメリカの自国優先主義がそれを難しくしているのです。