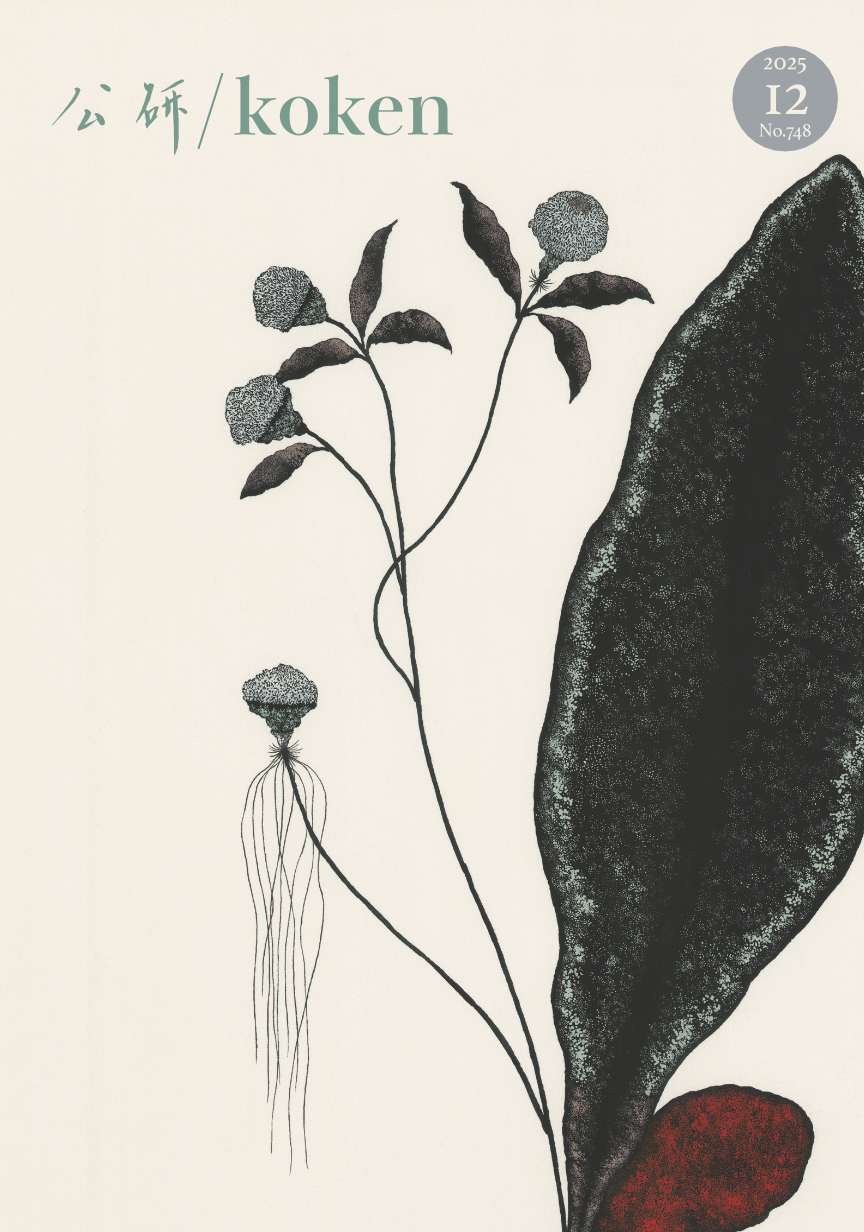気候変動の最後のブレーキ 太陽放射改変
上野 気候変動対策における最終的な手段として、炭素除去について議論してきました。それに加えてもう一つ重要な柱となるのが、太陽放射改変(SRM:Solar Radiation Modification)です。簡単に言えば、地球に届く太陽光の一部を反射・遮蔽することで、地球の温度上昇を抑えようとする技術です。日本でこの分野において最も専門性高く、技術動向を研究しているのは杉山さんですが、この技術はどこまで進んでいるのでしょうか。
杉山 まず、太陽放射改変にも様々なやり方があります。その中で最も研究が進んでいる方法が、 成層圏エアロゾル注入というものです。これは火山の大噴火によって地球の温度が下がる仕組みと同じです。
大規模な火山噴火が起きると、水蒸気や二酸化硫黄などのガスが大量に噴き出し、それらが成層圏にまで到達します。これらのガスは大気中で化学反応を起こし、酸化されて硫酸のミスト、つまり硫酸塩エアロゾルとなって地球全体に拡散していきます。この硫酸塩エアロゾルは、太陽光を宇宙へ反射する性質があり、その結果として地表に届く日射量が減少し、地球全体の気温が低下するのです。
実際に、1991年にフィリピンのルソン島でピナツボ火山が大噴火を起こした際には、気温が徐々に下がり、約1年半後には世界の平均気温が最大で0・5度ほど低下したという例があります。
自然の大規模噴火とは異なる部分も多々ありますが、これを人工的に再現し気温を下げるというのが成層圏エアロゾル注入です。この技術の良い点は、技術的に非常にシンプルで何よりコストが安い点にあります。若干楽観的な見積もりですが、年間1兆円の規模があればできるという指摘もあります。炭素除去のDACが年間で数十兆から100兆円かかると言われているので、その差は明らかです。
上野 1兆円でどのくらい温度が下がるのですか?
杉山 約0・5度でしょうか。
上野 けっこう下がりますね。2度から1・5度まで年間1兆円で下げられるのですね。
杉山 そうですね。先ほど少し触れましたが、先週、太陽放射改変に特化した国際会議に参加してきました。そこで感じたのが、少しずつですが実用化に向けて進んでいるということです。エアロゾルの散布にはどんな飛行機を使うのか、何度の経度緯度に入れたらいいのかなど、かなり細かな部分まで議論されていました。やはり、昨年の平均気温上昇が1・6度に達してしまったこともあり、太陽放射改変を本気で考えなくてはならないという真剣な雰囲気を感じました。
また、個人的に興味深かったのは、アメリカのプレゼンスの大きさです。アメリカの著名な研究者の方々が参加しているのはもちろん、政策に関する方も参加していたので、その真剣さを感じました。
人工的な気候操作に副作用はないのか?
上野 太陽放射改変について、杉山さんにお聞きしたいのはその意図せざる影響についてです。15年ほど前、杉山さんとお話した際に、「気温は確実に下がるが、地域ごとの気象パターンにどう影響するのかは、まだよくわかっていない」と言っていたのを覚えています。たとえば、日本で梅雨がなくなり稲作に大きな打撃を与えるといった、予測の難しいリスクがあると。その後の15年で、こうした点の研究は進展してきたのでしょうか?
杉山 一言で言うと、ちゃんと医者の言うことを聞いて使えば大丈夫、という感じでしょうか。要は、使い方を間違えなければ、大きな問題にはならないということです。
成層圏エアロゾル注入は、確実に地球の平均気温を下げる効果があります。しかし、それに伴う「副作用」、たとえば降水パターンの変化や農業への影響は、投入量に比例して増えるのではなく、非線形に、つまり時に急激に大きくなる可能性があると考えられています。たとえば大量に冷やそうとすれば、日本の梅雨やインドのモンスーンがガラリと変わってしまうシミュレーションも数多く存在します。
でも逆に言えば、投入量を抑えれば、そうした副作用もかなり抑えられる。初期のシミュレーションでは2度、4度といった大規模な冷却が想定され、副作用も大きく出ていましたが、現在では0・5度程度の抑制的な利用であれば、かなりリスクを減らすことができることがわかっています。
上野 やはり0・5度というのは、けっこう大きな効果ですね。排出削減の努力で2度を少し超えるくらいに抑えられれば、太陽放射改変で2度やそれより低い水準に下げられるということになります。
杉山 そうですね。0・5度くらいが、安全に下げられる温度の上限だと考えていますが、実際に0・5度でも気候変動による被害の緩和には十分貢献できます。他方で、たとえば、3度から2度へ下げるような使い方をすると副作用の懸念が強まりますので、まずは排出削減で温度上昇を抑えたうえで、成層圏エアロゾル注入を補完的に用いることが基本です。言い換えれば、排出削減の先送りが正当化されるわけではないということです。
もう一つ注意すべき点は、成層圏エアロゾル注入は、注入を止めた瞬間に気温が急上昇する点です。これを終端問題(termination shock)と呼びます。たとえば、仮に2度冷やす規模でエアロゾルを投入していて、ある日突然止めてしまうとすると、その2度分が急激に跳ね返ってきます。そんな事態になれば、世界に壊滅的な影響が出る可能性があるのです。
しかし、最近は投入量やタイミング、場所をきめ細かく制御する工学的な知見も進んできました。たとえば、季節ごとに調整したり、特定の地域に限定して投入したりすれば、冷却効果だけでなく、降水量やモンスーンなどへの副作用も抑制的にコントロールできるようになっています。つまり、「太陽放射改変=危険」と決めつけるのではなく、使い方次第で安全に運用できる可能性があるということです。
上野 使い方が大事ということは、どんな技術にも言えることですね。
杉山 そうです。ただ、成層圏エアロゾル注入の本質的な問題は、国際的な協調が成り立つかどうかという点にあります。国際会議で気になったのが、中国からの参加者がほとんどいなかった点です。これは正直不気味に感じました。
もちろん、アメリカ在住でグリーンカードを持っていたり、すでに帰化しているような中国系の研究者は何人かいました。しかし、中国国内の政府や政策に直接アクセスできるような立場の人、つまり中国共産党の意思決定に関与しているような人は、ほとんどいないか、いても完全に政治と断絶したような状態でした。主要国間での信頼関係や意思疎通の経路が確保されていないというのは、非常に大きな懸念材料です。
成層圏エアロゾル注入では国際協調が重要
上野 そこは杉山さんにお聞きしたかったことの一つです。温室効果ガスの排出削減は、日本一国だけで努力してもあまり意味がなくて、世界全体で協調しないと温暖化を抑制できません。ところが、成層圏エアロゾル注入はその逆で、航空技術を持っていて、エアロゾルを撒くことができれば、一国だけでできてしまいます。国際協調なしで実行できる。しかも、その影響は世界全体に及びます。
たとえば、軍事的に強い国で異常気象が頻発して、世論に押されて「もっと冷やせ!」という声が高まり、科学者の想定以上の散布が行われるとします。そして、その副作用が世界の別の場所で出るなんてことになりかねないと。どの時点で注入するかといった基準の国際的な合意ができていないと、意図しないかたちで副作用に晒されるリスクが出てくると思うのです。
杉山 大いにあり得ると思います。そうなると、中国のように意図が読みづらい国との間にコミュニケーションチャネルがないのは危険ですね。そこで隣国の日本の役割も重要になるのではと思います。
上野 その通りですね。そもそも、排出量と温度上昇の対応関係には大きな幅があるので、2度に抑えるつもりで相応の排出削減努力をしても、実際には予想を超えて2度以上になってしまうかもしれない。そうした不確実性が高い以上、成層圏エアロゾル注入のような技術を保険的に用意しておく価値はあります。
さらに言うと、副作用をコントロールしながら使用できるのなら、保険ではなく早々に手を出してしまう国が出てくる可能性もあろうかと。いずれにしても、無謀なかたちで実行されないよう、研究や小規模な実証実験によって副作用の解明を早く進めたほうがよいのでしょう。
ただ、トランプ大統領は気候に関する科学的な研究予算をどんどんカットしていますから、太陽放射改変の研究も進みにくくなるのでしょうか。
杉山 アメリカでも、太陽放射改変への逆風が吹いています。長時間にわたって残留している飛行機雲は意図的に撒かれた有害物質だという「ケムトレイル陰謀論」があるのですが、実はこの陰謀論と関連づけられて、州レベルで太陽放射改変を規制するような法案が通っているのです。ですから、残念ながら政治的に見ると停滞はするのだろうと思います。
気温上昇 限界への危機感
上野 実際に成層圏エアロゾル注入を実行すべきだと人類が判断する時は、温暖化の影響が深刻で、無理やり温度を下げてでも止めねばならないほどかどうか、そこが大事ですよね。温度に基準を置くのはわかりますが、どれほど被害が大きいかも重要です。そこはどう見ていますか?
杉山 結局これは主観的な面が大きいです。科学者たちはプラネタリーバウンダリーズ(人類が地球上で安全に活動できる限界を示す枠組み)や1・5度目標など、ある種の基準を提唱していますが、それも政治的もしくは専門家の主観的側面があり、1・5度と言った人の声を拾ってきたという側面もあります。
新しい提案もたくさんありますが、やっぱり最終的には食料や水の問題が大国を揺るがすほどの被害を引き起こす時が一つの基準、臨界点になるのではないでしょうか。
上野 たとえばアメリカの共和党強硬派が強い地域で気候変動による激しい被害が出て、議会上院もそれで国際協調に傾けば、新たな条約ができるかもしれない。しかしアメリカで大きな被害が出ているということは、世界全体では、もっと深刻な被害が出ているということになりますが…。
杉山 そう考えると、早く影響が出そうなのは中国やインドではないでしょうか。アメリカもハリケーンなどの被害はありますが、資金が削られてもそれなりに研究して適応策を取るでしょう。なので中国やインドのような新興国のほうが耐えられない声が大きくなる気がします。
上野 そうですね。耐えられないという声はむしろ新興国から上がってきそうですね。中東の産油国も悪影響が出やすいかもしれません。
杉山 オーバーシュートの話をしましたが、1・5度、またはそれ以外でも限界を超える感覚を日本でももっと議論すべきだと思います。技術の進展はあるものの、残念ながら私たちは限界を超える危険に近づいているのが現実です。
上野 途中で話題となった去年の1・5度超えは、まだ単年での超過であって、1・5度を超えたかどうかは20年平均で判断するものと理解しています。20年平均での1・5度超えには、まだ距離がありますが、このままのペースだと2030年代のどこかで超えそうです。
杉山 そうですね。年々変動があっても基本的にこの調子で上昇していたら、限界が来るのは当然です。太陽放射改変の発展が気候危機に間に合わない可能性もある。まずはCO2の削減といった基本に立ち返り、同時並行的に太陽放射改変の議論を進めるしかないのだと思うのです。(終)




![「コロナの時代」の 戦略思考[第5回]「殯(もがり)の夏」【池内恵】](https://koken-publication.com/wp-content/uploads/2022/12/池内先生-150x150.png)