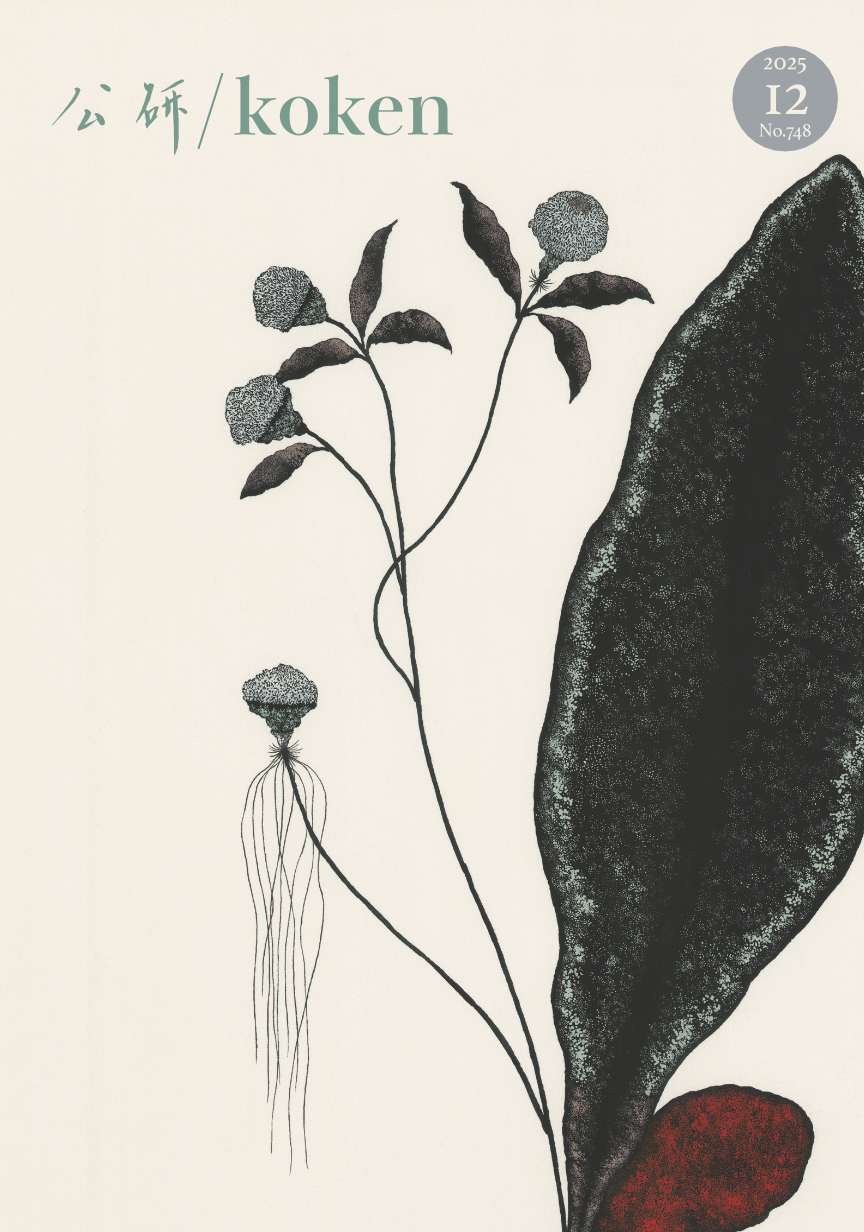トランプ2・0でどれだけ目標から後退するのか?
杉山 バイデン政権は、パリ協定の下で「2030年までに温室効果ガス排出量を2005年比で50~52%削減する」という目標を掲げましたが、第二次トランプ政権の誕生によってここが大きく揺らいでいます。現時点でどの程度その目標から遠ざかってしまっているのか。正確に測るのは難しいとはいえ、どう見ていますか?
上野 目標までの未達幅は広がるばかりです。そもそもバイデン政権下でも、すべての気候変動政策の効果をひっくるめて40%削減に届くかどうかといった水準でした。トランプ2・0でどこまで政策が壊れるかにもよるので、正確な予想は難しいですが、2030年で30%削減にすら届かない可能性もある。
目標未達にさらに拍車をかけているのが、アメリカの電力需要がここ数年で少し増加に転じている点です。もちろん、コロナからの反動もありますが、それだけではない増加が表れている。データセンターもその一因で、15年近く、ほぼ横ばいだった電力需要がここにきて増加し始めているのです。
この需要増に石炭火力の廃止延期で対応することとなれば、その分だけ排出量は増加します。2030年の削減目標や2050年ネットゼロ排出は、実現可能性が遠のいているのが現状です。
杉山 やはり後退は避けられないのですね。アメリカがこのような状況で、多くの人が気になるのが1・5度目標だと思います。この目標は、「地球の平均気温の上昇を産業革命前から1・5度以内に抑えることをめざす国際的な目標」で、2015年のパリ協定で採択されたものです。
上野 そもそもアメリカは1・5度目標も含めてすべてを放棄している状態ですよね。排出シナリオを分析されている杉山さんから見て、排出量の今後の見通しや、地球の平均気温上昇のスピードはどうなるのでしょうか?
杉山 残念ながら1・5度を超えるのは目前だろうと感じています。実は昨年、世界平均気温が、産業革命前から初めて1・5度を超えて1・6度の上昇となりました。1・5度目標はあくまで長期の平均で見るものなので、すぐに達成不可能とは言えませんが、重く受け止めるべき数字です。ただし、排出量は世界全体でまだ減っておらず、このままでは1・5度を超える現実がすぐそこまで来ています。
読者の皆さんには釈迦に説法かもしれませんが、気候変動は「ストックの問題」です。つまり、一度大気に排出された温室効果ガスは消えず留まり続けます。現在の気温上昇も、これまでに人類が排出してきた蓄積によるものです。
よく、1・5度目標を守るために残された排出可能量、いわゆるカーボンバジェット(炭素予算)で語られますが、これが2025年頭の時点で、現在の排出量の4年分しか残っていません。出してよい分が、ものすごいスピードで失われているのは間違いないのです。
上野 国際社会の足並みが乱れている中で、着実に排出量は増えていると。
杉山 そうですね。一方、1・5度という数字に、引っ張られすぎなのも事実です。先週、南アフリカ・ケープタウンで開催された太陽放射改変または太陽ジオエンジニアリングに関する国際会議に参加してきました。アメリカからの参加者が非常に多く、トッド・スターン(元アメリカ気候変動特使)やデイビッド・キース(シカゴ大学教授・気候工学の第一人者)といった著名な人物も出席していました。
そこで、複数のアメリカの専門家が強調していたのが、技術の進歩はすごいという点です。今の技術進展で言うと、1・5度は厳しいが、2度台なら見えてきたのではないかと発言していたのが印象的でした。
しかもそれが、太陽放射改変などに関心のある人たちから出てきたという点は、重く受け止めるべきだと思います。後程お話しできればと思いますが、私は気候変動問題は最終的に技術の問題だと考えています。シェール革命の例のように、一度コストが下がった技術は市場に定着します。再エネや電気自動車も同様で、今のアメリカのように停滞はあっても、技術の進展によって長期的には逆戻りしないはずです。1・5度目標は事実上不可能かもしれません。今は非常に曖昧で見通しが立ちにくい局面とはいえ、パリ協定の2度目標、あるいはそれを少し超える程度に抑える可能性が完全に失われたわけではないのです。
上野 パリ協定には1・5度と並記して2度目標も掲げられていますが、2度を全く超えないかは別にして、その近傍に収まる可能性がトランプ2・0で後退したとしても、技術の進歩によって残っていると。
杉山 残っているというより、2度台はむしろ可能性が増していると考えます。というのも、技術の進歩が本当にすごいんですよ。たとえば再エネに関して、日本では「コストが高い」という話がよく出ますよね。経産省の調達価格等算定委員会の報告書などでも毎年のように言われています。でも、それはあくまで日本のコスト構造の話であって、世界の現実とは少しズレています。
日本のエネルギー業界は、どうしても世界の再エネの風を直接感じにくい構造にあります。それは仕方ない面もあるのですが、だからといって「世界全体でも再エネは高い」と考えるのは少し違います。実際、アメリカで再エネがこれだけ伸びたのは、ITCやPTCといった税控除の政策支援もありますが、何より技術進展でコストが下がったことが大きい。コストさえ下がれば、ちょっとした後押しで導入が一気に進む。そういう地盤ができていると思うのです。
物理的に大気からCO2を取り除く技術
杉山 現在の排出トレンドを踏まえると、1・5度目標は、今後一時的にでも超えてしまう、いわゆるオーバーシュート(目標超過)になる可能性が高まっていると、先ほどお話ししました。このような事態においては、目標を一度超えたとしても、その後できるだけ早く気温上昇を抑制し、1・5度以内に引き戻すことが重要になります。
戻すための手段として、近年注目されているのが二酸化炭素除去(CDR:Carbon Dioxide Removal)または炭素除去と、太陽放射改変(SRM:Solar Radiation Modification)です。
上野 CDRは文字通り大気中からCO2を除去する技術ですね。
杉山 なぜこれで平均気温を下げることができるか。基本的なことですが地球温暖化は、大気中に蓄積されたCO2の累積量によって、引き起こされています。したがって、そのCO2を大気から除去していけば、気温は緩やかに下がっていくことになります。毎年の排出量と除去量が釣り合えば気温の上昇は止まり、除去量が排出量を上回れば気温は次第に下がり始めるという仕組みです。
そのため、たとえ今後1・5度や2度の気温上昇を一時的に超えてしまっても、大気中のCO2を継続的に除去していけば、将来的には気温を再び下げることも可能になると。その方法の一つが炭素除去です。
上野 炭素除去には種類がいくつかありますよね?
杉山 はい。植林もその一種です。1番わかりやすいですね。光合成によって大気中のCO2を吸収します。ただ、植林は森林火災などが起きるとCO2が再放出されるので、永続性に課題があります。
永続的に貯留するには地下に入れることが最適です。そのうちの一つが、装置を使って大気中から濃度0・04%の二酸化炭素を除去して地中に埋める直接空気回収(DAC:Direct Air Capture)です。大阪・関西万博でもDACの実証実験が行われていて、注目度や期待値が高まっています。
上野 物理的に大気からCO2を取り除くと。この技術はアメリカが世界をリードしていると言っていいでしょうか?
杉山 はい。アメリカには直接空気回収を専門にするベンチャー企業が多く存在します。中には科学的にやや怪しい企業もあるのですが…(笑)。ただ、ベンチャーキャピタルからも多くの資金が流れ込んでいて、今後が期待される分野です。やはり熱気が違いますよね。
上野 DACでは実際にどのくらいのCO2を除去できるのですか?
杉山 今の技術的に数ギガトン規模のCO2を除去できるかは難しいです。しかし、そこには及ばずとも、500メガトンの除去でも確かな貢献になります。もし1ギガトン規模になれば、それは日本の年間排出量に匹敵します。そういう規模をめざしていけたらいいですね。
ただ、その実現には、アメリカ政府の支援が非常に重要です。現時点では炭素除去の技術コストが非常に高いため、高品質なものを普及させようとすると、やはり先ほどの上野さんの話でも少し出てきたCCSに対する税控除制度である「45Q」などの政策支援が不可欠ですよね。
上野 炭素除去、特にDACに関する支援政策については、今のところ概ね生き残っています。たとえば、2021年に成立したインフラ投資雇用法では、国内に4カ所の「DACハブ」を整備し、政府の補助金で関連産業を集約することが構想されています。2022年から26年にかけて総額35億ドルの複数年予算が超党派の合意で成立しています。
ここから少しややこしい話になりますが、現在、トランプ大統領はこの構想を含め、脱炭素に関する予算執行を一時的に止めています。すでに議会で認められた予算を執行しないのは本来違法ですが、政権側は「違法ではない」という立場を取っている。司法判断で執行停止が覆されるのかが当面の争点ですが、根っこから予算執行を止めるには、議会で未執行予算を撤回する必要があります。たとえば、先ほどお話しした減税法案の中にその撤回を紛れ込ませるという方法が考えられるのですが、下院を通過した法案では、各種の脱炭素予算の廃止が盛り込まれているものの、DACハブについては手つかずでした。
また、DACはインフレ抑制法の「45Q」の減税も使うことができ、DACでCO2を1トン回収して地中に貯留すると最大180ドルの控除が受けられます。これも下院の法案では残されています。
つまり、トランプ政権が狙ってそうしているのかは定かではありませんが、今のところDACへの支援は維持される可能性が高い、という状況です。
杉山 アメリカ国内で気候変動への姿勢が分極化しているというのはその通りです。ただし、メディアではどうしてもトランプ大統領を中心とした動きばかりが取り上げられがちですが、反対側の動きも確実に存在しています。たとえ政治的には厳しい局面が続いていても、技術というのは一度生まれれば社会を大きく変えていく力を持っています。政治の風向きがどうであれ、技術の進化は確実に前に進んでいく。だからこそ、トランプ陣営としても、技術のインパクトを甘く見ないほうがいいと私は思います。





![集中連載 「コロナの時代」の 戦略思考 [第3回]「巣ごもりの地政学」](https://koken-publication.com/wp-content/uploads/2022/12/池内先生-150x150.png)