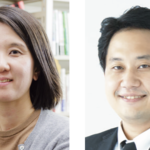革命と君主制の関係性
水島 次に革命と君主制の関係性について考えてみたいと思います。これに関して言えば、オランダとロシアは対極にありますね。ロシアは立憲君主制をめざす試みは挫折して、最終的にはロマノフ家を処刑するかたちで社会主義共和国を築きました。逆にオランダは「反革命」が勝利した国です。イギリスでさえピューリタン革命があったのに、オランダは一度も革命らしい革命を体験していない。
今のオランダは同性婚を制度化し、安楽死も認めています。さらには、売春は合法化されているし、ドラッグも事実上容認されている。非常にリベラルな国でありながら、他方で今でも君主制は健在です。個人間の平等にあれだけこだわっているのに、不平等の最たるものであるはずの君主制が維持されている。実に逆説的です。
オランダは革命も王室の廃止も経験していませんが、進歩的な社会を実現させている。その一方で、旧来の制度や価値観をすべてひっくり返したはずのロシアは、今現在もウクライナと戦争をしています。なぜこんなに分かれてしまったのでしょうか。
池田 ロシア人はよく「私たちは普通の国になりたい。けれども普通が何なのかわからない」と言っています。他の西洋諸国は今日、王政があろうがなかろうが、多かれ少なかれ平穏な日常を送っていますよね。ところがロシアの場合、革命で王権を倒してみると、その後は強権的な体制になって、それがまた突然瓦解するという感じで、断絶がとても大きい。そして断絶しても、強権的であるという社会の基本は変わりません。
この背景にはいったい何があるのか? すごく大雑把に言えば、やはり権力を下から支えるいわゆる市民社会が弱いのではないかと、私は考えています。今のロシアの元になっているのは、13世紀に成立したモスクワ大公国ぐらいからですが、その頃から君主の権利が常に強かったんです。他の中世ヨーロッパのように貴族、領主、騎士などの在地権力が存在している構造ではありません。土地はすべて君主が所有し、貴族の側には所有権が確立していません。実質的には、貴族たちは息子に領地を遺贈しますが、やろうと思えば、君主はそれを取り上げることができる。
だから、私的所有権が芽生えてこない。君主と臣下の関係も本当に一方的な関係ですから、ヨーロッパの封建制における相互の契約みたいな発想が出てこない。そのため貴族も弱いし、貴族の繁栄に促されて勢力を持ってくるはずの商業階級も弱いままです。
近代化していく局面でも、工場などは基本的に上から導入されました。出版業だって皇帝たちが導入しているので、検閲があります。だから、自立的な市民社会が脆弱なままでなかなか育っていかない。さらには、国民の8割を占める農民たちは、ずっと識字率も低いままでいるという社会でした。ですから、バランスに変化が生じて都市社会の支配が崩れると、農民たちが一気に反乱を起こして、それを収めるためには暴力を使うしかなくなるというサイクルがあります。
私はロシア研究者として「ロシアは市民社会が弱い」といったことを言い過ぎるところがあるので、他のロシア史研究の先生たちからは「それは偏見だ」と言われたりもします。けれども、ロシア史を学び、現地に2年間住んだ経験からすると、やはりロシアは市民社会が脆弱だと言わざるを得ないところがあります。アムステルダムの市議会や商工会議にあたるものの発言力が増したこともないし、地方もずっと弱いままでした。今のロシアもそうですが、国家行政は地方自治体と一体化していて、原理的に分かれていないんです。
水島 国家に権力が集中しているわけですね。
池田 役人や議員は、ある時はモスクワ市の役人だった人が、その次には文部省の役人へと動いていたりします。結局どういう原理で動いているのかと言えば、いくつか派閥みたいなものがあって、「誰の子分なのか」ということで動いている。役職や任期といった公の制度が確立されていないので、権力の側は、純粋に人間関係だけで人事を回しています。一般の人々はそれに従っているだけという世界なのでパブリックなものがない。
市民社会が強いほうが君主制を維持しやすい?
水島 逆に市民社会が強いオランダ、あるいはヨーロッパでも北の国々のほうが君主制を維持しやすい、ということになるのでしょうか。現在ヨーロッパで君主制を維持しているのはイギリス、スペイン、オランダ、ベルギー、それから北欧のスウェーデン、ノルウェー、デンマーク、あとは小国のリヒテンシュタインなどがあります。興味深いのは、どちらかと言えば北ヨーロッパの人権意識が強く、平等感覚が強い国々で君主制が残っている。
他方、南ヨーロッパのほうはフランスやイタリアを始めとして、王政を自覚的にひっくり返している国々が多い。結局、近代化の中ですべてをガラガラポンした革命ではなくて、漸進的な民主化、自由化を進めた国々のほうが、結果として見れば、君主制が生き延びている。そういうことが言えるのかもしれません。
池田 すごく逆説的ですね。この話を突き詰めていくと「民主主義とは何か」といった深淵なテーマに行き着くのかもしれません。イギリスであれ日本であれロシアであれ、一つの社会を統治していくためにはなにがしかの権力が必要です。そして権力を機能させるためには、誰がそれを体現するかについての合意が必要です。その仕組みや正統性がなければ、おそらく権力は機能しない。
もちろん選挙で大統領を選んでもいいのですが、実権がない象徴であるならば、それはもう世襲制の君主でも大して問題にはならないのかもしれません。むしろその人物を「私たちの社会の象徴」として置いておくほうが、社会を機能させていく上で割と安定感があるのだと思います。君主制は選挙がないだけに安定感はありますからね。極端に乱暴な君主が出てきたらマズいですが、今は大体どこでも立憲君主制ですからそれはできない仕組みになっています。
ですから、漸次的に議会の力を強めていき立憲君主制に移行した国のほうが、次は誰が権力を握るかという問題を恒常的に考えることなく、安定した社会運営ができるのかもしれない。
水島 実は徐々に民主化が進んで、徐々に君主制が廃止された国というのは、ほとんどないんです。君主制が廃止されたきっかけのほとんどが革命か敗戦です。逆に言えば、革命や敗戦を体験していない比較的安定的な自由民主主義体制の場合は、イギリスやオランダを典型として君主制が安定的に存続できている。
ロシアの場合は、そういった順調な民主化というかたちを取りづらかったために、君主制が革命の中で否定されざるを得なかったのかもしれない。
池田 ロシアは20世紀までずっと専制君主によって統治されていました。1906年に議会と憲法はできますが、その後も皇帝の権力はなお強いわけです。結局、憲法の上に立つ者として皇帝は居続けるので、憲法に縛られない。そういう状態で第一次世界大戦が始まりましたが、社会のあり方があまりに古かったので総力戦に耐えられなくなった。そして、労働者と農民の反乱が起こって政権が倒れた。
けれども政権を倒した民衆は、憲法に基づく共和制の国をつくろうといった理解をもっているわけではなかった。この民衆を率いるかたちで1917年10月に権力をとったレーニンたち共産党も強力な権力を中央に集中させて、自分たちこそが正しい道を知っているのだから我々に付いてこい、というかたちで人民を啓蒙しました。啓蒙専制の一番極端なかたちが共産党体制ですね。だからイデオロギーは違うのですが、ロシアはずっと啓蒙専制であることには変わりがないわけです。現在のプーチンも啓蒙専制君主のようなところがある。
水島 プーチンはロシア連邦の大統領ですが、一種の君主的な存在であると。
池田 そうだと思いますね。だから、彼が亡くなったときにあの国がどうなるのかは興味深いです。今のプーチンの体制も別に誰かに強制されてああなったわけではなくて、気が付いたら強権的な体制ができていたわけです。結局ロシア人の8割ぐらいの人にとって、プーチンのようなスタイルが馴染むのでしょう。
オランダでは、極端な主張もデモクラティックに解消されている
水島 プーチンはまさにペテルブルク出身ですが、彼には今日お話ししてきたようなペテルブルク的な、つまり西側的な要素はあるのでしょうか。
池田 あると思います。もともと彼はテクノクラティックで、西側の理屈をよく知っているリベラルな部分もある人物でした。少なくとも政権初期の頃は、西側とうまくやっていこうと考えていた節がありました。ロシアの近代化を追求する開明派のイメージは強かったんです。もちろん元KGBですから強権的なところはありましたが、同時に合理主義者だと受け止められていました。ロシアのリベラル──反体制派──の中でも、プーチンはヨーロッパ的な発想を捨てないだろうと信じていた人も多かったんです。けれども、今回のウクライナ戦争は彼のこれまでの基準からすれば、かなり極端な路線を突き進んでしまっている。
ちなみにオランダでは、極端な政治家が台頭してくることはあるのですか? ポピュリストはいるとしても、極端に民族主義的な政治家などはどうです?
水島 オランダは過去100年にわたって完全比例代表制で、150議席の選挙を1議席に至るまで配分するという選挙制度を採用しています。政党は0・67%の得票率を獲得すれば、議会に1議席を送れます。マイノリティであっても議席の獲得が容易ですから、様々な連中が政党を立ち上げて選挙に参加しています。イスラム教徒やヒンドゥー教徒など、ありとあらゆるマイノリティが議席を獲得できるわけです。直近の選挙では17党が議席を獲得しました。
興味深いのは、やや極端と思われた新興勢力も、議会でやり合っていると意外に議会のルール・オブ・ゲームに馴染んでくる。議会の場がデモクラシーの一種のガス抜きのようになっている面があります。良くも悪くも開かれたシステムだと言えるかもしれません。
池田 すごくいい話ですね。マイノリティも主張する機会があるわけですからね。
水島 ロンドンのハイド・パークに「スピーカーズ・コーナー」という場所がありますよね。自由に演説をすることができる、独特の空間です。ここでは様々な主張が飛び交いますが、あまりに極端な意見には誰も付いてこなくなります。そうすると、「自分が言っていることはまったく説得力がなかったな」と気付くこともあるでしょう。
オランダの政治空間も似たところがあります。極端な意見は次第に支持を失っていくことが多い。逆に、最初はキワモノ扱いされる極端な主張をしている政党が次第に人々の支持を集めることもあります。
その典型がアニマルパーティー(動物党)です。彼らは「動物の権利を憲法に書き込むべきだ」といった主張です。ユニークな政策を掲げる小政党は、これまでも登場しては消えていったので、同じ運命を辿るのだろうと見られていました。ところが、アニマルパーティーは、若い人たちを中心に勢力を拡大しました。特に博士課程に進んだような若い知識人からの支持もあります。
最近のヨーロッパでは、反肉食の主張をする人が広く見受けられますよね。
池田 ビーガン(完全菜食主義者)的な人たちですね。
水島 そうです。日本ではあまり実感する機会はありませんが、ヨーロッパではベジタリアンではなくてビーガン的な人が多くなっている。彼らは、残虐行為の禁止も含めた動物擁護、動物福祉の徹底を求めています。アニマルパーティーはその先駆的な動きですね。アニマルパーティーが強い市の市役所の食堂では、肉食が制限されるようなことが起きてきます。
いろいろな主張が出て支持を集めることもあれば、支持されないこともある。人々の支持を広く集めた主張は、政策として具体化されていく。民主主義とはまさにそういうものですね。オランダでは、極端な主張も結果的にデモクラティックに解消されていると言えるのではないか。
もちろんオランダにもポピュリストはいます。ポピュリストを「民主主義の敵」とする見方もあります。11月の下院選挙では、反イスラムを掲げる右派ポピュリスト政党の自由党が勝利し、第一党になりました。党首のヘールト・ウィルダースは「反民主主義的だ」と批判されています。他方、過半数の議席をとれるわけではないので、同党の政策が直接実現するわけではない。オランダの完全比例代表制のシステムは、極端な意見があったとしても、極端な行動や運動に結び付かないかたちでの一種のカタルシスや吸収力を与えていると見ることができると、僕は考えています。
池田 やはり優れたシステムですね。
オランダにも負の歴史がある
水島 最後に一点だけ追加させてください。今日は、オランダのいい話ばかりしてきましたが、オランダ擁護だけで終わるのは、ちょっと違うとも感じています。17世紀のオランダは世界で最も繁栄した国でしたが、同時にアムステルダムを中心に奴隷貿易を積極的に行っていました。それによってかなりの富を蓄積したことは、間違いない事実です。
オランダは南米のスリナムを植民地として、奴隷プランテーションを経営していました。アフリカの西側の海岸から奴隷を積み込んで、それをスリナム含む各地に売りさばいていました。この奴隷貿易の歴史に関しては、ようやく昨年から今年にかけて、首相や国王が謝罪を語ることで決着させようとしています。ただし、補償に関しては今のところ特に何も言っていません。アムステルダムは、自由で活発な経済活動と言論活動が繰り広げられてきたことは事実ですが、同時にその豊かさは奴隷貿易に支えられていました。
ただ、オランダはこうした歴史の負の遺産の対処に際しても、スマートです。昨年末に首相が奴隷制、奴隷貿易を謝罪したときは「オランダがついに謝罪した」と国際的にポジティブに報じられました。今年7月にオランダ国王ウィレム・アレクサンダーが謝罪したときも、「オランダは、かつて奴隷制を担った国家の中で最初に国王が謝罪した国となった」と好意的な評価を受けました。ネガティブな歴史をむしろ「オランダは先進的だ」と転換させて伝えることに成功したわけです。このあたりの扱い方のうまさは本当に見事です。
ただし、この点においてロシアは、奴隷貿易に手を染めた、血塗られた過去をそれほど持っていないですよね。
池田 西ヨーロッパ的な意味での奴隷貿易や植民地主義は、ロシアにはありませんでした。国外に植民地を持たなかったですからね。
ロシア人は、自分たちは民族差別をしないという自意識を持ってきました。中央アジア人だろうが、ジョージア人だろうが、一緒にやってきたのだという認識が強いんです。ただし、今回のウクライナとの戦争をきっかけに、それはロシア人の思い込みに過ぎなかったという面も浮き彫りになっています。諸民族共生を掲げてはいますが、過去の時代を振り返るとロシア人の側からの差別はあったし、政権の側から諸民族への激しい暴力ももちろんありました。「ロシア史にも植民地主義があったのではないか、再検討すべきだ」という議論が、いま研究者のあいだでは起こっています。
それでも、ロシアが海の向こうに植民地を求めに行かなかったことや、多言的文化の世界を尊重していたことは、本来はロシアの良いところであり、強みだった部分のはずです。
ヨーロッパの王室は進歩的?
──現代のヨーロッパの王室の方々は進歩的な人物が多い印象があります。
水島 確かにデモクラシーの発展した国の君主たちや王室の人々は、どちらかと言えば中道左派的なスタンスを取ることが多いですね。結果的には、それが一番幅広く支持を受けるうえで効果的だからでしょう。逆に右派の人々は、国王や王族がリベラルなことを言うのを苦々しく感じることもあります。
もともと100年前のヨーロッパでは、左派、社会主義勢力は反王室を前面に掲げていました。それが次第に弱まり、語りにくくなったのは、王室が比較的リベラルな意見を代弁してくれるところがあったためだろうと思います。このあたりの位置取りについては、ヨーロッパの王室はかなりセンシティブに反応しています。結果として見れば、それが立憲君主制を支える一つの王道になっている印象はありますね。
池田 よくわかります。だいたい19世紀に王権の側が国民化していって、国民の模範的な存在になっていたところがありますね。それまでは王家や貴族はコスモポリタンですから、自分の国のことはよくわからないけれども、ドイツやイギリスなどよその国の皇帝とはお互いに親戚同士だったりしたわけです。それが19世紀後半ぐらいからは、まずは自分の国の君主として振る舞うことが求められるようになった。そこがうまくできた国は君主制が割と安定して残って、それで議会制と調和してやっていく。そこがうまくいかないと革命で倒されるし、最悪ロシアのように殺されてしまう。
存続した王室の側はそうした例を見ています。なので、あまり目立たないようにすることも含めて、戦略的に振る舞っているのだと思います。
水島 まったくその通りだと思います。そして第二次大戦中にナチスドイツに占領されて亡命した君主たちは、一種のレジスタンスのシンボルとなりました。オランダ、ノルウェー、ルクセンブルクなどの王室はイギリスに逃げて、そこからBBCで自国民に対して奮起を促す呼びかけを行いました。ナチスドイツへの抵抗のシンボルでしたから、戦後になっても正当性は強いですよね。
ただ、あのときに微妙な立場を取ったベルギーの君主などは、今に至るまで国民的正統性が弱いところがあります。結局のところ、君主がデモクラシーの守り手、担い手として国民に理解されるかどうかが、君主制存続の試金石となるのでしょう。 (終)
水島治郎
/
千葉大学法政経学部教授
みずしま じろう:1967年東京都生まれ。ライデン大学留学(94年──95年)を経て、東京大学大学院法学政治学研究科修了。博士(法学)。日本学術振興会特別研究員、甲南大学法学部助教授、千葉大学法経学部准教授、同大人文社会科学研究科教授などを経て2012年より現職。著書に『ポピュリズムとは何か──民主主義の敵か、改革の希望か』『反転する福祉国家──オランダモデルの光と影』『隠れ家と広場──移民都市アムステルダムのユダヤ人』など。
池田嘉郎
/
東京大学大学院人文社会系研究科
(西洋史学)教授
いけだ よしろう:1971年秋田県生まれ。東京大学文学部西洋史学科卒業、同大大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。98年10月から2000年9月まで文部省アジア諸国等派遣留学生として、モスクワのロシア科学アカデミー・ロシア史研究所に研究員として留学。新潟国際情報大学情報文化学部講師、東京理科大学理学部准教授、東京大学大学院人文社会系研究科(西洋史学)准教授などを経て2023年より現職。著書に『革命ロシアの共和国とネイション』『ロシア革命──破局の8か月』など。