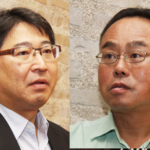失語症の文学
──大学院生時代は京大俳句会に入っていたとお聞きしました。今でも俳句は詠みますか?
上野 もうすっきり止めています。1990年に歌集を出して、そこで「今後は一句も増えません」と宣言をしました。それが最後です。自分にとって必要がなくなったのです。
──俳句で何かを表現する必要がなくなったのでしょうか……?
上野 俳句は不自由な表現です。とにかく短い。私は俳句を「失語症の文学」と呼んでいます。私は俳句で何を表現していたのか。私たちの大学闘争は惨憺たる敗北に終わりました。あの闘争からより多くを学んだのは大学側です。大学は学生の管理の仕方を闘争から学んだのです。夜間に門を施錠するとか、電源をオフにするとか、キャンパスの管理が厳重かつ巧妙になったのを実際に見てきました。
しかし、学生は惨憺たる思いで敗北を味わいました。そうするとだんだんと言葉が出なくなってくるんです。それでも、やはりポロッとつぶやきみたいなものが漏れる。それは世界で最短の詩型である、わずか17文字の俳句で思いを表現するのにぴったりでした。自分のつぶやきを盛る器として、当時の私は俳句に縋ったのです。それが10年経ってみたら私は俳句に縋る必要がなくなったので、もう詠むことはありません。それだけの話です。
──他の表現方法に出会ったのでしょうか?
上野 私がその10年間で出会ったのが、女性学です。女性学に出会った時、目から鱗が落ちる思いがしました。こんな学問が存在するのかと。この出会いによって俳句に縋る必要がなくなりました。
そもそも、自分の好奇心を満たしてくれると期待して社会学を始めましたが、やってみたら社会学もつまらなかったのです。学問の中に私の居場所はないと感じました。なぜだろうとよくよく考えてみると、それまでの学問とは、男の男による男のための学問、つまり男の子がいかに生きるかということを学ぶものだったのです。女である私がいかに生きるのかということに、学問は答えてくれそうにないと感じましたね。
女が女を語ることが許されていなかった
──どこにそこまで惹かれたのでしょうか?
上野 自分自身を研究の対象にしてもいいと思えたことです。しかし、学問は中立的かつ客観的でなければならないと考えられてきました。その考えに基づくと、女が女の研究をすると主観的であり、それは学問ではないと言われたのです。
ただ、男が書いた女性論はたくさんあったんですよ。ドイツ哲学ではショーペンハウエルやバイニンガー、社会学ではジンメルが女性論を書いています。
デカルト、カントと並ぶ三大哲学者のショーペンハウエルが女性を何と定義したかご存じですか? 「成人女性は成人男性と子どもの中間の生き物である、なぜなら男は子どもと遊ぶとすぐに飽きるが、女は1日中飽きもせず遊んでいることができる。女はその分だけ子どもに近いからだ」と。笑ってしまいました。これが哲学の論証だと見なされていたのです。
私の師匠の一人である社会学者の作田啓一さんはジャン=ジャック・ルソー研究者として有名な人です。そのルソーは、「民主主義の父」「フランス革命の父」として歴史に名を残している人物で、『エミール』という素晴らしい教育書を書いています。実は、私の父が、『エミール』は抱いて寝ていたぐらいの愛読書であったと言うのです。父がそこまで言う本はどんな本なのかと私も読みました。すると、本の最後に「以上述べてきたことは女の子には当てはまらない」と書いてあったのです。「女の子は男を支えるように育てるべきだ」と。冗談かと思いましたね。
日本の小説家では吉行淳之介や渡辺淳一も女性論を書いています。読みましたが、妄想の集合でしかありません。女性を貶めるか女神化するかのどちらかですが、どちらも女性にとっては迷惑です。
渡辺淳一は「女のことは僕が一番よく知っている。だから、女について知りたければ僕に聞きなさい」と言いました。でも考えてみてください。女がどういう生き物で何を感じて何を考えるかは、「あんたに教えていらねえよ」です。こんなことを話していると怒りが湧いてきますね(笑)。
男性が書いた女性論は腐るほどあったのですが、学問の世界では女が女を語ることは許されていなかった。だから、私にとって女性学は目から鱗の学問だったのです。ただ、そんなものは学問ではないと言われていたのですが。
問答無用のエビデンスと理論
──上野先生が考える女性学とは?
上野 私が定義するまでもなく、女性学を日本に持ち込んだ井上輝子さんというパイオニアが、「女性学とは女の女による女のための学問研究」だと定義しました。ただ、この定番は物議をかもしました。「女の女による」という点が問題となりました。男たちが「男は女性学をできないのか」と言い出したのです。しかし、女が学問の客体から主体になることが大事でした。
加えて「女のため」という点も気に入らなかったようです。「女のため」となると、ある特定の社会集団の利益になる学問となりますので、「中立性」の原則に反します。したがって女性学は偏ったイデオロギーであると批判されました。
例えば、マルクス主義も労働者階級の利益のための学問とされていたので、日本ではマルクス主義は偏ったイデオロギーだと考えられていました。同じように女性学も女性という特定の社会集団の利益に奉仕する学問ですから、偏ったイデオロギーであって、そのようなものは学問ではないと。これを跳ね返すのに大変な思いをしました。
──どのようにその批判を跳ね返したのでしょうか。
上野 問答無用のエビデンスと理論です。これでもか! これでもか! とデータを示して理論的に証明していきましたよ。ここでようやくそれまで身に付けた学問が、私の武器として役に立ったのです。エビデンスと理論があれば相手を黙らせることができますから。私は論争に強い女と呼ばれました。
家事は「不払い労働」である
──ご著書『家父長制と資本制』の中で「家事は労働である」と提言されました。当時としてはかなり常識とは異なる考えです。
上野 そうですね。当時は専門の経済学者たちから「家事を労働だと君たちが主張するのは、君たちが経済学に無知だからだ」と、取り合ってもらえませんでした。労働の概念が狭すぎることが問題だと、「不払い労働」という概念を定着させていきました。
──家事の扱いに違和感を持ったきっかけは?
上野 私の母を見ていたからです。当時、主婦は三食昼寝付きで、「良いご身分だね」と言われていました。ところが私の母を見ていると、朝は父より早く起きて家族の朝ごはんをつくり、姑が要介護になれば世話もしていました。朝から晩まで母はこまねずみのように働いていましたから、私からするとこれはまったく三食昼寝付きどころではない。なのに感謝すらしてもらえない。
そして、母の謎を解こうと、主婦は何する人なのか研究をしてみたら、とても奥が深かった。10年かけて『家父長制と資本制』を書き上げて、「家事は労働ではない」と言ってきた人たちに、ようやく母のリベンジ戦を果たせたと思っています。
ただ、家事は労働であると提唱したら、経済学者だけでなく、主婦からも猛反発が来ました。彼女たちの主張によると、家事はお金に換えられない価値のある愛の行為だと言うのです。今もそう思っている人はいるのではないでしょうか。
──私は評価されているような気がして嬉しいです。
上野 そうですか。労働の定義は、「第三者に移転可能な活動」です。家事も育児も介護も第三者に移転可能ですから、労働です。それを第三者に委ねると対価が発生するのに、妻や嫁がやると対価が発生しない、おかしい、というのが出発点です。誰かがやらなければならない重要な労働なのに、不当に支払われないから「不払い労働」と呼びます。今になってようやく世の中の常識が変わってきたようですね。
学問はスッキリするための極道
──怒りに飲み込まれてしまうことはないでしょうか? 上野先生は闘士のように戦っているイメージがあります。
上野 そんなことないですよ。研究自体はとても楽しいですから。新しい発見の連続で、好奇心を満たしてくれます、こんなに楽しいものはございません。学問は自分がスッキリするための死ぬまでの極道だと言っています。それが人の役に立つかどうかはよくわかりません。お金にならなくてもいいのです。
──世の中を良くしたいなどが動機ではないのでしょうか?
上野 それもありますが、研究者の動機とは自分自身の謎を解きたいという好奇心に尽きます。目の前にある謎を解きたい。子どもの頃に夢中になったものはないと言いましたが、私が初めて夢中になったものが女性学です。
極道といえば、音楽やスポーツも同じです。これらが具体的に何の役に立っているのかといったら答えられませんよね。オリンピックに出場して「皆さんに勇気を与えたい」と言うアスリートの方がいますが、大きなお世話です。では、この方たちは何のために厳しい練習に耐えているのか。それは、達成感を味わうことが自分自身に対する最大の報酬だからではないでしょうか。世のため人のためでも、拍手喝采を浴びるためでもありません。
だから、私は学問が他のあまたある極道よりも優れたものだと思っていないのです。ですから他の極道に比べて、偉そうな顔はしないでおこうと自戒しています。
私の場合、幸運だったのは、私が謎だと感じていたものが、当時の多くの女たちが直面する共通の謎だったことです。同じ謎に取り組む仲間がいたのです。しかも日本に限らず世界中に。私が情報を発信すると、それを受け止めてくれる人たちがいました。