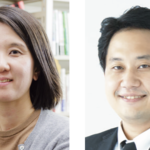「地霊」とは何か?
阿川 『地霊を訪ねる』に話を戻します。この本は日本各地の鉱山を旅することが核になっていますけれど、その土地ゆかりのいろいろな人物が登場します。それに温泉ですよね。「源泉掛け流し」という言葉が頻繁に出てくる。これが「地霊」とどう関係するのかよくわかりませんが、キーワードですよね。
猪木 いや鉱山のそばには温泉があることが多いからね。それだけですよ(笑)。
阿川 そうですか(笑)。私は温泉というか熱いお湯が苦手で、源泉掛け流しの有り難さがよくわからないものですから。山奥にはあまり行ったことがないんです。猪木さんは同行者と別れて、わざわざ山奥まで温泉を求めて行かれることもありますね。
猪木 温泉の湯を循環して再利用したり、加水・加温をしたりしていないから源泉掛け流しだと気持ちのうえで違いますよ。地中から湧いてくるんですよ。熱いお湯が。けど近年、地下のお湯が少なくなってきているようですね。
阿川 そもそも地霊って何を意味しているのですか?
猪木 本のなかでは「『地霊』とは、『思想風土』あるいは『習俗』として、その土地その土地に沁み込んだ、いまは亡き人々の思いの堆積から発せられる無言の声とでも言えようか」と書きましたが、説明が不十分ですね。
私としては、日本をもっと見てみたいという思いがありました。今まで日本の経済史や日本の労働市場を勉強してきましたが、日本がどのような歴史と地理を持つ国なのか、きちんと見てこなかったと反省しています。近代の日本を発展させた二つの重要な産業があります。一つは繊維産業です。主に綿業、それから蚕からつくる絹の製糸業。もう一つが鉱業です。経済史では若いときに繊維をやる人が多いこともあって、繊維に関しては厚い研究蓄積があります。
一方の鉱業はもちろん研究はなされていますが、繊維ほどではありません。ですから近代日本の工業化を担った鉱業──金、銀、銅、鉄、石炭、鉛、マンガン、石英など──の操業地がどのような変遷を辿ったのかを知りたかったんですね。かつては基幹産業で栄えた地域が、今では荒廃地になっているところが多い。もちろん産業転換をうまくやって、別の産業で地域を再生させたところもありますけど。
経済地理的な観点だけから、そうした鉱山の跡を紹介しても、どうしてもスチール写真(静止画)を見るようなものになってしまう。けれども、そこには現在に至るまでの経緯があるわけです。地理的な現実と経済史の両方から見なければ、「日本は何か」ということを掴まえることはできないのです。
ともかく僕も先は長くはないので、いろいろな鉱山の跡を歩いて見て参りましょう。地元のものを食べましょう。温泉にも入りましょうというわけです(笑)。
美味しいものは、食べられないように身を守っている
阿川 食事の描写も何度も出てきますね。「意外に美味しい蕎麦屋さん」とか。
猪木 兵庫県にある生野銀山を訪れた際に城崎温泉で「津居山ガニ」──津居山港で水揚げされた松葉ガニ──を食べているときに自然科学の重大な原理原則を発見したんですよ。カニって美味しいけど、食べにくいでしょう。美味しいものは、食べられないように身を守っている。これはニュートンぐらいの大発見だと思う。
阿川 そういう記述がありました。栗もそうだと。
猪木 ウニもそうです。こころが深くて美しい人もそうでしょう。
阿川 それは相手にもよるんじゃないかと思うんですけどね(笑)。
猪木 食べ物に関しても実際に口にしていくと、いろいろな理解の仕方があることがわかる。些末なことかもしれませんが。
阿川 いやその通りだと思いますよ。
猪木 われわれ研究者は抽象的な表現ができたらハイレベルだとみなしがちですが、観念的な言葉はごまかしがある場合が多い。
阿川 ありますね。自省を込めて前から思っていたのですが、書いていることが自分自身で本当にわかっていないからごまかす。
猪木 本当にわかっている人が書いたらわかりやすいはずですよね。
阿川 できる人の本は、難しくても読める。できない人はわからないから難しい。難しいことがらを簡単に書くことができる天才のような人もいますね。
京都で御霊について考える
阿川 猪木さんがカニを食べて大発見をされた生野銀山編では、福崎町出身の柳田國男の話が出てきますね。柳田は「日本人の死後の霊は、里の見える山の上へ行くと考えた」と書かれていますね。「霊は地下へ行くのだ」「根の国というのがある」と言っていた本居宣長の説は気に入らないと。
猪木 柳田國男は「地下には行かない」と言っていますね。
阿川 その根拠は何でしょうか。私にはわかりません。
猪木 柳田國男は聞き書きをベースにしていますから、土地の人がそう言っているというのが根拠じゃないですか。
阿川 『古事記』にも黄泉の国が出てきますね。イザナギは死んでしまった奥さんのイザナミを、地中にある黄泉の国に訪れ、帰ってくるように説得しますが、見てはいけないと言われた妻の死体にウジがたかっているのを見て怖くなり、逃げて地上に戻ってくる。西洋の子どもの物語にも、地下に潜る話がたくさんあります。柳田の御霊は山に行くという説にはしっくりこないところがあります。
私は慶應を退職し同志社に移って一年の半分ぐらい京都で暮らすようになって、初めて御霊のことを考えるようになりました。京都では死んだ人が霊になるのが、今でもごく自然であるように感じます。今日の会場の周辺にも上御霊神社と下御霊神社がありますが、明らかに御霊が主人公です。東山に目を向けると、清水寺の向こうは墓ばかりですよね。
猪木 あだし野(念仏寺)にはいらっしゃいましたか?
阿川 行きました。圧倒的ですね。嵯峨のあの辺りは、あだし野だけでなく、その先も霊に満ちているように感じます。だから京都にいると、御霊は山の上の高いところに行ってしまうのではなくて、それほど遠くない地下にとどまっていて、いつでも帰ってくるように思えるんです。帰ってきた先祖の霊を五山の送り火であちらの世界へ再び送り返す。霊は毎年帰ってくる。そしてそのうち私もあちらへ行くけれども、またこちらへ帰ってくる。だから、この街の人たちは死なないんじゃないかと感じるようになりました。
こんなことを申し上げたら失礼かもしれないし、猪木さんは不愉快に感じられるかもしれない。けれども、なかなか伺えなかったので今日聞いてしまうと『地霊を訪ねる』にはどこかに奥様がいるなと思うんです。ときどき奥様が出てきますよね。
猪木 いやほとんど出てこないですよ。愛妻家の阿川さんが勝手に空想しているんでしょう(笑)。
阿川 ほとんど出てこないけど、旅をしている猪木先生の心中をはかるに、鉱山や経済史、地霊のことを考えながらも、どこかで先に逝かれた近しい人のことをときどき思い出されているのではないかと勝手に想像しているんです。
猪木 いや、それは当たっていないですね(笑)。ただ、霊一般のことを考えることはあります。大学時代の友人で医者になったのがいます。彼がまだ研修医だった頃に聞いたんですが、患者が最期亡くなる瞬間「ふぅーっ」と息を返すと言うんですよ。『旧約聖書』の「創世記」でも神が土から人間をつくる話が出てきますよね。
阿川 アダムとイブですね。
猪木 そのときに息を吹き込むでしょう。人は死んだら土左衛門じゃないけど、物体になりますね。まったくのモノになる。けれどもモノになる前は、われわれであれば研究したり、今日のように、ためになるのかどうかもわからないような話をしたりしている。
そういうことをする「力」がわれわれのなかに潜んでいる。だから人間を人間たらしめているのは、その力なのかもしれない。亡くなると、それがスポッと抜けてどこかに帰っていく。それは山の上に行くのかもしれないし、下に行くのかもしれない。僕は土に帰るほうが宇宙の秩序として安定感があるように思いますが。
阿川 不思議ですね。東京にいると考えないのだけど、京都にいるとそういうことをときどきふと思う。いろいろなことがあったこの街の長い歴史がそうさせるのかもしれませんね。老舗のご主人と話をしていると、「うちなんかまだ300年ですから、ご先祖様のおかげでやらしていただいております」などと、何気なく言われる。今宮神社前のあぶり餅屋さんにどのくらい続いているのかと聞いたら「そやな、1000年ぐらいかな」と言ってました。平安時代からずっと同じことをやっているわけです。
そうすると、死んでも死んでいないような気がしてね。「ふぅーっ」と吐き出した何かがその辺りをときどき歩いているような感じがします。私が住んでいたアパートの前も、生きている人ともう死んでしまった人が、あちらの世界へ行ったり来たりしているかなと想像しました。
猪木 海に散骨することもありますが、肉体は基本的には土に帰りますよね。器だった身体が土になってしまうと、その人が持っていた喜び、悲しみ、恨み、怒りなどこの世の感情がその辺りに漂うことになる。『地霊を訪ねる』ではこの感覚についてチェーホフを引用しています。
「やがてお寺で夜半の祈祷の鐘が鳴りだすと、彼はふと自分が死んで、ここに永遠に埋められているもののように考えた。するとその時はじめて彼は誰かが自分をじっとみているような気がして、いやいやこれは安息でも静寂でもないのだ、じつは無に帰したものの遣瀬ない憂愁、抑えに抑えつけられた絶望なのだと、一しきりそんなことを考えた。…」(「イオーヌィチ」神西清・原卓也・池田健太郎訳『チェーホフ全集(11)』)
墓場で愛人を待っているときに、誰かが自分を見つめていると感じるわけです。これは迫力のある神秘だと思う。エロスとタナトスと言うじゃないですか。愛と死が一緒になっている。
阿川 セックスは一般に死ぬときと似たような経験をしているとも言えますね。
猪木 拙著のなかでも、蚕の話として、繭が脱皮してサナギとなり羽化した蛾が交尾して一晩で約500個の卵を産んで一生を閉じる話を書きました。アリストテレスが同じような生殖と死のことを言っていますね。阿川さんはアリストテレス級の含蓄がある(笑)。
阿川 そうですか、全然知らなかった(笑)。でもあれは死の始まりですよね。人の誕生にしてもそうで、「おめでとう。君は必ず死にます」ってことであるように思います。身もふたもないですが。若い頃は、自分だけでなく、近しい家族が死ぬことがとても怖かったのですけれど、それが歳をとって鈍感になっているのかどうかはわかりませんが、今は「まあいいや」みたいな感じになっていますけどね。
『地霊を訪ねる』を読んでいても、猪木さんはこのとき何を考えておられたのかなと気になる場面がいくつかあって、それはきっと今は亡き近しい人のことを考えておられるのだろうと思ったわけです。きっと猪木さんの守護神は奥様なんですよ。
猪木 ほら、阿川さんご自身が愛妻家であることを告白しているではないですか。
阿川 誤解です。諍いがいつも絶えない。
猪木 奥様の話が多い人は、たいてい愛妻家なんですよ。阿川さんは愛妻家の典型です(笑)。