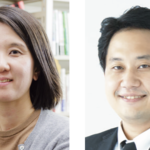番長グループのナンバー2と一対一で喧嘩
──やはり語学の習得にセンスがある。
木村 語学を学ぶのは大好きでした。ただ高校時代は、柔道ばかりやっていましたし、後輩たちはやんちゃな連中でしたから、揉め事が多くてなかなか勉強に集中できないんです(笑)。中学校では虐められたから、高校ではあの屈辱を二度と味わいたくないと思って、柔道部に入部したんですが、そうしたら今度は上級生の番長グループに目を付けられた。
──またですか(笑)。
木村 貧しい家庭の子たちが多く集まる大阪の下町の落ちこぼれ高校ですから、そんなもんですよ。休み時間になると番長グループが1年生の教室に脅しをかけに来るんです。先ほども言ったように、当時のぼくはもう逃げないぞと心に誓っていましたから、よし、その時が来たなと思いました。
5、6人に囲まれたので、「どうしたんです? ひょっとして寄ってたかって1年生のぼくを袋叩きにするつもりですか。まあ、好きにやったらよろしいがな」と言ったんです。そうしたら向こうもちょっと怯みましてね。後で聞いたところでは、2年生の番長グループでナンバー2と言われていた生徒らしいんですが、その生徒が「よし、一対一でやったろやないか」と言ったので、「それなら筋が通りますね」と返すと。「放課後、校門のところで待っとれよ」と捨て台詞を残して向こうに行きました。
──絵に描いたような修羅場ですね。
木村 腹をくくってしまうと、こういう場面では妙に落ち着くんですよ。授業が終わったら教室の外で先ほどのグループが待っていて、学校の裏へ連れていかれました。先生たちもうすうす気付いていたようですが、見て見ぬフリです。自分が大人になって同じような立場に置かれてもそうするでしょうね。
学校の裏手に着くと、なぜか近くに小学生が立っていてこちらを見ていたものですから、「危ないぞ」と声をかけた瞬間に殴られたんですが、その後のことはよく覚えてないんです。とにかく、われに返ったら相手が目の前でひっくり返っていた(笑)。
喧嘩した上級生とはその後に仲良くなりました。卒業してからその先輩に高校で偶然会ったら、「おれは今、日本拳法をやっているんや」と言ったので、「どうしてそんなのをやっておられるんです?」と尋ねると、「お前を倒すためや、決まっとるやろ」といったので、二人で大笑いしました。
番長連中に懐かれる
──外国文学の翻訳家とは思えない青春時代ですね(笑)。
木村 それからも柔道の練習は熱心に続けました。師範がいなかったので、岩波書店から出ていた『柔道講座』という、たしか8巻ものの本を図書館から借りだして技の掛け方、体さばきなんかを覚え込んでいったんです。ぼくの師範はあの本でしたね。
2年生になると入部してきた後輩連中に懐かれましてね。気がついたらキャプテンになっていました。ところがガラの悪い地域の落ちこぼれ高だから、入ってくるのは中学の番長みたいなのばかりなんです。練習にあまり来ないんですが、そんな彼らをなだめすかして続けていたら、いつの間にか大阪府でベスト8に入りましてね。後輩もいかつい連中ばかりだったんですが、彼らに慕われるようになってわが家は梁山泊状態になりました(笑)。
大学に入ってからも高校の後輩連中との付き合いが続きました。その頃にもいろいろな事件があったんですが、語り出すときりがないので、今回は端折ります(笑)。
大学受験の3日前に警察に捕まる
──木村さんの高校時代に戻りますが、神戸市外国語大学のイスパニア学科を受験されたのは、スペイン語にご関心があったからですか?
木村 いやいや、募集要項には「イスパニア学科新設」と書いてあったんですが、イスパニア語というのがスペイン語だということさえ知らなかったんですから、能天気なものです。同級生がたまたま大学の募集要項を見ていて、欄外に小さな活字で「イスパニア学科新設」と印刷されていたのを見つけて、ここはみんな見過ごすはずだから「絶対に穴場だ!」と言ったので、藁にでもすがる思いで受験することにしたんです。イスパニアというのはスペインの古名で、新設学科をつくる際に、主任教授の高橋正武先生が学科の名称はスペインの古名イスパニアがいいだろうという鶴の一声で決まったそうです。
ぼくは神戸外大にイスパニア学科が新設されたことも知らず、同級生が「穴場を見つけた」といった言葉にしがみついたんです。募集要項の枠の中には英米学科、ロシア学科、中国学科と並んでいて、その欄外に小さな活字で身をひそめるように「イスパニア学科新設」と書いてありました。これならあまり目につかないから、受験生も少なくてひょっとすると潜り込めるかもしれないと、せこいことを考えたんです。ところが、受験の手続きに行ったら長蛇の列ができていて、実質倍率は約7倍を超え、改めて人生は甘くないと思い知らされました。それに追い打ちをかけるように受験の3日前に警察に捕まったんです。
──何があったのですか?
木村 試験も終わったので、高校の柔道部に足を向けたんです。練習を終えて、帰ろうとしたら、横を歩いていた後輩が向こうから来た男と「肩が当たった、当たらない」で揉めましてね。その後輩は大阪府でもベスト10に入るような猛者でしたから勝てるわけがないのに、向こうが闇雲にとびかかってきた。後輩はそいつをぶん投げたんです。ぼくも止めに入ったんですが、気がつくと場所が何と警察署の真ん前で、すぐに連行されました。ぼく自身、そばにいた小柄な男と揉み合いになったんですが、それはなかったことで済ましてもらいました。
つかみ合いをした二人が署内で調書をとられているときに、目の前を通りかかった警官に「3日後に受験なんですが、今回の件で受験はダメでしょうね?」と尋ねたら、「お前も喧嘩したんか?」と訊かれたので、「いいえ、やってません」と答えると、「そしたら関係ないやろ」って(笑)。
──助かりましたね。見逃してもらえた(笑)。
木村 だけどその日の夕食の時に、父に「これまで受けた大学はすべて不合格だったし、残っている一校も受かりそうにないので、受験を辞めようかと思っている」と言ったら、「あほやな、お前。受験って勉強やと思っとるんか。あんなもんミズモノやないか。科目は何が苦手や?」って訊かれて、「数学」と答えると「3日間、数学だけやったらええ!」。言われた通り3日間、数学の問題集とにらめっこをしたんですが、試験場で問題用紙を開くと、何と前日に参考書で見たのとほぼ同じ問題が出ていたので、わが目を疑いましたね。
ビリから2番目で合格
──勝負強い。
木村 人生ってやっぱり、運と縁だなとしみじみ思いますね。高校へ報告に行っても、教師はもちろん同級生や後輩も、ぼくが合格したとは信じてもらえなかったんです。中でも、受験指導の先生に報告に行った時がいちばん愉快でしたね。教員室に行って、「神戸外大に受かりました」と報告すると、先生は急にがっくりうなだれると、長い間一言も口を利かずその姿勢のまま固まってしまったんです。
こちらが不安になって、「先生、大丈夫ですか?」と尋ねたら、しばらくしてようやく顔を上げると、「うーん、ついていけるかなあ。ここがどんな高校かお前もわかってるやろう」という返事がかえってきて、えっと思いました。同級生や後輩からも、陰でいろいろ言われていたようですが、どうやら試験に合格したところで、どうせ授業にはついていけないと思われていたんでしょうね。
大学入学後に同級生から聞いたのですが、ぼくの成績は入学した40人中の尻から2番目だったそうです。愉快だったのは、尋ねたクラスメートに、「ぼくはビリのはずなんだけどな」とつぶやいたら、彼が「いや、お前はうしろから二番目や。最下位はオレなんだ。ちゃんと事務局で確かめてきたからな」という後日譚もありましたね。紙一重で入学しても気にしなくていいんで、高校の英語で経験したように入学してから頑張ればいいんだと前向きに考えたんです。
大学ではスペイン語と英語は一生懸命勉強しましたね。その一方で、小説本が好きだったので、日本人が書いたものはもちろん、翻訳ものの小説もよく読みました。中学時代以来ずっと卒業したら、商社に就職して、スペイン語圏の国であれ、東南アジアであれ、どこへ行ってもやっていけるように心の準備をしておこうと考えていました。
「木村くん、大学に残らないかね」
──学部の4年間を終えると大学に残られていますね。商社ではなく学者の道を選ばれた。
木村 いや、今申し上げたように卒業したら兄のように商社に行こうと決めていたので、大学の先生になることは考えたこともなかったですね。ただ3年生の終わりくらいに、周囲で「われわれ一期生の中から1名が助手として大学に残ることになるらしい」という噂が耳に入ってきました。4年生になってそろそろ就職試験の時期だなと思っていたら、突然イスパニア学科の高橋正武教授から「木村くん、大学に残らないかね。学科の先生がたとも話し合った結果、君にお願いしようということになったんだ」と言われて、びっくりしました。
当時はスペイン語関係の大学院がどこにもなかったので、一期生の場合、学部を卒業したら中の誰かが教員として残るというのが慣例になっていたようで、東京外大や大阪外大も同じだったそうです。古武士然としたところのある高橋先生は少々おっかない感じがするんですが、人柄がよく、信頼の置ける方だったので、その話を受けることにしました。
父はぼくに大学の先生の仕事が務まるとはとても思えず、心配だったようですが、もしその仕事をするのなら、「本が財産だからお金の勘定をせずに本を買え。本屋の借金が払えなくなったら何とかしてやるから、怖がらずに買え」と言ってくれました。
「ラ・マーガに出会えるだろうか?」
──最初はスペイン文学をご専門にされていたとか。
木村 二十世紀初頭に活躍したスペインのある作家の作品研究から第一歩を踏み出したのですが、徐々にその作家の書くものにうんざりし始めましてね。自分の生まれ故郷であるスペイン北部のバスク地方に題材をとった作品は、抒情的でよかったんですが、作者が首都マドリッドに移ってから書いた作品はかつての生気というか、輝きが失われておもしろくなくなったんです。その作家と同世代の小説家たちの作品にも目を通してみたんですが、やはり肌にあいませんでした。おもしろいと思えない小説と格闘して、うんざりしながら論文を書いて業績稼ぎなどしても意味がない、それならやめたほうがいいや、とまで考えましたね。
ラテンアメリカ文学に興味を持つようになったのは、まったくの偶然の産物なんです。「禅を学びたいと思って日本にやって来た」一人のメキシコ人が、「神戸市外国語大学にスペイン語を教えている学科がある」という話を聞き込んでやってきたんです。そこで1年生だったか2年生の学生をつかまえて、事情を話して助けてもらおうとしたんですが、思惑通りにいかず、学生のほうも持て余して、ぼくに泣きついてきた。
それで、いろいろ相談に乗ったんですが、それがうれしかったんでしょうね。ある日ぼくに、「キムラ、お前はスペイン文学の研究をしているが、ちっともおもしろくないとこぼしていたな。だったら、どうしても読んでほしいすごい本があるんだ」と言って、見るからに前衛的な感じのする真っ黒な装丁の分厚い一冊の本をぼくの手の上にのせたんです。それが、アルゼンチンの作家フリオ・コルタサルの書いた実験的な小説『石蹴り遊び』だったんです。
「ラ・マーガに出会えるだろうか?」という冒頭の一行を見たとたんに、こんな書き出しの小説があるんだ、と衝撃を受けましてね。当時は自分が向かうべき方向が定まらず揺れていたので、「出会う」という言葉に衝撃を受けたにちがいありません。その単語が啓示のように閃いたんです。それから「コルタサルの書いたものをすべて取り寄せてくれ」と洋書の代理店に頼みました。やがて、コルタサルの作品、それも上質な幻想的短篇集が次々自宅に届き、至福の時を持つことができ、本当に幸せでしたね。
それを起点にして、以後ホルヘ・ルイス・ボルヘス(アルゼンチン)、アレホ・カルペンティエル(キューバ)、ガブリエル・ガルシア=マルケス(コロンビア)、マリオ・バルガス=リョサ(ペルー)、ホセ・ドノソ(チリ)など枚挙にいとまがないほど多くの作家の創造した世界にもぐりこみ、その世界を生き、かつ何冊かは翻訳までさせていただいたというのは、この上ない幸運としか言いようがないですね。