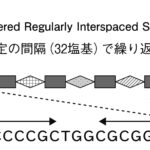『公研』2022年3月号「interview」

宗家花火鍵屋十五代目 天野 安喜子
昨年の東京オリンピックで唯一日本人として柔道の試合を裁く女性がいた。さらに彼女は日本最古の花火屋「宗家花火鍵屋」の15代目である。日本の文化でもあるこの二つの世界で活躍する天野安喜子さん。ご自身の勤めにどのように向き合っているのだろうか。
──東京2020オリンピックでは、柔道で唯一の日本人審判員として、決勝の大舞台でも裁かれました。
天野 そうですね、決勝の審判員に選ばれることへの誇り、嬉しさはひとしおです。審判員に選ばれたからには誤審のないように気を引き締めて裁こうと覚悟を持って、畳に上がっていました。
柔道は審判員もランキング制になっているので、世界トップ16位までしかオリンピックの舞台に立てないのです。柔道の試合には常にスーパーバイザーや審判理事の方々がいて審判員を審査しています。
オリンピックを裁く審判員は、大会開催前の世界選手権やグランドスラムなどで良い裁きをしている審判員を対象に、開催2年前に50人程に絞られ、一年前で30─20人に絞られていく。オリンピックにたどり着くまでに2年以上、共に世界各国をまわりながら試合を裁いていくのでみんな家族のようになってくるんですよね。そうやってようやくオリンピックの審判員になることができても、さらに会期中の試合で裁きの評価点数が付けられていますので、安心はできません。
自国の選手の試合は裁けないので対象外の試合もありますが、3位決定戦と決勝戦は評価点数の高い、選ばれた審判員しか裁けないのです。
──オリンピックでは8日間で37試合も裁かれました。これはこの期間で裁く試合数として多いのでしょうか。
天野 他の大会ですと、何百という参加選手を2日間─3日間で裁かなければいけないこともありますので、37試合という数は多くはありません。
しかし、オリンピックや世界選手権というのは、大きな大会を勝ち抜いてきた選手たちだけに対しての裁きなので、緊張度や空気感が他の大会とは違い1試合ごとの重みがかなりあります。そういう意味では、全ての試合に集中力を持って裁けたちょうど良い試合数でした。
──試合ごとの息抜きはされますか。
天野 試合毎に気持ちを抜くことはしないので会期中の8日間、ずっと緊張し続けていました。オリンピックが始まる前から自分のテンションをつくり始めて気持ちをコントロールするんです。
唯一、切り替えという意味では試合毎に折り紙を折っていました。何も考えず、折ることに集中することで無意識に気持ちの切り替えをしていたのかもしれません。
ちなみに、オリンピック以外にも柔道の審判員として世界を周ることがあるので、折り紙は日本の文化を知ってもらえたらということもあって必ず持っていっています。鶴やくす玉などを折ってアロマの香りをつけて置いてみたり、他のレフリーの方々が少しでもリラックスできるような空間作りにも役に立てていました。
「見せる柔道」を仕掛ける
──審判員同士どのようなコミュニケーションがあるのですか。
天野 一昨年までは主審と2人の副審が一緒に裁く三審制でした。反則や技の裁きの基準、判断のタイミングは、3人の呼吸が合っていないと裁けないので、そういう意味でもコミュニケーションをとることが必然と重要になってきます。審判員の育ってきた国の文化、柔道を見る視点など試合で一緒になった審判員同士、日常をある程度知り得た中で共に呼吸を作っていくのです。審判員同士は一つのチームですので、コミュニケーションをとることは最も重要なことです。
それから柔道の審判というのは技を判定するだけでなく、リズムを作ることで「見せる柔道」にすることも大切な仕事です。審判員が中心になる動きではなくて、選手がお互いエキサイティングに試合できるよう、黒子のような動きで仕掛けていくという役割もあるんです。
一昨年、阿部一二三くんの試合(2020年12月東京オリンピックの内定を懸け、丸山城志郎選手と24分におよぶ長い死闘となった男子66kg級代表決定戦)もそのリズムをつくっていくことで長くなってしまいました。
リズムが審判員毎、試合毎にバラバラだと選手は混乱してしまうので、審判員同士コミュニケーションをとって、誰が裁いても一定のリズムになるような流れにしなければいけないのです。私は選手の「心」と「気」も読んで畳の上だけではなく、観客にもコーチ・監督にも納得してもらえるような裁きを心掛けています。
単純にミスジャッジがない裁きだけではいけないということに気づくのに年月がかかりましたし、気づいてからの試行錯誤も非常に苦労しました。
審判員は自分の心を決してに表に出さない
──2008年北京オリンピックの審判員も経験されていますね。その時のメンバーもいますか?
天野 いえ、もう皆さん引退されています。私は柔道の国際審判員を15年間もしていますので、私が一番古いと思います。
海外の試合に行くと自国を留守にしてしまいますから、審判員が本職の仕事を持ちながら世界をまわることは実は難しいのです。サッカーや、野球の国際審判員ですと生活ができるぐらいの社会的地位になってくるのですが、柔道の国際審判員はまだまだボランティアのような形なので、それだけでは生活はできない状況です。特に日本国内での審判員の仕事はボランティアになっていますので、別のお仕事を持っていないと難しいです。海外の皆さんも、柔道審判員に加えて、警察官、弁護士、お医者さんなど、国に帰ってもお仕事ができる社会的地位を持っていらっしゃる方も多いです。元々柔道の戦歴を持った方々もたくさんいらしています。
審判員は日本の中だけでも数万人いますから、世界の審判員の人口で考えると相当な数がいます。その中で国際のトップに居続けるのはなかなか難しいことなのです。このような中で選ばれた審判員は、前に前に進もうという非常にポジティブなメンタルを持っている方が多い。そんな審判員の方々と活動をしているので、とても良い刺激になっています。
それから、オリンピックの審判員は選手たちからすごいと思われるような立ち居振る舞いをすることが訓練されています。ホテルから一歩出ると姿勢が一気に変わるし、一方で帰りの送迎バスに乗ったとたん、音楽をジャンジャン鳴らして盛り上がったりと、ある意味豹変ぶりがすごいです(笑)。そのくらい、試合では決して自分の心の動揺、心自体も表に出さないのです。
──柔道審判員をされるきっかけはお父様のお誘いだったそうですが、審判のどのようなところに魅力を感じて決意されましたか?
天野 当時、オリンピック競技に女子の柔道も加わったので女性審判員を育てようという動きがありました。父も柔道家で、その頃東京都柔道連盟の役員をしていましたので、柔道を引退したばかりの私に白羽の矢が立ったのです。
その時、私は山梨に花火の修行に行っていたのですが、父からの電話で審判員のお話があり、即答で「審判員の試験を受けます」という返事をしました。それは審判員に魅力を感じて返事をしたのではなく、天野家では父の一言は絶対で、打診してくることはやりなさいという意味に等しいからでした。審判員に魅力を感じたり、何か目標があって進んだという格好良いバックグラウンドはありません(笑)。
公式試合で審判をする方は経験を重ね、柔道家としてタイトルを取ってきた方が多いのですが、ちょうど私が審判員になった当時は女子柔道の試合では、なるべく女性が裁こうという動きがありました。まだ女性の審判員が少なかったので、審判員になったばかりの私でもいろいろな試合で裁く機会をいただきました。
しかし、日本の柔道界は、国際大会に出ても金メダルを取っていないとメダルとはみなされない、という不思議な呪縛に包まれているんですよね。私も福岡国際大会で日本代表として出場し、3位になりましたがメダルではないと思っています。
私は他に大きな大会に出たこともないし、タイトルも取っていない。このような経歴で、ましてや女性なのに大きな試合を裁いていることにコンプレックスを感じていた時期もありました。そのコンプレックスに打ち勝つには経験と実績を積むしかない、一つひとつを丁寧に審判員として上がっていくしかない。審判員として誰にも負けない経験を積み上げていこう、とある時から思い始めたんです。
そうして経験を重ねるうちに「白黒はっきりつける」って面白いなと思うようになりました。たぶん、私の性格にも合っているんだと思います。がむしゃらに頑張ってきた部分もありますが、気づいたら20年裁いていました。

学問としての花火
──ここからは天野さんのもう一つの顔である花火師のことを伺っていきます。花火師になりたいと思ったのはいつからですか?
天野 小学校2年生の時には鍵屋の15代目を継ぐことを心に決めていました。父の背中を見て育っていたので自然なことだったのだと思います。それからは父の期待を裏切ることが自分の中では許せなかったので、いつでもいい子で居た気がします。
鍵屋の花火玉は協力工場へ発注するのですが、自分で花火製造の技術を身に付ければ、「できること・できないこと」を理解した上で職人と向き合って仕事ができると思い、山梨の花火製造工場で2年間修行をしました。
そうして2000年に鍵屋の15代目を襲名しました。
──花火師としてすでに活動をされていた中で、なぜ改めて日本大学大学院芸術学部に入学して花火を研究しようと思ったのですか?
天野 「なぜ花火は人に好かれているのか」、それを知りたいと思ったことがきっかけでした。つまり作り手側でなく、観ている側が感じるものを研究したいと思ったのです。
花火は危険なものですので、火薬の調合や安全のための構造といった工学的な研究はされてきましたが、芸術的と言われながらも芸術分野の学問として論じられたことがなかった。それならばあえて一番最初に研究してみたい、と芸術学の門をたたきました。
──どのような研究をしたのですか。
天野 人は、打ち上げ花火の迫力や感動をどうやって感じるのか、花火のどのような事象から印象を得るのかという研究をしました。
まずは鍵屋の花火大会にご来場されているお客様に何千枚もアンケートを配布して、花火の音やリズム、形が、見ている人の心にどのように影響しているのかを調査しました。
さらに心理的な分析をするため、視覚・聴覚の要素に分けて大学で印象評価実験をしました。花火の打ち揚がる音に音楽を入れたときと、入れないとき、そして音がない花火の映像など、いくつかのパターンの刺激を作成して、それぞれの要因が印象にどのように作用するかのデータを取りました。その結果、人が花火に感じる印象というのは、花火大会の要素である「視覚的要因・音要因・音楽要因」の変化によって起こるものだと確認できました。
花火の迫力はビジュアルではなく音から感じるもので、例えば、花火の迫力を出したい場合は、打ち上げる時の「ドン」という音を際立たせるために音響は控える。逆に、舞踊の演出として背景に花火を打ち上げるのであれば、音が激しく鳴らない花火を選び、ビジュアルは流れるようなイメージの花火にすると舞踊が映える。
このような研究を「打ち揚げ花火の『印象』──実験的研究による考察──」という論文にまとめ、日本大学大学院芸術学研究科で博士号をいただきました。私がこれまで花火師として活動していたことがデータを見て間違っていなかったという確認ができ、研究の結果を今の花火の演出に活かすことができています。

──花火師として具体的にどのようなお仕事をされているのですか。
天野 全体のコーディネート、デザイン演出のほか、火薬の申請、電気配線の計算、実行委員会との調整、現場での指揮など綿密に半年以上かけて準備をしています。打ち揚げの現場では、たくさんの職人や関係者が入るのでそれぞれの仕事で摩擦が起きないよう、全体を見て動くようにしています。
今は昔と違って、打ち揚げは直接点火するのではなくボタンを押して打ち上げる遠隔操作による点火です。そのボタンを押すタイミングが大事なので、全て私が一つひとつ指揮者のように手を振り下げて指示をしています。練習はできませんから皆を信頼しています。私は共に働くスタッフにプレッシャーをかけるのが得意なので(笑)、「ま、いいか」で仕事することが嫌なんです。
人間らしさがある花火
──花火のデザインをするときは?
天野 私の演出は自然界で人の心を動かすようなことを花火を使って表現しているんです。例えば、激しい稲妻は美しさと怖さが表裏一体となっています。それを花火という手段を使って表現するんです。そういったイメージをもとに「光・音・色・形」を指定して数社ある協力工場に花火玉を作ってもらいます。桜の色一つとっても濃厚なピンクだったり、淡いピンクだったり、工場によって微妙に違ってくるので、その都度審査して一番イメージに近い工場に依頼します。
また、演出のアイデアは、日々の生活の中から生まれます。私は、人の笑顔を見るだけで心が温まりますし、何か少しの変化や出来事に感動しやすいのでアイデアのストックはいつでもあるんですよ。
でもあるとき、発想がどうしても出ないことがありました。その時は流行語やその地域の老若男女の比率とか、理論で考えて無理にデザインをしたのです。そのようにしてできた花火は、綺麗ではあるものの、機械的で型にはまりすぎてしまって、自分の中では面白くなかった。「ただ綺麗にするのが掃除ではない、葉っぱ一枚を残すくらいが風情である」というような教えと同じ感覚で、人の心を大切にする「人間らしさ」がなかったんです。
間を愛でる心
──「鍵屋の花火」とは?
天野 鍵屋の花火は「人の心を大切に」したいと思っています。コンテストで審査員が評価点数を付けるような花火ではなく、見ている人の幸せや優しさの感情が溢れ出て、それを人に分かち合える場になるような花火大会をしたいと考えています。それは心を豊かにすることにつながる。人だからこその感情を大切にしていきたいのです。
鍵屋の花火大会の特徴でもありますが、会場に来ているお客さまは最後にドドッと一斉に打ち揚がるクライマックスを期待しています。その瞬間、「ほらきた!」という一体感を感じるような演出も大切にしています。
また、花火が打ち上がるリズムがずっと一定だと、人は飽きるんです。でもちょっとリズムを不規則にはずすと、それが人を惹きつけることにもつながる。その絶妙な外し方、程よいリズムがあるのです。そのような程よいリズムの中で生まれる「間」が命です。一つ打ち上がって美しいねと感動する、花火の消えたあとの真っ暗な夜空の余韻を楽しむ。「間を愛でる」というのは日本の文化でもあると思うんです。
現代は最新の技術で効率重視の便利な世の中ですが、鍵屋の花火は古き良きものも大切にしながら時代に即して進化しています。
──コロナ禍で人が集まりづらくなっています。今後、花火はどのようになっていくのでしょうか。
天野 360年の歴史がある「宗家花火鍵屋」は、これまで疫病、戦争、震災などで花火ができなかったことが幾度となくありました。日本にコロナが広まった2020年は、終息祈願として花火を打ち揚げました。花火を「揚げる」は「掲揚」の「揚」です。この漢字が使われているように願いを天に届ける、さらに火というのは悪いものを浄化させる作用があるということで、収束祈願として花火を打ち揚げたのです。その時は音楽もなく、エンタテインメント性のない、ゆっくりとしたリズムで花火を揚げたのです。いつもと違うものでしたので、花火の量が少ないとか、何故この時期に花火を打ち揚げるのかとご批判があるかもしれないと思っていました。
しかし、花火を見た方々からは人と触れ合えない状況下、一つの物を見ることで繋がっている感覚を持てた。涙が溢れた、といった声を多く聞きました。花火というのは見ている人の気持ちがリアルに繋がるんです。
私は今を受け止めて、今できることをして次に繋げたいと思っています。このようにして乗り越えたのだと、記録を残すことが大事だと思っています。もちろん生活は変わった部分もありますが、くるものがきた、と嘆いてはいないです。
花火は、エンタテインメント性を求めるだけのものではありません。人の心に寄り添い、勇気を与えることができるものでもある、と確信を持っているのでこの先も怖くないですね。
今回のコロナ禍は、花火の新しい方向性を見いだすヒントをもらったような気がしています。
身に染みついた「覚悟」
──花火師と柔道審判員、ご自身の中で影響し合っていることはありますか。
天野 花火の打ち揚げ現場は危険と背中あわせです。緊急時では責任者は自分の持ち場を動いてはいけないので、現場へ誰かを行かせるという究極の判断が必要になります。こんなに怖いことはないです。ですからその判断には相当な覚悟がいるんです。その身に染み付いている「覚悟」が、柔道審判員で畳に上がった時に裁きの判断をする「覚悟」に繋がっていると思います。
また、私の心の哲学、心の幹は実は柔道から成っています。柔道での挫折や取り組みを通して、自分一人ではなくみんなの協力があって成しえるという感謝の気持ち、目標を掲げたら人が押し上げてくれるのを待つのではなく、自分でもがいて掴み取りにいくことを知りました。このことは「人への感謝を持って、がむしゃらに進む」という私の仕事の姿勢に活きています。
柔道も花火の仕事でも共通しているのですが、マイナスをプラスに変えていくようなポジティブで「熱い人間」が自分の周りにたくさんいるんです。それを受けて私も、もっと熱くなる。人に恵まれていることは非常に幸せなことです。

──天野さんご自身のパワーが熱い人を引き寄せているような気がします。
天野 「安喜子」という名前にもあるように、人に喜んでもらって皆さんに笑顔になってもらいたいという強い使命が自分の中にあるのです。そのためにも私はなんでも全力投球することを心掛けています。子育てをしながら花火師、柔道整復師の勉強、柔道審判員、学位、五つを平行していた時もありました。大変な時期ではありましたが、その経験を通して、結果だけではなく、頑張る姿勢、その過程が大事であることを学びました。だからこそ、真剣勝負で一緒に仕事をした人や学友とは心が通って仲間になれるんですよね。
私は柔道場で子供たちの指導もしていますが、正直でいること、声を出すこと、力量に差があっても構わないが、やる気に差があってはならないと指導しています。
聞き手・本誌 並木 悠