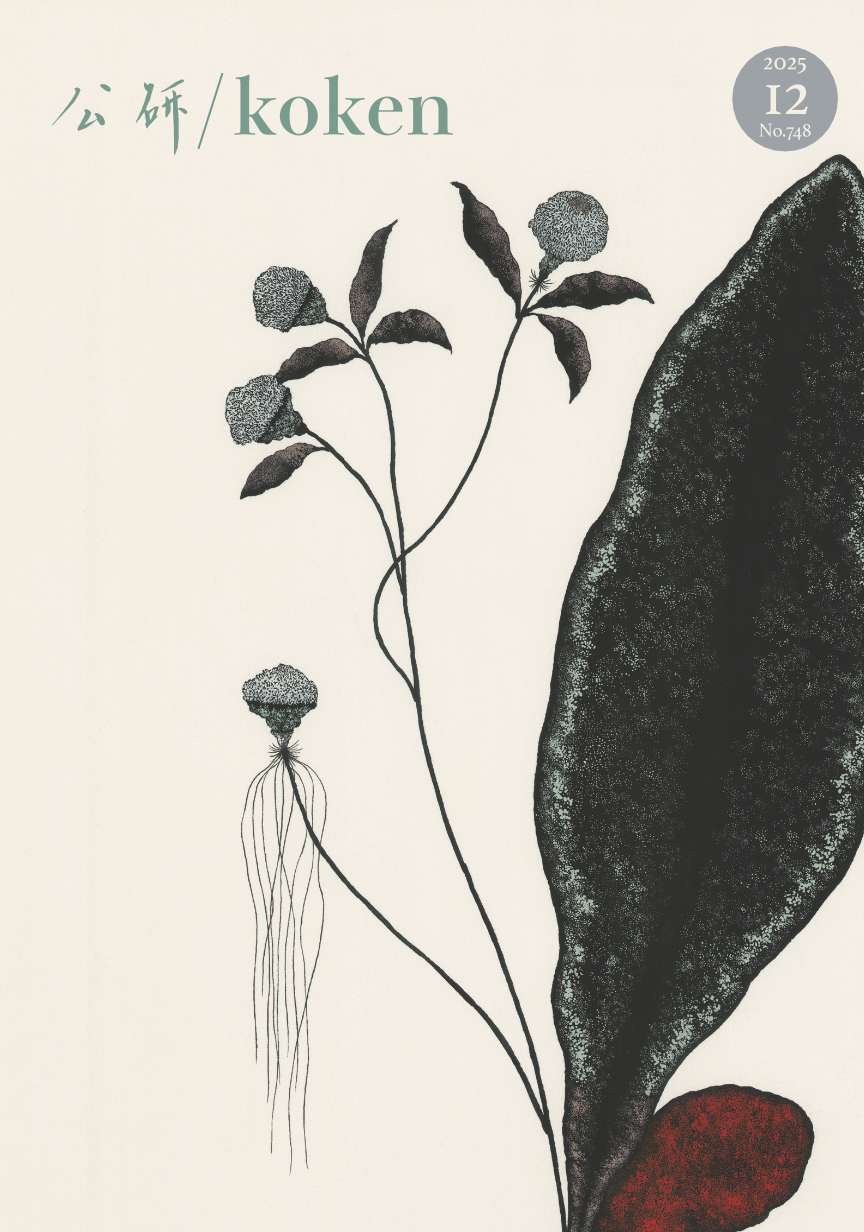農業における人手不足は極めて深刻
砂原 うまくいっている新しい取り組みについてお話しいただきましたが、主要産業の一つである農業の現状はいかがでしょうか。農業従事者の高齢化や不足が指摘されてから久しくなります。
上田 農業における人手不足は極めて深刻な状況で、今後さらに厳しくなっていくと想定されています。そうした状況を踏まえたうえで、今後の農業がどうあるべきなのか。花巻市が農業の一つのあり方として追求しようとしているのが有機栽培です。昨年11月には、環境に配慮した持続可能な農業の実現をめざす「オーガニックビレッジ宣言」を出したところです。
これから有機農業を進めることを明確に打ち出したわけですが、大事なことは消費者に直接結び付くことです。有機栽培は手間暇が掛かりますから、全体の生産量が減ることになります。要するに、高く売れなければ採算は合いません。ですから、多少高くても買ってくれる消費者をどれだけ探し出せるのか。ここがポイントになります。正直に言って、花巻の場合は都会の人ほど所得が高くありませんから、やはり外の人に買ってもらうという選択肢を持たなければなりません。
ここは、先ほど紹介した高橋博之さんがやっているような事業が参考になるのだろうと思います。つまり都会の消費者に花巻で有機栽培される農作物の品質の高さを広く知ってもらうことで、購入してもらうことに尽きるわけです。売れることが実感できれば、生産者も苦労してでも有機農業を進めるべきだと考えるはずです。だから、買ってもらうところを見つける取り組みは全力でやっていきたいと思っています。
ただし、問題になるのはやはり人手不足なんですよ。農業者はどんどん減っています。稲作はほとんど機械でやりますから、担い手が少なくとも何とか維持することができます。花巻も今では農地のほとんどが集落営農か法人になっています。農地所有者はほとんど収入もないのですが、貸すことによって何とか農地を守っているんですね。
その農業法人や集落営農の方々が、いま圃場整備(農地、農道、用水路などの整備・集約化)を進めています。例えば、今まで1反歩(約1,000平方メートル)だった水田を5反歩だったり1町歩(約10,000平方メートル)の水田にすれば、効率的に機械化できるんですね。一時期は圃場整備が進まなかったのですが、今は進み始めています。これにはものすごいお金が掛かるし、5年10年単位で時間もかかります。けれども、集約化が進み、機械化することによって農業者が減少しても生産できるような農業に転換しつつあります。ただし、野菜や果樹となると、どうしても機械化がむずかしく人手が相当かかるんですね。今は70歳以上の人たちが農業の中心になっていますから、彼らに野菜や果樹の生産を担ってもらうのは現実的ではありません。やはりここには限界があります。
花巻市は平成18年に旧花巻市と3町(石鳥谷町、大迫町、東和町)が合併して今の花巻市になりましたが、特に石鳥谷地域はリンゴの名産地として知られてきました。全国的に見てもとても美味しいリンゴができるのですが、リンゴ農地は年々減少しています。リンゴ栽培は1年中やらなければならないことがあって手間が掛かるので、従事者が高齢化すると止めてしまうケースが多いんですね。とても美味しいリンゴですから、つくれば売れるんです。今でも栽培しているところは、ネットで販売して高く売っている人が多いんです。だから儲かるのだけど、つくれなくっている現状があります。
野菜をつくるケースを考えても同じなんです。コメに比べると儲かるのだけど、本当につくる人がいない。なので、生産量は減ります。この状況を一体どうするのか。これは花巻だけではなくて、国全体の課題になっています。
亡くなる人が多く、生まれてくる子どもが少ない
砂原 人がいなければ、規模が縮小していくことは避けられないですよね。この10年くらいの地方創生を振り返ってみると、どうしても人の奪い合になった側面があったと思います。今のお話があったように、人が来てくれないと困るので、何とか人を呼び込もうと努力していたところがありました。花巻市に限らず、どこの地方自治体でもそれは同じだったのだと思います。
この10年間、人口を増やすために非現実的なものも含めて、いろいろな政策が打ち出されましたが、成果が上がっているとは言えない状況です。上田市長はまさにこの期間に花巻市長を務めてこられたわけですが、この10年間の地方創生や人口を増やすための政策については、どのように振り返りますか。
上田 「あまり役に立たなかった」と言うのは簡単ですが、私は必ずしもそうではなかったと思います。人口減少で、一番大きいのは自然減なんですね。生まれてくる子どもが極端に減っているのはもちろんですが、亡くなっていく数も大きいんです。花巻の場合は、65歳以上の人口は3年前から減り始めています。けれども75歳以上の人口はあと5、6年は増え続けます。また、85歳以上人口は、あと10数年は増え続ける見込みです。ですから、亡くなる人は間違いなく増えます。
今は毎年1400人から1500人が亡くなっています。それが1600から1700人くらいになる時代がやってきます。その一方で、生まれてくる子どもたちは確実に減っています。5、6年前までは600人ぐらい誕生していましたが、今では約400人になりました。コロナ禍で極端に減ったんですね。これは全国的な傾向ですから、人口は間違いなく減ります。
優先すべき課題は、やはり少子化対策になります。日本以上にこの問題が深刻な韓国では教育にものすごくお金が掛かることがネックになって、子どもを持つことが負担になってきたのではないかと指摘されてきました。親も子どもに十分な教育を与えて幸せにできるのか、自信を持てないでいるのではないかと。それで韓国は、子ども支援に巨額の予算を計上していますが、それでも成果は上がっていない。合計特殊出生率は0・72(2023年)まで減少していますから、日本の1・26 (2022年)よりも遥かに悪い。
砂原 ソウルだけを取り出すと0・5くらいという推計もあります。
上田 韓国を参考にすれば、お金を出しても子どもがすぐに生まれるわけではない。けれども、それでもやはり子育て支援は続けなければ、出生率はさらに減りますよ。経済的な事情で子どもは一人だけでいい、二人目は厳しいと考える家庭は多いわけです。そういう人たちに、子育てにかかるお金のことは心配せずに、子どもを産んでもらえる環境をつくることは大事です。子育て支援を充実させる方向性自体はやはり間違いではなかったと私は思っています。
花巻市に関して言えば、平成18年に1市3町が統合する前から人口は減り続けていました。特に社会増減(転入・転出による人口の増減)はずっとマイナスでした。ただ、この5、6年はプラスに転じています。昨年はマイナスでしたが、社会増はそれなりにあるんですね。特に30代、それから0歳から14歳の人口が増えていますから、子育て世代が移っていることは間違いないでしょう。子どもを育てやすい街として、花巻市はそれなりに評価はされているのだと見ています。
砂原 そうした子育て世代は、どういうところから花巻市に移られてきているのですか?
上田 花巻の場合は、県内が多いことは間違いないです。県内の他の地域と比較した社会増減を見ると、一時的にマイナスになる場合もありますが、ほとんどの地域はプラスになっています。東北全体で見ると、仙台との関係ではマイナスです。全国で見ると、首都圏との関係ではマイナスになっています。やはり、東北地方の中心である仙台や東京に特に人が移転しています。
砂原 地方創生を始めるときには、「人口のダム」といった喩えがよく使われていました。地方の中核となる都市が人の移動を食い留めてダムのような機能を果たしてもらおうという考え方でした。東北地方で言えば、県内の比較的小さな市や町村から仙台などの中核都市に人が移っていき、そこから東京などのさらに大きな都市に移動していく数はなるべく減らそうというわけです。
ところが、この「人口のダム」は結局あまり機能していなくて、首都圏に行く人がすごく多い。関西で言えば、大阪ですらダムの役割を担えていなくて、東京に人が流れていっています。地方の小さな市町村↓地方の中核都市↓東京といった感じで、人口の移動の仕方が2段階になっている傾向が指摘されています。首都圏への一極集中は相変わらず続いていて、東京があらゆる地域からを人を吸い上げているのが現状です。
上田 岩手から見ると、やはり仙台は住みやすい場所だと思いますよ。雪があまり降らないことは、北国の人にとっては魅力ですよね。比較的海沿いですから、夏も盆地ほどは暑くない。人口も100万人を超えていますから、いろいろな文化的な催しもあります。仙台には都会に必要な要素がそろっています。知事も半導体の企業を宮城県に引っ張ってくるなど努力されている。
仙台が発展することは、岩手にとってもメリットはあります。例えば、仙台空港を発着する国際便が増えると、そこを経由して岩手を観光する人も増えてくる。ただし東京との関係で仙台が人口のダムになることによって、東北全体が良くなるという単純な話ではないんですね。人口のダムとしての仙台に人が吸い上げられると岩手県は結局人口が減少することになります。
いまご指摘いただいたような人の移動は、花巻市のなかでも見られることです。先ほど今の花巻市は、1市3町が合併して誕生したとお話ししましたが、かつて町だった地域から旧花巻市に移ってくる人は増えています。例えば、市役所の職員は職場に近く住みたいということで、親が住んでいた自分が生まれた町を離れて、旧花巻市内に家を建てる若い人が増えているんですね。減る地域にとっては、この動きは頭の痛い話ですよね。
こうした人の流れについては、強い危機感を持っています。その回答がどこにあるのか考え続けなければなりませんが、誰も答えを見出すことはできないと思うんですよね。
花巻に仙台や東京にあるような文化的な側面を含めて、都市の機能を持たせることはムリな話です。そういう意味では、東北では仙台にそうした機能を持たせて首都圏への流出を防ぐダムの役割を果たしてもらうのは、わからないでもない。それでも仙台から東京へ人が移動してしまうのは、日本全体のバランスを考えたときに、好ましい状況ではないのと同様、東北の各県から仙台に人が移動することも決して好ましい状況とは言えないだろうと思いますけどね。
有効な空き家対策はあるのか?
砂原 住宅についても少しお伺いしていきたいと思います。このところ課題とされているのは空き家の問題だろうと思いますが、花巻市ではどのような取り組みをされているのでしょうか。
上田 空き家は深刻ですよ。どんどん増えています。調査で花巻市には1000戸ぐらいの空き家があることを掴んでいますが、実態はもっとあるでしょう。高齢者だけが住んでいて、お子さんたちが仙台や東京に行っていたりとすると、その方が亡くなってしまうと空き家になります。それが放置されて雑草も刈られなくなると、小動物が棲みついたりして、ますます荒れてしまう。近所からすれば非常に迷惑です。
こうした空き家を有効活用するための「空き家バンク」という仕組みもあって、私が市長になったあとに花巻市でも始めています。増減はありますが、大体380戸くらいの空き家が登録されているんですね。「空き家バンク」を利用して物件を借りたり、購入された件数は制度を作ってから10年弱で累計220件になります。そういうかたちで活用するのが一番いいんですね。空き家に住む場合、補修費等について花巻市の補助金の対象となる場合もあります。例えば、水回りの修繕に市の補助金を活用する方が多いです。
それから草刈りなどがされずに放置されている空き家については、所有者を調べたうえで適正な管理をお願いする文書を出す際に、シルバー人材センターの案内も一緒に送っています。そういうところに頼むと、通常よりも安く草を買ってもらえるわけです。なるべく綺麗に保ってもらうための工夫は行っています。
砂原 地方の住宅問題をデータなどでつぶさに見ると、急激に人口が減少している集落の近くに、新しい住宅地が開発されているケースが結構あります。新しく住宅地を開発するとなると、インフラを新たにつくり直す必要も出てくるのだと思います。人口減少下でも新築中心の考え方は根強い印象があります。
上田 いろいろな考え方がありますよね。賃貸の公営住宅を充実させて、そこに住んでもらうという発想もあります。そうすれば、新たに住宅地を開発し持ち家住宅を新築する必要はありません。しかし、既存の賃貸公営住宅が老朽化し利用も低調な中で地方が新たな賃貸公営住宅を今後どしどし建設することはあまり考えられませんし、今の国の政策もそういう方向にはなっていないですよね。
実際地方の場合は、安く家を建てられるんですよ。「毎月5万から6万円の支払いで家をつくれる」といった宣伝がたくさん載っています。花巻であれば、400万かそこらで土地を手当てできて、家を建てても2000万ぐらい出せば3LDKの家に住めます。そうした背景もあって持ち家住宅の新築が多いことは間違いないです。
ただ、家ができる場所には問題があります。先ほども触れましたが、新たに家ができるのは旧花巻市エリアなんです。旧3町に新築ができるのは、実家のすぐ近くに家を建てて住むというケースを除くとまずないんですよ。旧花巻市においても市街地が離れたところではなく、市街地に比較的近い場所に建設されることが多い傾向がありますから、急激に人口が減少している集落の近くに、新しい大規模な住宅地が開発されているということは花巻においてはあまり考えられません。また、花巻市は、市街地に近い場所を含めてほとんどの平場の土地が農振法(農業振興地域の整備に関する法律)上の農業振興地域になっており、住宅、商業施設、工業施設などを建設することが農振法に基づいて制限されています。昨年制定された農振法の改正によって農業振興地域からの除外はさらに難しくなりますので、市街地に近い農業振興地域の住宅、商業施設、工業施設などへの転用は例外的な場合を除いて実際上できない状況になります。
それでも、いま現在は花巻市に住んでもらうために、新たな住宅の供給は必要な状況がまだ続いています。例えば、お隣の北上市には大きな工場ができていて1000人ぐらいが働いています。それが今後2000人から3000人に増えることも見込まれていて、そうすると花巻市内で勤務する方々に加えて、花巻市に住んで北上まで通勤し勤務する人たちが一定程度いるんですね。その人たちの住宅については、整備していく必要があります。
従って、大規模開発は難しいとしても、今後も小規模な住宅地開発が進められることが想定されます。市としてはその部分については、環境の悪い住宅をつくってもらっては困るので、例えば、6メートルの幅のある道路を通してもらうことなどを条件にして、開発に補助金を出すような政策を打ち出しています。
公営住宅については、今後は市営住宅を増やすつもりはありません。古いものを長寿命化して、それでもダメなものは壊していくかたちになります。公営住宅についてはそういう状況ですが、東日本大震災の被災者が住む住宅については、国や県から花巻にもつくってほしいという要望があったので、街中に30戸くらいつくりました。元々は衰退した商店街でしたが、バスも通るし、1階にはコンビニが出店しました。便利だということで、住んでいる人たちからも、「花巻はいいところだ」という声を多くいただきました。被災者の方が住まなくなったら若者世代に住んでもらっています。
砂原 賃貸物件も含めた民間の中古住宅事情はいかがでしょうか。地方自治体では、そもそも不動産の流通量が少ないという話をよく聞きます。極端な例だと、夕張市などは不動産屋さん自体がなかったりする。
上田 先ほどお話しした空き家バンクが機能していますから、花巻では中古物件を探す手段はあります。市のホームページには具体的な写真や間取り等も紹介して、すべての物件を掲載しています。最終的な契約は、不動産業者に頼みますが、そうしたかたちで市でも支援しています。ですから、流通していないから空き家や中古物件を利用できないということは花巻ではないですね。