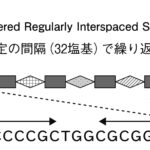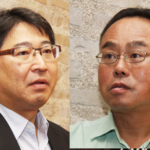2021年12月号「issues of the day」
日銀の政策運営の特徴について、故・中原伸之氏が次のように評したことがある。「『突然に』、『それまでの議論とは180度逆の方向に』、『十分な説明もなく決定する』という三つの原則がある」と。これは、中原氏が先行して提唱した「量的緩和」が採用されるに至った際の日銀の豹変ぶりを簡潔にまとめたものだ。ただ、この「中原三原則」は政策運営における教訓として、いつの時代にも幅広く通じるものであろう。
リフレ派
リフレ派の大御所として知られた中原氏だが、「リフレ派」は事後的に広まった呼称であり、日銀審議委員(1998─2002年)としては舌鋒鋭いハト派の論客だった。東燃(現ENEOS)社長を務め、企業経営者としての知見を見込まれて審議委員になったとの印象はない。経営者の枠を超えた経済論陣が評価され、政府は日銀・政策委員会の議論活性化を期待して審議委員就任を打診したと言われるが、まさに適役であった。
一般的に金融界や経済学界から登用されて審議委員になった場合でも、就任時から政策論に踏み込む向きは少ない。この点、中原氏は当初から緩和姿勢が鮮明で、就任間もなく緩和策の提案に動いた。98年に施行された改正日銀法の下で、それまで「スリーピングボード(眠れる委員会)」と揶揄された政策委員会は、中原氏の緩和論にリードされて覚醒する形になったのは間違いない。
三原則成立の背景
ここで「中原三原則」が成立する日銀豹変の背景を説明してみたい。日銀が豹変を余儀なくされた要因としては、既に政策金利の下げ余地がほとんどなく、「ゼロ金利に到達したらまったく身動きが取れない」との思いが強過ぎたことだ。「緩和余地がない」との政策判断が先に立つと、結果的に情勢判断は甘くならざるを得ない。景気悪化が懸念されても、緩和余地を温存したいため、情勢判断は楽観に傾きやすいわけだ。
残念ながら、当時の経済情勢は、日銀の楽観を裏切る形で悪化が続いた。前年秋に三洋証券破綻を契機に勃発した金融危機は不良債権問題の深刻さを露呈させ、銀行は貸し渋りを強めた。景気は低迷を深め、中原委員の利下げ提案を後追いする形で日銀は政策金利を引き下げ、99年2月にゼロ金利に到達した。2000年8月のゼロ金利解除が失敗し、翌年春にこれまた中原委員の提唱していた量的緩和を採用するに至った。
政策判断は、言うまでもなく情勢判断を踏まえて決められるものだ。景気悪化が予想されるなら、自然体で緩和策を講じればいい。しかし、緩和余地がない、との思いが強いと情勢判断は楽観的な色彩を帯び、緩和効果に懐疑姿勢を示すようになる。確かに当時の緩和余地は乏しかったものの、緩和手段が枯渇していたかと言えば、そうではない。「ゼロ金利に到達した後は、量を増やせばいい」という発想は日銀内でも存在していたのだ。
「量的な緩和」は、今でこそリフレ派の専管事項との印象が強いが、90年代後半の時点ですでに思考実験的に議論されていた。かつてドイツ連銀は「マネーサプライ」を重視していたし、80年代前半は日銀も参考にしていた。このため、「金利の次は(マネーサプライなどの)量ではないか」という問題意識を持って日銀取材に当たっていた。
ただ、日銀は実験的な政策には慎重だった。金融危機の直後は「国債買い入れを増やすべき」(幹部)との声も一部にあったが、改正日銀法の施行後は否定的になった。これは説明責任を強く意識し、「効果の不透明な策は取れない」との原理主義に立ち返った面もあるからだ。これ自体は正直さと真面目さの反映だが、事態悪化への予防的な対応はできず、得てして緩和策の発動は後手に回り、まさに「突然」、「180度逆方向に」、「十分な説明もなく決定する」ことになった。
時代を超えた教訓
「中原三原則」の要点は、政策に限界はない、先行きに予断を持たない、悪化には予防的に対応する、とまとめられる。
皮肉なことに、リフレ政策に忠実な量的緩和を断行した黒田日銀が「三原則」に当てはまる豹変を演じた。突然、量的緩和に限界を覚え、それまで否定的だったマイナス金利を十分に説得的な説明もなく、やってしまった。本来なら量の効果を信じ、量的緩和を徹底すれば政策論として新たな次元が開けたかもしれないのだ。この黒田日銀の意味不明の転進は、「中原三原則」が今後も時代を超えて教訓として生き続けることを示唆する。
時事通信社解説委員 窪園博俊

![「コロナの時代」の戦略思考[第8回(完)]「改まる年に向けて」【池内恵】](https://koken-publication.com/wp-content/uploads/2022/12/池内先生-150x150.png)