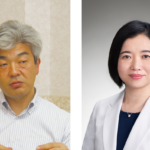『公研』2025年8月号「めいん・すとりいと」
日米に続き、米EU、米韓の間でも関税合意が成立した。また、ベトナム、インドネシア、フィリピンとも合意が成立した。またインドは非関税障壁やロシアとの武器貿易などを理由に25%となった。トランプの「関税劇場」はとりあえず8月1日に発動し、動き始めた。もっともこれらの関税合意は、政治的な合意であり、大枠での合意でしかなく、合意を結んだ当事者の間で様々な解釈の幅を含んだものとなっている。そのため、日米、米EU、米韓ともに合意内容が食い違っていたり、双方の認識に隔たりがあるものが多い。
日米の場合、5500億ドルの投資が合意されたが、日本側は「出資、融資、融資保証」の三つのカテゴリーがあり、赤澤大臣はニュース番組に出演して「出資は全体の2%程度」という説明をしていた。他方、ルトニック商務長官は、テレビ番組で「日本の資金を米国が求める分野に投資し、その利益の90%を米国が得る」と語り、「日本は融資や融資保証というが、米国の指示に基づいて資金を提供する」と説明している。また、日本は米国製自動車に関し、「日本の交通環境においても安全な」車に関しては追加試験がない、と説明しているが、ルトニック商務長官は「米国車が米国の基準をクリアすれば」輸入されるとしている。
通常、関税交渉は双方で誤解のないよう、時間をかけて品目ごとに相互の市場への影響を考慮しながら、国内産業との調整を踏まえつつ進めるものだが、トランプ政権の関税交渉はそうした細部にこだわらず、大枠だけを口頭の交渉で決めるという「バザール交渉」である。バザールでは品物は同じでも交渉次第で価格が変わるが、関税の場合は、様々な産品が対象であり、様々な誤解を生む余地が生まれる。まさに「悪魔は細部に宿る」のだが、すでに執行されている自動車関税を下げることを最優先にするあまり、そうした細部の詰めをしないまま、大枠の合意だけが発表され、それが独り歩きしている状態である。
ただ、興味深いのは、一連の関税交渉を見ていると、トランプ政権の世界観が見えてくるという点である。最初に関税合意を結んだのは英国だが、米国は英国に対して貿易黒字を持っているため、「貿易赤字を解消する」というトランプ関税の目的からすれば、さほど重要性を持たない国である。こうした貿易黒字を持つ相手には、ベースラインの関税率である10%を適用し、それを軸に自動車関税の低関税枠を設定するといったことを行っている。なお、貿易黒字があるとはいえ、トランプ大統領の盟友であるボルソナロ前大統領を起訴したブラジルには50%という懲罰的な関税がかけられている。
他方、米国が貿易赤字を抱える相手である日本やEU、韓国に対しては、「相互関税」という名の一方的な関税も、自動車関税も15%とする、というかたちで決着した。そして、ベトナムなどの東南アジア諸国は、米国からの輸入品に対して関税を0%にするかわりに、米国への輸出品には20%の関税がかけられるということで合意し、中国製品については40%の関税率となるということで合意している。ここから言えることは、トランプ政権の世界観では、貿易黒字相手には10%、工業国には15%、東南アジアなどの新興国には20%という同心円状の関係性が構築されていると言うことである。個別品目ごとの関税ではなく一律関税をかけるのと同様、各国の細かい差異を気にせず、大括りなグループ分けをして、そこに関税をかけるという見方であり、その上で各国との交渉は投資額をつり上げるための交渉がメインになる、ということのように見える。日本は5500億ドルの資金提供となったが、EUは6000億ドルであり、加えて7500億ドルのエネルギー調達も行うこととなっている。
こうした同心円状の世界観にはまらない国が一つだけある。それが中国である。ストックホルムでの会合で34%の追加関税の適用は90日間延期されることが決まったが、米国にとって、中国はレアアースを始め、米国経済の首根っこを掴んでおり、経済的に威圧をかけることができる国である。米中関税交渉の行方を見ることで、米国が中国をどの位置に位置づけるのか。米国は中国の威圧に屈するのか、それとも強気に出てさらなるエスカレーションを招くのか。米中関税交渉を通じて、安全保障を含む地政学的・地経学的な対中戦略の一端が見えてくることになるであろう。東京大学教授