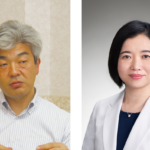隠れ実験で科学の常識をひっくり返す
──なんだか緊張感がありますね。
近藤 日本に帰国後、早速実験の準備です。しかし、そもそも素人がタテジマキンチャクダイを大きくなるまで育てるのが難しいという理由で、何十軒もの熱帯魚店から売ることを断られました。海水魚の飼育技術が今より発達していなかったのです。さらに、お店の人でも「魚の縞模様が動くなんて聞いたことがない」と言うのです。
そんな中でも、唯一売ってくれた熱帯魚店がありました。さらに衝撃的だったのが、その店のおばちゃんが「魚の模様は動くよ」と断言したことです。僕がこれから実証しようとしていることを、当たり前のことのように言ってきたのでなんだか拍子抜けした気持ちにもなりました…(笑)。ともかく、ようやくスタートです。
──孤独な闘いです。
近藤 飼育が始まるともうやるべきことはほぼ終わっています。魚を飼育して大きくなるまでは約1年ほどかかりました。でも、観察を始めてみたら、飽きることもなく毎日が楽しかったですよ。
そして、ようやくその時が来ます。実際にタテジマキンチャクダイのストライプがジッパーのように裂けて動いていったのです。最初は目の錯覚かと思いました。1週間、2週間と時間をかけてゆっくりと模様が動いていったのです(写真3)。
──科学の常識がひっくり返った瞬間ですね。どのような気持ちでしたか?
近藤 模様は動くと信じていましたが、目の前に起きていることが奇跡のように感じました。嬉しさを受け止めきれなくて、誇張でも何でもなく毎晩公園で踊っていました(笑)。頭おかしい人がいたと思われてたかもしれません。
自分の説が正しいことはわかった。次はこれをどこかで発表して他の研究者の反応を知りたいという気持ちが芽生えます。でも、本庶先生にはバレてはいけない…。でも気になる…。危険を承知で分子生物学科会のポスター発表に出すことにしました。
しかし、どんな反応をもらえるのかウキウキで発表の準備をしていたある日のことです。本庶先生に呼び出されます。ついに分子生物学会の要旨集で僕の隠れ実験がバレてしまっていたようです。めちゃくちゃ怒られましたよ。「趣味です」と必死に言い訳をして、免疫の研究にも一層尽力することを誓い、なんとかその場をやり過ごしましたが、生きた心地がしなかったですね。本当に怖かったです(笑)。
「いや、面白いからもう無理です」
──発表の反響はいかがでしたか?
近藤 発表は大成功に終わり、ポスターは常に大勢の人に取り囲まれた状態でした。これはいけると思い論文を書き始めます。絶対に失敗ができないので、わずか2ページの論文を書くのに4カ月もかかりました。もちろん不安もありましたよ。論文が出たら本庶先生にバレることは確実なので、この論文一つで決めなくてはいけない。『Nature』のようなトップジャーナルに載らない限り、この研究を続けることは不可能ですから。
完成した論文を郵便局で送ってから、10日目に返信が来ました。予想外に早い結果にダメかと思いましたが、封を開けてみるとすでに査読も終わっている。さらにはアクセプトすると書いてある。自信は無限にありましたが、びっくりしました。念願の『Nature』の掲載です。さらに驚くことに、僕の論文に関連してその号の表紙をタテジマキンチャクダイの写真が飾ったのです。

──その号を代表する論文ですね。さすがに本庶先生にも趣味とは言い訳できない状況です。
近藤 流石に見つかりました(笑)。本庶先生にこう問い詰められることになります。「魚をやめるか、私の研究室をやめるか選べ」と。事実上のクビ宣言ですよね。でも、私は「魚をやる」と1秒も待たず即答したので、流石に本庶先生もびっくりしていましたね。
僕は『Nature』の表紙を飾ったから、どこかでは研究を続けられると考えていたんです。でも、本庶先生は「魚の縞模様で食っていけるわけがない」と言っていました(笑)。医学者であり、免疫学が発展すれば人々の命を救うことにつながるような、そんな研究の道を歩んできたわけですから、生き物の模様は本庶先生にとっては道楽にしか見えなくてしかたないですよね。
そんな状況でも本庶先生は僕の研究者人生を心配してくれたようで、「ここを辞めてどうするんだ?」「君な、うちにおったら京大の医学部の教授になる道はちゃんとつくってやれるんや」と。でも僕としては「いや、面白いからもう無理です」と答えるしかなくて。そんなやりとりをしたこともありました。
しかもそのとき私は、「さきがけ」という若手研究者支援制度に応募していました。3年間の期限付きですが給料も出る制度です。なので、「さきがけが雇ってくれるから大丈夫です」と謎の自信があったのです。でも、実はその時はただ応募した段階で面接にすら進んでなかった。しかも、競争率は19倍ほどです。

──安定した研究人生を蹴って、大きな挑戦です。
近藤 多分大丈夫だろうって思っていたんですよね。こんなに面白いものは他にないと確信していましたから。
その後、さきがけから連絡がきて、本庶先生と話をした約1週間後に、東京の面接に行きます。受かる自信はありましたが無職になったら困るので、「落としやがったら首絞めたるぞ!」という意気込みで向かいましたね(笑)。
審査員も錚々たるメンバーです。その一人が本庶先生の友人でもある中西重忠先生(京都大学名誉教授:分子生物学者)でしたが、中西先生にも「君は本庶のところの講師なんだからこんなことできるわけないだろう」と言うんです。でも私は「先週辞めてきました」と。びっくりしていましたね。
最終的に「さきがけ」でも領域代表をしていた豊島健先生という癌学会の超大物が、京都の本庶先生に会いに行き、「近藤は俺が預かる」といったようなやり取りがなされたそうです(笑)。僕はめでたく、1997年徳島大学総合科学部教授となりました。
──近藤先生の研究人生は、平たんではないですね。
近藤 もし自分の息子が同じことしてたら「バカなことするな」と言うと思います。
──その後の本庶先生とのご関係は?
近藤 本庶先生は立場上、私の研究を認めることはできないにもかかわらず、研究室の廊下に僕のタテジマキンチャクダイの写真が表紙になった『Nature』 の論文をずっと額に入れて飾っておいてくれたんです。「さすが懐が深い」としか言えませんね。
細胞同士が会話をして模様をつくる?
──徳島大学ではどのような研究を?
近藤 タテジマキンチャクダイで「模様はチューリング波で説明できる」ということは示せましたが、「では実際に何がその波をつくっているのか?」という問いが残っていました。そこを突き止めないと、生物学の人たちはなかなか納得してくれないんです。
そこでゼブラフィッシュ(写真4)を使った研究をしました。この魚は黄色と黒のストライプ柄の魚なのですが、黄色い細胞と黒い細胞が互いにやり取りしながら配置を決め、それによって縞模様ができていることを証明しました。

──細胞同士がコミュニケーションをとって自発的に動いているということでしょうか?
近藤 そう考えてもらって問題ありません。
チューリング理論についてもう少し詳しく説明しますね。チューリング理論では、生き物の体に現れる縞や斑点などの空間パターンは、「活性因子」と「抑制因子」という二つの要素のバランスによって生まれると説明されます。簡単に説明すると、活性因子は「自分と同じものを増やそう」と働き、抑制因子は「近すぎると打ち消そう」と働く。そのせめぎ合いが波を生み、パターンが自然に立ち上がるのです。
ゼブラフィッシュを調べてみると、活性因子と抑制因子の関係が、まさに黒い細胞と黄色い細胞の間で起きていることがわかります。ある意味、オセロの石のように、近づきすぎると互いを押し合ってひっくり返す。でも少し離れると、今度は相手を支え合う。まるで細胞同士が「ここにいよう」「もう少し離れよう」とコミュニケーションをとりながら自発的に動いているように見えるのです。
つまり、簡単に言うと近距離では抑制し合い、遠距離では促進し合う。この二つの力のバランスこそが、全体として均一なストライプのパターンをつくり出していた。そしてこれは、チューリング理論が予言した「活性因子と抑制因子の拡散スケールの違い」とぴったり対応していることを、生き物の中で実証できたわけです。
動物の様々な柄は本質的には全て同じ
──では、生き物の模様の多くはチューリング波で説明できるのに、なぜこれほど多様なのでしょうか?
近藤 同じチューリングパターンでも、抑制因子と活性因子の強さのバランス次第で模様の見え方が変わるんです。お互いにやりあって一番安定したバランスが模様として出てきます。
例えば、黒の細胞が強ければ黒の領地が増えて、黒地に黄色の斑点ができるし、逆に黄色が強ければ黄色地に黒の斑点になる。一方で、強さが拮抗してちょうどいいバランスのときにストライプができる。だから、斑点とストライプは別物に見えても、実は同じ波の断面を見ているようなものなんですよ。人間が勝手に「斑点」「ストライプ」と呼び分けているだけで、本質的には同じなんです。
それから「最初の種」がどこにできるかも、模様を決める大きな要素です。ゼブラフィッシュだと体側の側線に色素細胞が最初に並ぶので、そこから波が広がり縞になる。でもナポレオンフィッシュのように最初の種がない場合は、不規則なパターンになります。いろんな魚を観察したら、種がここにあるなってわかると思いますよ。
他にも、キリンやヒョウの斑点模様は、成長の途中で波が一度止まったり再開したりすることでできていると考えられます。
──波が止まることもあるのですか⁉
近藤 そうです。キリンの場合、最初に斑点ができます。でも途中で波が一度止まるんです。そのまま体が大きくなると、斑点と斑点の間がだんだん広がっていく。そして、その状態でもう一度波が走り出すと、あのキリン特有の網目模様になるんですよ。あれは波の跡なのです。なので大人の模様は動きません。
どうして止まるのか、どういうきっかけで再開するのかはまだよくわかっていません。もしキリンを実験に使えるなら解明できるのでしょうが、不可能ですからね。
シマウマの縦じまに絶対的な意味はない
──動物の模様は、例えば「捕食者から見つかりにくくなるため」といった何かしらの意味や役割を期待してしまいます。
近藤 波は物理現象として自然にできてしまうものです。波の存在自体に意味はありません。生物学ではどうしても「この柄は何の役に立つのか」と考えがちですが、それは「どうやってできたか」とは別の話です。僕の研究はまさに「意味ではなく、どうつくられるか」なのです。
たとえばシマウマと馬はよく似た動物でも模様はバラバラです。シマウマの縦じまはサバンナの草むらに隠れるため、と意味づけされることがありますが、他方で似た生き物の馬は模様がなくても生きていける。つまり、模様はあってもなくても生存に致命的な差はない。もし模様に絶対的な意味があるのなら、一種類に収束しているはずです。
だから模様は「役に立つからある」というより、「物理の原理で自然に生まれる」ものなんです。結果的に意味を持つ場合もあるかもしれませんが、模様をつくる仕組みそのものとは関係がない。僕にとって重要なのはなぜその模様ができるのかという点であって、その模様が何の役に立つのかではないのです。
──葉っぱに擬態する昆虫もいます。結果的にたまたまあの姿になったということでしょうか?
近藤 そうです。擬態という言葉が誤解を招きますが、昆虫が葉っぱに似せようとしたわけではありません。たまたま葉っぱに似た形の個体が生まれ、それが環境の中で有利だったから生き残った。進化とはそういう偶然の積み重ねです。最初にランダムにいろんな形が生まれ、その中で環境に適したものが残っていく。だから「どうやって形ができるか」という原理と、「その形にどんな意味があるか」という用途は、必ずしも直接つながってはいないのです。
──チューリング波は、生き物の模様だけでなく、形の形成にも関わっているのでしょうか。
近藤 もちろんです。アラン・チューリング自身も、この波は模様にとどまらず、生き物の形づくりにも効いていると考えていました。
たとえば人の手です。胎児のとき、最初は指のないヒラメみたいな形をしているのですが、そこから指ができていく。その数や配置はチューリング波のパターンで説明できることが、シミュレーションや実験で示されています。波のピークのところが指になるんですね。指紋もチューリングパターンで説明できます。
──チューリング波は、生き物の形をつくる「一要素」と考えればよいのでしょうか。
近藤 そうです。でも、かなり大きな一要素ですね。というか、何もないところから形を生み出すときには、基本的にチューリング波に似た原理が必ず出てきます。だから、生き物の形をつくる一番重要な原理だと言ってよいです。
今はもう、「チューリング波がある」というのはこの分野の研究者にとっては当然の前提になっていて、その上で形態形成をどう説明するか、という研究段階に入っています。だったらもう、私自身がそこに関わり続けなくてもいいなと思いました。