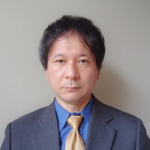謎解きの舞台は科学からアートへ
──だから先生はチューリング波に限らず幅広い研究テーマを扱っているのですね。
近藤 そうですね。最近まではカブトムシの角や貝殻など、多種多様な対象を研究してきました。
そんな中、昨年4月ごろ定年で研究室を1年後に閉じることが決まります。新しい研究テーマを立ち上げる余裕もなく、頭が少し空白になってしまったんです。そんなとき、昔から気になっていたエッシャーの絵を思い出しました。
──だまし絵のエッシャーですね。階段がどこまでも続くように見える絵などが有名です。これまでの研究とはまったく異なる分野です。
近藤 子どもの頃に、少年誌の表紙でエッシャーの絵を見たことがあって、「なんでこんなふうに見えるんだろう」と、不思議でしかたなかったんです。その感覚がずっと心に残っていたんでしょうね。
じゃあ今なら時間もあるし研究してみようと始めてみたら、これが本当に面白かった。エッシャーはただ奇抜なだまし絵を描いたのでなくて、光の当たり方や影の落ち方、人物の配置まで、ものすごく論理的に考えて描いている。だからこっちも論理的に考えると、ちゃんと答えが出るんです。鑑賞というより、まさに「謎解き」ですね。気づいたときには「やられた!」って、まんまと騙された自分に笑ってしまいます。これが楽しくて、どんどん読み解いていきました。
──それが発展して、昨年12月には『エッシャー完全解読 なぜ不可能が可能に見えるのか』を上梓されています。ご著書を読んでここまで多くのヒントや仕掛けが隠されていることに驚きました。
近藤 びっくりしたでしょ?僕も自分で驚きました。エッシャー自身、「自分は芸術家じゃなくてクラフトマンだ」と言ってますが、ほんとその通りで、すごく理屈で仕掛けを組んでいるんです。適当に描いた絵からは理屈なんて出てきませんからね。
──まさに研究にも通じる「謎解き」ですね。
近藤 そうなのです。謎が解けたときは、本当に爽快でしたね。研究しかり、何か謎を解き続けていたい性分なのかもしれません。
──ありがとうございました。
聞き手 本誌:薮 桃加