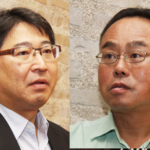『公研』2019年6月号「interview」
小林 亮介・HLAB代表
日本の若者は、「人付き合いが苦手」とか「海外に出たがらない」と指摘されて久しい。そんな昨今において、国内外の高校・大学生を集め、合宿を中心とした交流によって学びを場を提供している若者がいる。何がこの発想のきっかけとなったのだろうか。
寄付は戦略的に集めるもの
 ──「社会起業家」と紹介されることが多いですが、世の中に対して疑問や憤りを感じた最初の出来事は?
──「社会起業家」と紹介されることが多いですが、世の中に対して疑問や憤りを感じた最初の出来事は?
小林 小学校5年生のときに起きた9・11とそれに続くアフガニスタン戦争、イラク戦争は衝撃的でした。テロはもちろん、戦争を起こして人を殺すことの正当性の議論は、子どもの目線にもロジックが破綻していると思えました。漠然と、戦争を終わらせるためであっても、報復行動には違和感を感じたのを覚えています。アメリカの態度の背景には何があるのだろうと考えるようになりましたね。それ以前は、幼い頃から横田基地の存在が気になっていました。母方の祖父母が青梅に住んでいましたから、そこに行くときに必ず横田基地の下をくぐる。「なんでこんなところにアメリカの基地があるのだろう」とずっと疑問に思っていました。
──何でも「知っているよ」という感じの小学生だった?
小林 「知っているよ」と言いたいところはあったのでしょうね。でも、そういう時には父は「甘い」と指摘して、考えるさせる人でした。「問題というのは、課題に分割してそれを一つひとつ解いていくことだ」と。論理が通りにくいことには感情的になりがちですが、「感情に訴えかけてはダメだ」と繰り返し言われましたね。
──お父様はどんな方なのですか。
小林 早稲田大学の理工学部で教授をしています。今で言うAI(人工知能)が専門で、音声認識、画像処理、自然言語処理などについて研究しているようです。僕も数学や物理が好きでしたが、父と一緒に数学の問題を解いたりすると、初見の問題でも構造をサクサクサクと掴んで解答へ導いていく。それを見ていて、とても勝てる気がしなかった。単純に僕よりも楽しんでいるな、と感じて同じ分野に進もうとは考えなくなりました。それで歴史や社会科学系の学問に関心が向いていったところがありましたね。
──高校時代にアメリカに留学されていますね。
小林 オレゴン州です。ポートランドから、車で北に3、40分行ったところにある5000人くらいしか住んでいない田舎町です。留学で鍛えられたのは、英語力よりも精神力でした。ビザを取ってくれたり、生活の世話をしてくれたりする団体が、日本を出発する数日前に「ホストファミリーを見つけられなかった」と連絡してきたんです。
──そんなことがあるんですね。
小林 僕もびっくりしました。一時的なステイ先は決まっていましたが、そこにはお子さんがいなかった。学校になじむうえでも子どもがいる家庭のほうがいいだろうと考えて、ホストファミリーを自身で探していました。けれども結局、ホストファミリーが3度も変わることになりました。僕も疲れてしまってステイ先と揉めたりして、次第に引きこもりがちになったんです。不良生徒ですね。留学団体も「日本に送り返すか」という話になりかけた。ところが、通っている高校の先生と同級生たちが、団体に対して抗議の手紙や、「留学を続けさせるべきだ」という嘆願書を提出してくれたんです。小さな街だからこの騒動が知れ渡って10家族くらいが「ホストをしたい」と受けて入れてくれることになって、残りの期間は充実した毎日を送ることができた。英語よりも、精神的に成長した一年でした。
──一橋大学に現役で入学していますが、すぐにハーバード大学に移られている。
小林 アメリカの大学は9月入学ですから、ハーバードの合否を待ってからでは一橋の入学に間に合わない。それで一橋に入学しました。知り合いにアメリカの大学を受けている人はいませんでしたし、情報もほとんどなかったからハーバード受験は本当に暗中模索でした。合格率も奨学金をもらえるかどうかもわからなかった。ただ高校時代、一橋の副学長だった大芝亮先生に相談したことがあったんです。二つの国際関係論の論文を「バン!」という感じで置かれました(笑)。日本語の論文と英語で書かれたアメリカの学者の論文です。「両方を読めば、どちらのレベルが高いのか、すぐにわかるはずだ」と。大芝先生ご自身もイェール大学のご出身でしたから、暗にハーバード進学を薦められていたのだと思います。そもそも世界で読まれている国際関係の論文には、日本の学者のものはほとんどなかった。合格通知が届いてからもかなり迷ったんですが、「チャンスがあるのであれば、早くいってこい。ダメだったら戻してやる」ともおっしゃっていただいたので、一橋は中退して秋からハーバードに進むことを決めました。
──アメリカの名門大学はものすごく学費が高いのでは?
小林 ハーバードの学費は年間700万円と言われていますが、僕は全額免除で奨学金もいただいていたので寮費に関しても実質的にはタダでした。いま世界のトップレベルの大学について言えば、留学生を除いて、その多くで家庭の年収に応じた奨学金が付与されています。こうしたトップレベルの大学は、日本の大学とはビジネスモデルが根本的に違うのです。
ハーバードは大学への寄付金からなる基金が3・7兆円積み上がっています。この基金を卒業生を中心とした優秀なファンドマネジャーがファンドにばらして約8%運用しています。つまりウォールストリートに送り出して、ノウハウを得た卒業生を母校に引き戻して、その基金を有効に運用させているわけです。8%運用ですから、毎年3000億円の実質的なフリーキャッシュフローを金融事業から得ることになります。学部生は1学年だいたい1600人ですが、卒業生の1人でも大成功して、1回300億円の寄付が入れば、それが毎年24億円を作り出すことになる。
大学側はそうした寄付を集めることをビジネスの前提に、学部生の顧客体験を戦略的に作り込みます。多くの学生は、学費は全額免除されて奨学金も得ています。それに全寮制で濃密な生活を送りますから、みんな大学には感謝しています。もし自分が成功した暁には、母校に寄付したいと、自然と考えます。
卒業後も大学生活という顧客体験を定期的に想起させる工夫がされていて、大学時代を想起させるメッセージを個別に毎年送ってよこすのです。そこでも寄付を募ります。ファンドレイズ・パーティーとなれば、世界を学長が回って、一度のパーティーに巨額の投資をする。学生への先行投資で顧客体験を作り、寄付金として最終的に回収する。それは30年後だったりして、とても期間の長いビジネスを行っているわけです。
卒業生オフィスなど、寄付を戦略的に狙いにいくことを担う部門に人材を厚く投入して、投資している。だから、「ハーバードは寄付が集まっていいですね」という感想は本質を見誤っていて、最初から授業料や受験料として教育の対価を求めるのではなく、数十年後の寄付を集めるというビジネスのゲームをプレイしているわけです。日本の大学では東京大学や慶應義塾大学くらいのサイズの大学でも十分な規模の基金がなく、同様の経営を行っているのは国際基督教大学くらいかと思います。
「大学での大半の学びは寮生活にあった」
──ハーバードの寮生活の様子をお聞かせください。
小林 家庭から離れて大学がどういう場所なのかみんな知らない中で、寮に放り込まれます。寮での生活を通じて、ルームメイトとは苦楽を共にした、同じ釜の飯を食べる仲間になります。深夜3時まで僕が日本語で愚痴っているのを聞いてくれるような信頼関係を築くことができた。やはり、授業だけで出会う希薄な関係とは圧倒的に違う。
寮での暮らしを思い出すと、まず浮かんでくるのが食堂です。1年生は1600人全員が同じ食堂で食事をとるんです。2年生以降の寮は食堂の前を通らなければ出入りできないつくりになっていて、そこには誰かしらがいます。24時間開放されていますからね。僕が外出先から帰ってきて自室に向おうとすると、そこで必ず捕まるんです。「リョウスケ! お前は課題をやるんだろ。エッセイはここで一緒に書いたらいい」って。
そこでは、みんながまったくの無言でそれぞれの宿題なりに深夜まで取り組みます。ドリンクメーカーやコーヒーマシンがあるから、部屋でやるよりも楽なんです。ふと2時くらいに集中力が途切れたときに、バカ話がはじまったり、それぞれが興味を持っているテーマなりを話し込んだりします。ここでの会話こそが大学生活で最も大事な学びの瞬間だと僕は考えていて、多くの同級生も「大学での大半の学びは寮生活にあった」と口を揃えます。
先輩の例で言えば、こうしたやり取りのなかから生まれてきたのが映画『セッション』や『ラ・ラ・ランド』だったりします。あの作品の映画監督と音楽監督は僕と同じ寮の先輩で、ルームメイトでした。それから、数学専攻、経済学でビジネス、コンピューターサイエンスをやっていた人がたまたま同じ空間にいて、むかついたからという理由で女の子を顔だけでランキングするウェブサイトをつくってみたりする。『ソーシャル・ネットワーク』のワンシーンですが、彼らがFacebookを立ち上げることになったのは有名です。寮生活を共にする中で日常に生まれる、多様な人との接点や対話は、実際の作品や会社の設立、学問の探求につながることは珍しくないんです。
──多彩な人材が同居している。
小林 日本人だけを見ても、僕の二つ上の代にはプロバイオリニストの五嶋龍さん、Googleのエンジニアでありながらプロの指揮者でもあるユーガ・コーラー(高橋遊河)さん、後輩にはプロのサッカー選手になって今はアナリストをしている小林寛生さんなどがいました。正直、「そんなこと可能なのか」というキャリアですよね。僕がいた寮には、かつてビル・ゲイツがマイクロソフトをつくったという部屋もあるんです。「多様な才能が集まっていることはすごく楽しいよね」という雰囲気があって、お互いから学ぶという意識があります。
入学させる人を審査するアドミッションズもいかに多様な人材を入学させるかを重視しています。それに、どの寮に振り分けられるかわからない「ブロッキング」と呼ばれる仕組みがあって、自分たちで勝手に固まれないようになっています。ハーバードで強く感じたのは、学びが起こるうえでは、「共通項」と「違い」が必要だということです。なんらかの共通項、例えば同級生であることなどがあり、腹を割って話せる友人になる。その上で、お互いの経験や考え方の違いを理解しようとする。本当の学びは、そこにあるのだと思うんです。もちろん、それぞれの価値観は違うから、揉めることになる。違いは論争の元でもあるのだけど、そこに信頼関係があれば、いい意味での議論になります。信頼関係がなく作法もわかっていなければ、ただの感情的な水掛け論で終わってしまいます。
いまリベラルアーツ教育の重要性が盛んに叫ばれていて、日本ではすぐ幅広い科目の授業という話になりますが、本質的なリベラルアーツは、世代や分野を超えた、多様な人からの学びだと僕は思っています。教科も重要ですが、その前に一人ひとりの教授や学生を含めて、自分自身が今後の人生を歩んでいくうえでの指針になったり、ロールモデルになったりしてくれる人との出会いこそが大事だと考えています。ハーバードは寮生活を通じて、そういう関係をつくっていくためのトレーニングを若いときからさせてくれるわけです。レジデンシャル(学生寮)教育の根幹は、ここにあるのだと思います。
──お話を伺って個人的に連想したのが、山歩きの仲間ですね。
小林 似た側面があると思いますね。山歩きの仲間は、勉強しているやつも麻雀やアルバイトばかりしているやつもいます。いろいろな考え方をする人たちが、山歩きが好きだということで集っています。実際の山歩きでは、かなり長い時間を一緒に過ごしますが、大部分の歩いている時間は沈黙していますよね。けれども、その沈黙の時間が心地よいかたちとしてずっと流れているのだと思います。そして、登山を終えて、仲間と温泉に入って「ふー」と一息ついているときに「ああ、なるほどな」と思えるような会話のやりとりや人生に影響を与える一言が出てくるのだと思います。そういう言葉が出てくる可能性は、0・001%くらいだし、ある人にとっては何の意味も持たなかったりします。その瞬間でなければ、学びにはつながらないかもしれない。けれども、確率が低いからこそ、意味もなく多様な人たちが一緒に過ごす時間をなるべく長く設けておかなければ、そういう学びは決して生まれてこない。寮生活の設計思想はここにあります。
日本人は多様性から学ぶ訓練をあまり受けていない
──日本にも寮はありますが、どう違うのでしょうか。
小林 日本の寮の場合は、どうしても画一化してしまう傾向がありますよね。サッカー部にしても野球部にしても、それぞれの寮があって彼らだけで暮らしていたりする。大学によっては、留学生だけを住まわせたりしています。社会人になれば、会社ごとの寮がある。寮に限らず、教育の制度面で見ても、似たマインドセットを持った親に育てられた子どもたちが中高一貫の進学校に進んで、6年間かけて純粋培養されてしまう。そうすると、同じような価値観の人たちが受験を勝ち抜いて、東大に進学したりする。だから、サイロ化がとても早いタイミングで起こっているんです。彼らは、話は合うと思うんですよ。例えば、官僚の友人の中には高校時代のことで盛り上がったり、大学受験の話を未だに楽しそうにしゃべったりすることもありますよね。こういう話題は共通項だから話が弾むわけですが、共通性を確認することに留まっていて多様性から学ぶ訓練をそれほど受けていないこともあり、お互いの違いを認識し学ぶ機会は少ないように感じられます。
──日本ではエリートほど同質的になりがちだと。
小林 いまレジデンシャル教育を重視するのは世界の潮流になっていて、大学ランキングのベスト20のうち東大を除いた18─19の大学は基本的に全寮制です。重要なのは、アメリカやイギリスでは寮での生活を大学側がかなり力を入れて設計していることです。今はレジデンシャル教育自体が大学の価値になって、創造性を生み出す場になっているわけです。一方、日本の大学の寮やサークルは、基本的には自発的な運営になっています。京都大学の吉田寮のことをカリキュラムとは呼びませんよね(笑)。
この背景にはデジタル化の進展があります。メディアと教育は構造が似ているところがあります。メディアはAがBに情報を届けて、BがAに購読料を払うわけですが、教育業界の場合はこの購読料が授業料になっているわけです。デジタル化は、情報をN+1人目に伝えるコストを飛躍的に下げました。それによって、情報が溢れるようになった。こうして、情報自体の価値や受け取れる対価はゼロに近づいてきました。
同じように大学での講義や授業の価値もゼロに近づいています。こうした状況を反映して、いま世界中の一流大学が授業を無料で公開し始めています。オンラインに最適化されていて、実質的にゼロ円で講義を受けることができる。だからと言って授業に価値がないわけではなくて、その情報は大学の価値であると同時に公共財として世界で共有すべきだと考えているわけです。だから、そこではお金を取らないと。それでは、誰も大学に通わなくなるのかと言えば、そうではなくて、そこで過ごす時間や仲間との学びこそに価値があるわけです。
いまレジデンシャル教育を柱に据えて、大学を立て直そうという動きが世界中で起きています。世界中の名門大学が意図を持たせて寮を設置している。ハーバードも史上最大のファンドレイジング・キャンペーンを張って、より対話が生まれる寮の建て替えを行っています。
カレッジは一緒に住むことでお互いから学び合う空間
──日本では大学の寮と言うと、学生運動時代のネガティブなイメージが残っているように思います。
小林 ハーバードでもそういう勢力の巣窟になってしまったことがあり、1970年代以降の新しい寮は生徒が立て籠れるスペースを排除する設計になったこともあったようですが、今は変わりつつある。日本は、レジデンシャル教育やボーディング・スクール(寄宿学校)の概念は希薄ですね。寮と言えば、学生たちに公平に学べるよう、安価で住む場所を提供しようとか、住むところがない留学生に提供しようという発想だったりします。多様性が新たな学びをもたらすという考え方に立てば、留学生だけで住まわせるのは、彼らにとっても日本の学生にとっても勿体ないですよね。
そもそもカレッジは、一緒に住むことによってお互いから学び合う教育空間です。大学の歴史を遡るとヨーロッパの修道院にその起源があって、建築様式にしてもその影響を受けています。街の人たちが公に集まって一緒に話し合うことが目的の場であるとともに、そこは修道士たちが生活する場でもありました。プライベートとパブリックが隣接している。それが神学校に発展していって、大学の寮ができた。
イギリス起源のユニバーシティとカレッジは、日本では両方とも「大学」と訳されますが、ユニバーシティは総合大学であり研究機関です。そして、そこに紐づいているカレッジは教育機関です。教授と学生が寝食を共にしながら教育するのがカレッジの定義だったわけです。これがアメリカに輸出されたときにその役割分担が変わります。カレッジで教えている先生は、ユニバーシティの研究者でもあります。けれども学生は、自分のカレッジに所属している先生にしか付くことができなかった。それは効率的ではないという話になりました。それで、教える機能(teach)はユニバーシティのほうに持たせて、その代わりカレッジを「ハウス」という名前に変えて、寮として学生がお互いから学び合う機能だけを残したという経緯があります。
それがデジタル化の進展と共に情報自体が公共化されてきたので、教育の中心はやはりカレッジであることが再認識されるようになっています。一緒に住んで学んで教えることを重視するように移りつつあるわけです。新しい流れというより原点回帰とも言えます。
──ハーバードは寮生活でこそ学びがあるのはわかりますが、その成果について明確な方向性はあるのでしょうか。
小林 専門性を鍛えることが主眼ではなくて、一生学び続けていくうえでの根幹となる作法やスタイルを学ぶということなのだと思います。自分と違う人たちがいたときに、彼らの才能をどう活かすか。自分にとってどのように役立てていくのか。自分が相手にどう役に立つのか。
今の時代は、一つの会社でのみ通用するような考え方ではダメなのだと思います。特定の業界に所属していたとしても、パブリック(公)とプライベート(私)の橋渡しをする存在であることが求められています。そのためには、それぞれのセクターを理解できなければならない。つまり、企業はこういうインセンティブ構造で動いているが、官僚組織はまったく違うとか。政治という側面が入ってくると、代議士は有権者の存在を意識していて、彼らの声を聞かなければならないとか。
いま求められているのは、それぞれのセクターがお互いの言語やインセンティブ、考えていることを「なるほどな」と理解しながら、同じ方向を向かせることができるような知恵なのだと思います。これは「トライセクター・リーダーシップ」とも言われます。きれいにまとめ過ぎていますが、大学の日々の生活のなかからそれを学ばせていくのがリベラルアーツ教育の目的なのだと思うんです。
その根幹を成している機能の一つが寮という空間です。本来はまったく接点がないはずの学生たちも、人間が必ず行う「寝る」ことと「食べる」ことは共にする。その偶然の出会いから、学びが生まれる。ただそれだけの発想ですが、そうした人材を育てるための作法を学ぶのに重要な要素が寮生活にはあります。
──現在もハーバード在学中に立ち上げられたHLABの代表を務めていますが、就職という選択肢はなかった?
小林 日本と海外の橋渡しをする仕事をやりたいとずっとイメージしていました。そうすると、外交官やジャーナリストなんかが単純に仕事の名前としてそれっぽいなと。ところが、実際にケネディスクールやタフツ大学のフレッチャースクールにマスターで来ている外交官に友人ができて、話を聞いたりするうちに自分には合わないのではないかと感じるようになりました。外交官や国際機関の職員は、時の政権の方針に反する主張はできないし、しっかりと粛々と効率的に仕事をこなさなければならない。調整能力も求められますが、それは自分のキャラクターには合っていないと考えるようになりました。
僕が一番お世話になったメンター(先輩)にハーバード・ビジネス・スクールの竹内弘高先生がいますが、ハーバードきっての講演の名手なんです。日本語でも英語でも数百人規模の聴衆を巻き込む面白い講演ができる。先生も外交官なりを考えていましたが、奥さんに「それは違うのでは」と指摘されて結果的にハーバード・ビジネス・スクールの教壇に立つ選択をされました。そして、日本の経営界と世界の経営界を繫げる仕事をされています。そういう話を聞いて、個人として国際関係に関わる仕事にもいろいろなやり方があるなと思いました。それで現時点でできるベストを実践していこうと考えて、今に至っている感じですね。
短期間の合宿で寮生活を再現したサマースクール
──HLABを設立した動機と取り組みは?
小林 お話ししてきた寮での生活は、僕にとっては大きな意味がありましたから、これを日本に持っていきたいなという発想がありました。けれども、いきなり学校をつくったり、寮を建設したりするわけにはいきません。何十億円も必要になりますからね。それで考えたのが、短期間の合宿で寮生活を再現するサマースクールです。これならば1000万円ちょっとで何とかなりますから、可能かなという話になって20歳のときにHLABを設立しました。仲間も含めていろいろなところから資金を掻き集めて、最初のサマースクールを開いたのが2011年のことでした。
この時に考えたのが3年前の自分たちにメッセージを送るということでした。自分たちがいま大学生として一番貢献できるのは、一世代下の学生たちに自分たちの後悔を伝えることができる環境をつくってやることではないかと。
せっかく世代間でやるのであれば、国籍もなるべく多様化していろいろな世界を知ることができたほうが楽しいと考えて、今では世界中から200人くらいの大学生と240人の高校生を集めて、ほぼ1対1の2週間の泊まり込み合宿を行っています。毎年夏の終わりに東京、長野県小布施町、宮城県女川町、徳島県牟岐町の4カ所で開かれています。
──外国からの参加者を募ることには苦労されたのでは。
小林 最初はハーバードの同級生たちに声をかけて震災直後の日本を訪れてもらった。だから、HLABのHはハーバードと勘違いされやすいのですが、House(寮)やHub(交流のハブ)を意味しています。最初の参加者から、近隣のウェルズリー、MIT(マサチューセッツ工科大学)などにも口コミで広がっていきました。最初はWEBサイトもなかったんですが、世界中の大学から参加者がやってくるようになりました。
サマースクールに参加した高校生の中には、海外の有名大学に進学する人もたくさんいますが、別に海外に送ること自体が目的ではないので、そこにはこだわっていないし、その数字も出していません。このプロジェクトの特色は、合宿に参加した日々だけに意味があるのではなくて、その後も関係が継続されることにあると思っています。だから、5年後、10年後に同窓会を開いたときにどれだけの人が参加してくれるのか、その出席率にはこだわりたいと思っています。彼らがその後も何らかのかたちで繫がっていればやって来るし、疎外感を覚えていれば来ません。ハーバードの卒業5周年の同窓会は、4日間も過ごして参加費も10万円くらいするんです。みんな働いていますから、わざわざボストンまで行くことはたいへんだったりしますが、1600人中1200人程度、75%が集まりました。
HLABがめざしているのもそういうことです。参加者たちがお互いに学び合う関係を構築できれば、サマースクールで出会った人たちと事業を始めることもあるでしょう。たまに会ってお酒を飲んで話をするだけでもいいから、何らかの関係が継続していることを期待しています。それぞれが当時の自分たち以上に成長していると仮定すると、学びは年齢を増すと共にもっと大きくなっているはずです。
──今後の展開についてお聞かせください。
小林 サマースクールを8年間事業としてやってきたノウハウを活かして、新しい取り組みがいくつか進行しています。小田急線下北沢駅の複々線化に伴って線路が地下に潜りましたから、その上がガラ空きになりました。そこの土地を使って我々と小田急電鉄、まちづくりをしているUDSと共同で、高校生・大学生・社会人が同居する居住型の教育機関をつくっています。ここでは授業以外のすべてを提供することがコンセプトになっています。2020年夏に竣工し、21年には開校する予定です。もっと範囲を広げて街づくりなどにも携わっていく計画が始まっています。
──最後に小林さんの世代の日本社会への意識について思うところがあれば、お聞かせください。
小林 我々の世代は危機意識が低いと感じることはありますね。財政にしても社会保障にしても問題は山積していますが、そこに対しては無自覚なところがある。そもそも、そういうことを語る人は浮いてしまうし、気軽に語ることができる場所もないわけですよね。就職してしまえば、日々忙しくて余計に考える時間が奪われて、視野が狭くなってしまう。それでも、物理的な場を設けて、討論することは必要だろうと思います。オンライン空間ではそうした議論が行われているようにも見えますが、不毛なものに堕することが多いですよね。
僕が違和感を覚えているのは、テレビに出てくるような社会的に発信力のある若手の人たちが非常に個人主義的なことです。個人としていかに豊かに生きるかというところに入りがちで、「こうして自分は幸せになった」とか「副業で稼いでいる」とか、そんな話ばかりになってしまう。そんな強者の生き方の話よりも、よりマクロな、社会全体が幸せになれる仕組みについて語って欲しい。僕自身もそういう意識を持って、大局的に世の中を見ることが必要だろうと考えています。聞き手 本誌・橋本 淳一