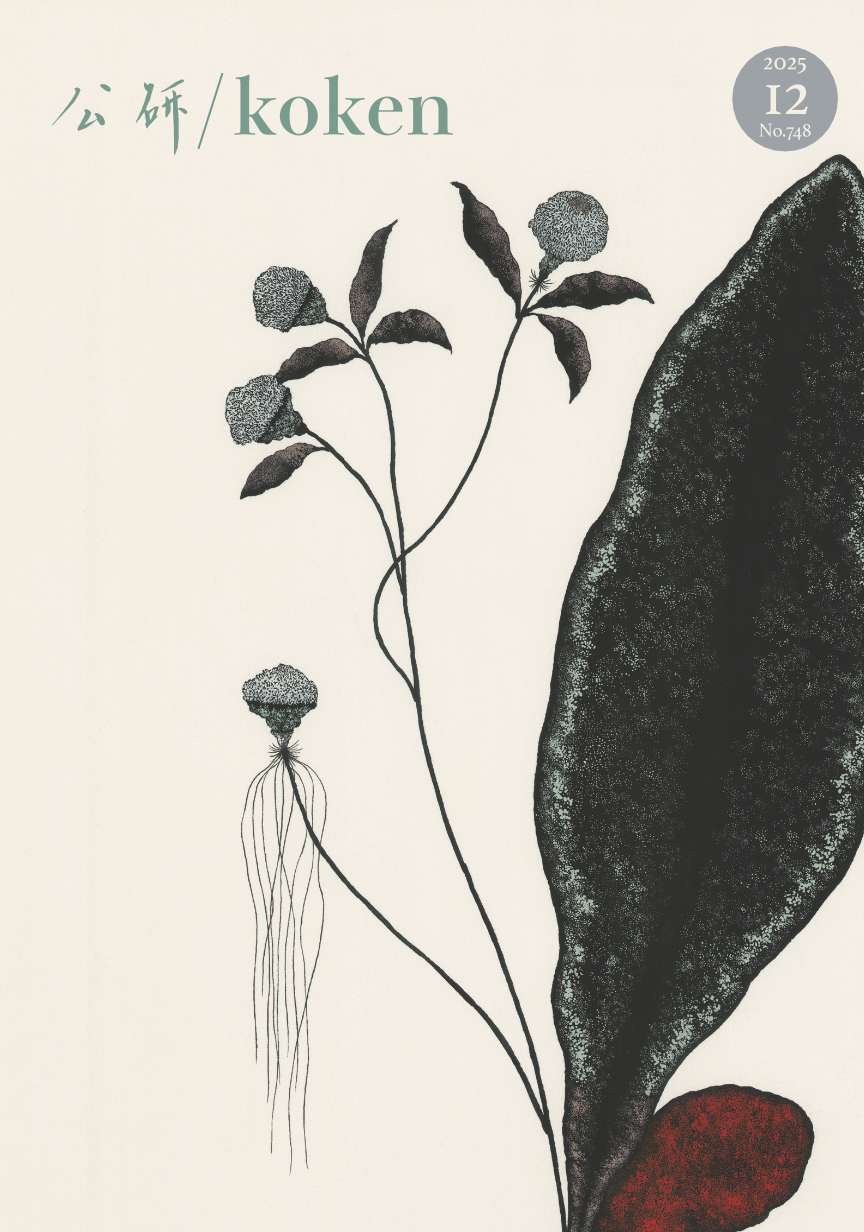なぜ的外れな政策が出るのか
編集部 女性の経済的な自立や、労働環境の問題が出産への気持ちに直結していることは、すでに実証されている。それにも関わらず、なぜ政策に活かされず、的外れな政策が出ているのでしょうか。
牧野 政策に活かされないのは、政策を決定している人たちの思い込みがアップデートされていないから、もしくは意図的にアップデートしていないからだと思います。例えば、先ほどお話した女性の社会進出が少子化に結びついているという思い込み。2000年ごろを境に、先進国では女性の社会進出が進んでいる国ほど、むしろ少子化の深刻さは緩和されている。この程度の知識はトレンドとして押さえておくべきでしょう。
また、「3歳児神話」も神話にすぎないと実証されているのに「3年間抱っこし放題」といった政策案が出てきています。もしそれを導入すれば、大して効果がないにもかかわらず、育休中の社会保険料免除や給付の財源に充てられる、国民が支払う保険料や税金の無駄遣いでしょう。このような実証研究の成果をアップデートすることは重要です。アップデートがされるように、私たち研究者や発信する側も、伝え続けていくしかないと感じています。
もう一つ、少子化政策を考えるうえで経済学から得られるヒントがあります。人間は常に「どちらが得か」を考えて行動する生き物だと前提に考えることです。
サブサハラ・アフリカ諸国では「貧しいから避妊具が買えない」と考え、コンドームを無償・割引配布する政策が行われてきました。しかし出生率は期待するほど下がらず、今もとりわけ中央・西アフリカでは1人が5~6人産むのが当たり前です。背景には、子どもが労働力になること、乳幼児死亡率の高さ、老後の社会保障がないため子どもが頼りになることなどがあります。つまり「たくさん産むほうが得」だからで、避妊具配布は的外れだと研究でも指摘されています。法律や制度があっても、最終的には「どちらが得か」で判断している。
この「どちらが得か」の思考は日本でも同じです。二人産むのが得なのか、一人でとどめるのか、あるいは結婚も出産もしないほうが得なのか、人はそれぞれ自分にとって最善だと思う選択をして行動しています。これがミクロ経済学の基本的な考え方です。これに基づいて考えれば、例えば出産一時金で50万円もらったとしても、その後20年間にかかる養育費や生活の保障があるわけではありませんから、「一時金があるから産もう」という発想にはなりません。
子供を産むことは、後戻りできない現実
犬山 意思決定の場に女性が三割以上いないことも問題だと思います。社会の中では、女性がまだまだマイノリティの場面が多い。そういう状況で議論が進むと、「子どもの数は増えてほしい、出生率は上がってほしい。でも自分たち男性が席を譲ったりしない、居心地のいい社会でもあってほしい」という、矛盾した、一方的な流れになってしまいます。
「女性を輝かせる」なんて言葉を聞くと、どこか上から目線にも感じてしまいます。だからこそ、牧野先生がおっしゃっていたように、最新の研究やエビデンスに基づいた取り組みを本気でやってほしいのです。
それから、女性たちの声が「お気持ち」みたいに軽んじられているのも問題だと思います。SNSを見れば、「子育てが本当にきつい」「夫が全然育児に参加しない」といった悲鳴がたくさんありますよね。でもそれを感情論として片付けてしまったら、こんなに生きづらい社会で子どもを産もうとは思えなくなる。女性の声を聞く時には、活躍している人ばかりではなくて、働き詰めのシングルマザーだったり、「二人目を欲しかったけど諦めた」といった現実を抱えている人たちの声にも、もっと耳を傾けてほしいと思います。子供を産むって、後戻りできないことなので。
牧野 女性の経済的な安定が少子化の歯止めになることを示唆する実証研究の成果がなぜ政策の場に活かされていないのか。犬山さんのお話を伺うと、競争に長けた男性が多くを占める政策担当者や政治家にとっては、やはり意図的にアップデートしない方が都合がいいのでそうしていない、という気がしてきました。都合がいいのは為政者だけ、女性の経済的安定は社会全体のためになるということがもっともっと知れ渡る必要があると思います。(終)