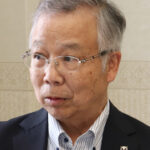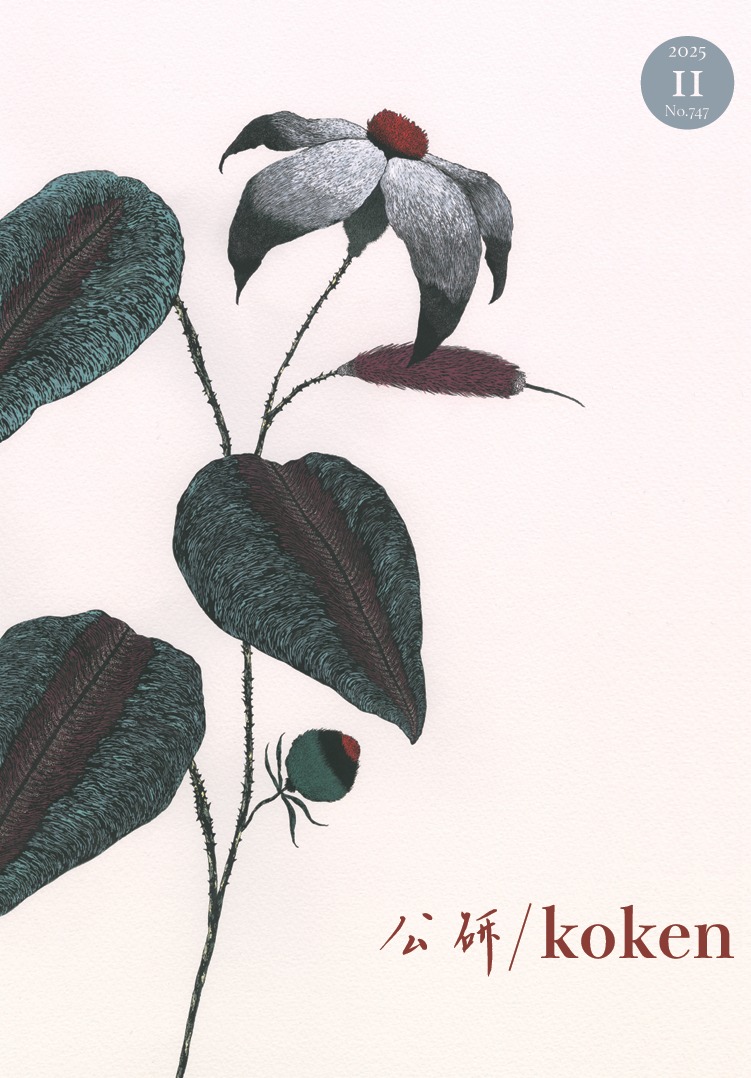『公研』2025年9月号「めいん・すとりいと」より
私は動物のコミュニケーションを研究し、そこから動物の心のあり方を探ろうとしている。デカルトに立ち返れば、自分の心だけは疑えない第一原理だが、他者の心の存在はいくらでも疑える。私たちが他者に心を仮定するのは外見や行動、コミュニケーションの類似ゆえであり、確たる根拠はない。それでも社会生活のために、私たちはおよそ5歳までには他者に心があると想定して行動するようになる。この想定に依拠して生きる私たちは「擬私主義者」であり、これを徹底して疑えば社会生活は成り立たない。
一方、人間以外(動物・植物・事物)に心を想定するのは「擬人主義」として戒められる。擬人主義は擬私主義を前提としており、私たちはまず人類一般の心を私の心の平均値のように見なし、その近似として動物の心を扱う。つまり、自分以外の人にも動物にも心があるというのはいずれも想定であり、心という体験が自己の内に閉じている以上、科学的にテストすることは極めて難しい。
このため、他者や動物に心を想定することは、現状、肯定にも否定にも決着しない。心理学は歴史の中で、証明困難な心を避け、観察可能な行動で説明する「行動主義」が力を得た。存在を証明できないものより、明らかに存在する現象を扱うほうが科学的だと見なされたからである。やがて心を情報処理として捉える立場が広がり、体験としての心を離れてモデル化すれば、いつか体験にも届くと期待された。しかし情報処理はあくまで情報処理であり、そこから飛躍的に体験が生まれる道筋は示せなかった。体験は自己という現象に特権的に許容されているかのようで、それ自体は科学の方法では扱いがたい。
再び時代は揺れ、「心は遍在する」という考えが現れた。自分だけに体験が生ずるとするより、万物に心があり体験があると考えるほうが自己を特権視しない点で公平に見える。これは反証不能で科学的とは言い難いが、心についての態度が科学的であるべきと考える根拠もない。もし心が遍在するなら、動物を搾取することは非倫理的となり、彼らの自由を最大限尊重し、行動を制御すべきではなくなる。原理的には首肯できても、現実にそのように生きることは可能なのだろうか。肉食、動物実験、ペット、動物園などすべて許容できなくなる。
心が遍在することを前提とした態度はいくつか考えられる。万物を尊重する世界を作ることである。最初からすべてを尊重できない。まずは動物、次に植物というように、順次尊重の範囲を広げることである。同時に尊重するとはどういうことなのかを考えなければなるまい。放置することは尊重することではなく、意識的思考を深めた我々ならではの尊重のしかたを模索する必要がある。次に我々が世界を尊重できないのであれば、我々自身を消し去ることである。もしくは私自身を消し去ることである。これは消極的とも無責任ともいえるが、取り得る態度であることは確かだ。第三に、自分自身の心を特権的にとらえることをやめ、遍在する心の一つとして万物と調和して生きることをめざすことだ。
私自身の研究と思索が、私自身の研究と思索を制限せざるを得ない結果になってきた。心的体験が植物にもあるとしたら、それは生命とほぼ同義になろう。さらにこれを事物に拡張するとしたら、それは存在と同義になる。このような拡張は、心の研究を漠然とした混沌に投げ入れることになる。私は結局、何がしたいのか。
生物心理学者