『公研』2023年7月号
最近は中国がニュースにならない日はなく、決まって習近平主席が登場する。毎日見ていると、中国では全てのことが習主席の鶴の一声で決ま り、動いているような気分にさせられるが、そんなことはない。中国には他にも有力なアクターがいるのだ。例を二つ挙げる。
一例は昨年暮れのゼロコロナ政策撤廃だ。11月11日政府が隔離期間の短縮、建物封鎖の範囲の縮小などの規制緩和を発表した。ところが、統治機構の末端が感染拡大(の責任追及)を恐れて緩和の指示に従わなかった。「話が違う!」緩和を待ち望んでいた国民は怒りを爆発させ、至るところの住宅団地で住民が取り締まり側と衝突した。
メディアは白紙を掲げて抗議する大学生らの姿を報じて我々の視覚に訴えたが、大半は封鎖されたキャンパス内の出来事で、数もたかが知れている。中国共産党はあれしきのことでは動じない。 しかし、「仕事に行かせろ」「食べ物を買いに行かせろ」と、全国至るところで起きた住民の切実な抗議は、比較にならないほどマグニチュードが大きかった。
政府はこれを見て11月末、ゼロコロナ政策を一気に撤廃するに等しい対応に踏み切った。一説によると、習近平主席は自分の名の下で進めてきた政策の撤廃に難色を示したが、抗議の広がりを前に、渋々同意したのだという。
もう一例は今年4月に起きた中国戦狼外交官の 「不規則」発言だ。在仏の中国大使がテレビ出演して、エストニアなど旧バルト三国は「主権国家としての地位を裏付ける国際合意がないため、国際法上実効的地位を有していない」と発言、たちまち欧州中の強い怒りを買った。
米国との深刻な対立を抱える中国は、他の国からの支持取り付けに懸命だ。グローバルサウス諸国との関係は良好だが、この数年、台湾や安全保障の問題をめぐって悪化した欧州との関係が頭痛の種で、中国は巻き返しに躍起になっている。発言の2週間前には、習近平主席自らが仏マクロン大統領やEUのフォンデアライエン議長を招いて、デカップル論を排したり、米中対立における欧州の中立を促したばかりだ。
そんな努力をこの発言で台無しにした大使が解任されるどころか、何のお咎めもなかったのはどうした訳か。
謎を解く鍵は中国の世論にある。ウクライナとロシアの戦争について、政府は「中国はロシア寄り」と見られることを嫌って、中立をアピールしているが、国内のメディアやSNSは、旗幟鮮明に「親ロシア、反欧米」だ。この大使もこれまで数々の戦狼発言を重ねて、国内で人気がある。恐らく「習近平主席の不興を買っても、処罰はされない」自信があって発言したのだろう。
こうして見ると、習近平主席は内政でも外交でも、万事を我が意のままに動かせる訳ではないことが見えてくる。姿かたちははっきりしないが、中国には体制内マジョリティというアクターがいて、その意思が明確なベクトルを持つと、習近平主席も従わざるを得ないということだ。
このアクターは、外交面では習主席ら執行部よりも対外強硬派で反西側的だ。その傾向は以前からあったが、コロナで西側との軋轢が高まって以降、いっそう強まった。
一方、中国は今年に入って経済不振が顕在化して、国民の間に先行き不安が高まっているところだ。これを機に、頑なになった中国の民意が和らぐことを期待したいが、事態が更に悪化する恐れもある。
どちらに転ぶかは、我々の出方にもかかっている。中国国民を和ませるようなオリーブの枝を振ることができればと思う。
日本国際問題研究所客員研究員






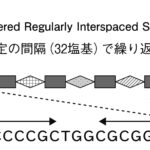

![「コロナの時代」の戦略思考[第7回]「『危機の20年代』の序幕」【池内恵】](https://koken-publication.com/wp-content/uploads/2022/12/池内先生-150x150.png)
